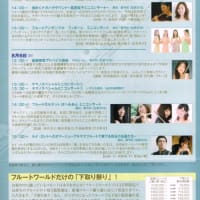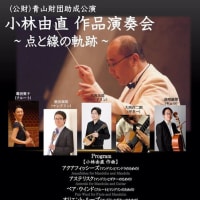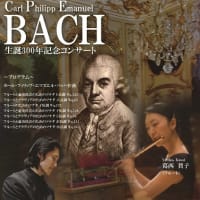ロングトーン
曲を吹く前に、体を「フルートモード」にもっていき、
運指に神経を邪魔されることなく音をつくり、整えるための
必須の基礎練であることは疑いの余地もありません。
(楽曲を吹くときには、すでに体と音は整った状態で、
その楽曲の表現のほうの練習に、集中力を費やす必要があります。)
問題はその内容(汗)
以前ドイツで、オーレル・ニコレ氏のマスタークラスで、とあるドイツのフルートの学生が
(もともと美しい音にも関わらず)ロングトーンにほとんどそのレッスンが終始し、
その、ニコレ氏の耳の厳しさと、受講生に対しても決して妥協を許さない姿勢に、
強烈な印象を覚えています。(しかしあの妥協しない、あきらめない演奏家魂・・あれは本当に、
フルートを吹く者の心がけとして、その後の私にとても良い転機となりました)
モイーズの「ソノリテについて」の、あの、始まりのロングトーン。それだけで。
何度も何度も、シ~#ラ~の一課題を、
「響きが上に行ってない」 に始まり、
「音の方向性がわからない」
「その音には、どんな感情をこめて吹いているのだ?」
「響きの最高に美しいmf」「次はff!」「pp!!」「ff>ppへ!」
それはもう、様々な課題・・いえ、目標ですね、目標をもって、次々とロングトーンをさせます。
しかし、あぁ、ギャラリーを目の前に追い込まれて、憐れな受講生・・(涙)焦りますよ、あんな状況・・
(さらにその後、やっと、曲にいったか・・と思いきや、ヘンデルのソナタのハ長調1楽章の冒頭、
ド・ミ・ソ・シ・ド・・の、最初のドからミに移るその二音間で、音にひずみがある!とさらに数分・・(泣))
ロングトーンは、音を美しく整えるために必要不可欠な練習とされていますが、
音をルーチン的に(”こういう響き”という目標なしに)ただ伸ばしているだけでは、
吹いているうちに音が自動的に美しく成長するなどありえない、
すべての音に、自分の心と頭からしっかりとした”Meinung(意見・考え・・意味?)”
をもって音を出すことに臨まなければ、「音楽たる音」は出しえない、と・・。
(これには色々な意味があります。曲のキャラクター的な角度、それから調性、そしてハーモニー・・
少し掘り下げて説明すると、例えば同じ「ド」を吹くにも、
ド・ミ・ソのハ長調の明るいドなのか、あるいはラ・ド・ミの暗い響きの中のドなのか、
はたまた和音の中でその音が根音なのか、第3音目なのか、一番上の第5音目なのか・・
それによっても、響き(実際的には音程の高さや倍音)が微妙に違います。)
・・ここまで細かく考えるのは、本当に究極の理想ではありますが

(しかしバロックや古典の曲を本当に理解して吹くには、やはり避けて通れないことでしょう)
◆◇◆
ちょっと深く掘り下げたマニアックな話になってしまいました
違う角度からもう少し具体的な話に話題を戻して・・(汗)
ロングトーンにしろ、
そしてそれからこれは、さらに音階や分散和音などのテクニック練習の時にもですが、
基礎練習とは、
「適切な条件で、各音に対し、適切な息運びできちんと楽器に息を送れているか」
を、自らの耳で、本当によく一音一音に集中を払いながら、チェックしながら、吹くことです。
「適切な条件」とは、
上半身・肩まわりや腕・下半身の姿勢が、どこの筋肉も特別に固く縮んでいることなく、
常にしなやかでニュートラルであること、
また、豊かで深い呼吸のために、体(胸郭)の中は広く、
そして横隔膜が柔軟に動けるよう”お腹を固めすぎない”弾力性の備わった状態が整っていること、
口・唇の形が、引っ張ったりしめつけすぎたりせずに、下顎がほどよく脱力、
そして口の中はほどよく空間があき(上下の歯の間が狭くない、舌の位置が浮いていない・・など)、
両の唇ではきれいな適切な大きさの口の穴(息の出口)が作られていること、
それらの、音を出すための条件下で、後は一音一音が美しく響いているか…
自身に厳しく、良い音を出したい貪欲さで、一音一音出すことです。
・・・もちろん今上に簡単に書いた「条件」の一つ一つを満たすことの、
どれも一筋縄にいかない経験者の筆頭は自分です・・
最初はなかなか前に進まず、辛い時もあるかもしれませんが、集中力!
そして慣れも肝心で、そういった「細心の注意」と「飽くなき音への欲求」は、
紆余曲折を経ても、良い結果に結び付いていくでしょう。
ロングトーンなど基礎練習時間の、ひとつの大きな指標・・の今日のこのお話でした


↑クリック応援、いつもありがとうございます


曲を吹く前に、体を「フルートモード」にもっていき、
運指に神経を邪魔されることなく音をつくり、整えるための
必須の基礎練であることは疑いの余地もありません。
(楽曲を吹くときには、すでに体と音は整った状態で、
その楽曲の表現のほうの練習に、集中力を費やす必要があります。)
問題はその内容(汗)
以前ドイツで、オーレル・ニコレ氏のマスタークラスで、とあるドイツのフルートの学生が
(もともと美しい音にも関わらず)ロングトーンにほとんどそのレッスンが終始し、
その、ニコレ氏の耳の厳しさと、受講生に対しても決して妥協を許さない姿勢に、
強烈な印象を覚えています。(しかしあの妥協しない、あきらめない演奏家魂・・あれは本当に、
フルートを吹く者の心がけとして、その後の私にとても良い転機となりました)
モイーズの「ソノリテについて」の、あの、始まりのロングトーン。それだけで。
何度も何度も、シ~#ラ~の一課題を、
「響きが上に行ってない」 に始まり、
「音の方向性がわからない」
「その音には、どんな感情をこめて吹いているのだ?」
「響きの最高に美しいmf」「次はff!」「pp!!」「ff>ppへ!」
それはもう、様々な課題・・いえ、目標ですね、目標をもって、次々とロングトーンをさせます。
しかし、あぁ、ギャラリーを目の前に追い込まれて、憐れな受講生・・(涙)焦りますよ、あんな状況・・

(さらにその後、やっと、曲にいったか・・と思いきや、ヘンデルのソナタのハ長調1楽章の冒頭、
ド・ミ・ソ・シ・ド・・の、最初のドからミに移るその二音間で、音にひずみがある!とさらに数分・・(泣))
ロングトーンは、音を美しく整えるために必要不可欠な練習とされていますが、
音をルーチン的に(”こういう響き”という目標なしに)ただ伸ばしているだけでは、
吹いているうちに音が自動的に美しく成長するなどありえない、
すべての音に、自分の心と頭からしっかりとした”Meinung(意見・考え・・意味?)”
をもって音を出すことに臨まなければ、「音楽たる音」は出しえない、と・・。
(これには色々な意味があります。曲のキャラクター的な角度、それから調性、そしてハーモニー・・
少し掘り下げて説明すると、例えば同じ「ド」を吹くにも、
ド・ミ・ソのハ長調の明るいドなのか、あるいはラ・ド・ミの暗い響きの中のドなのか、
はたまた和音の中でその音が根音なのか、第3音目なのか、一番上の第5音目なのか・・
それによっても、響き(実際的には音程の高さや倍音)が微妙に違います。)
・・ここまで細かく考えるのは、本当に究極の理想ではありますが


(しかしバロックや古典の曲を本当に理解して吹くには、やはり避けて通れないことでしょう)
◆◇◆
ちょっと深く掘り下げたマニアックな話になってしまいました

違う角度からもう少し具体的な話に話題を戻して・・(汗)
ロングトーンにしろ、
そしてそれからこれは、さらに音階や分散和音などのテクニック練習の時にもですが、
基礎練習とは、
「適切な条件で、各音に対し、適切な息運びできちんと楽器に息を送れているか」
を、自らの耳で、本当によく一音一音に集中を払いながら、チェックしながら、吹くことです。
「適切な条件」とは、
上半身・肩まわりや腕・下半身の姿勢が、どこの筋肉も特別に固く縮んでいることなく、
常にしなやかでニュートラルであること、
また、豊かで深い呼吸のために、体(胸郭)の中は広く、
そして横隔膜が柔軟に動けるよう”お腹を固めすぎない”弾力性の備わった状態が整っていること、
口・唇の形が、引っ張ったりしめつけすぎたりせずに、下顎がほどよく脱力、
そして口の中はほどよく空間があき(上下の歯の間が狭くない、舌の位置が浮いていない・・など)、
両の唇ではきれいな適切な大きさの口の穴(息の出口)が作られていること、
それらの、音を出すための条件下で、後は一音一音が美しく響いているか…
自身に厳しく、良い音を出したい貪欲さで、一音一音出すことです。
・・・もちろん今上に簡単に書いた「条件」の一つ一つを満たすことの、
どれも一筋縄にいかない経験者の筆頭は自分です・・

最初はなかなか前に進まず、辛い時もあるかもしれませんが、集中力!
そして慣れも肝心で、そういった「細心の注意」と「飽くなき音への欲求」は、
紆余曲折を経ても、良い結果に結び付いていくでしょう。
ロングトーンなど基礎練習時間の、ひとつの大きな指標・・の今日のこのお話でした

↑クリック応援、いつもありがとうございます