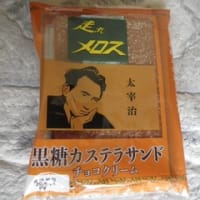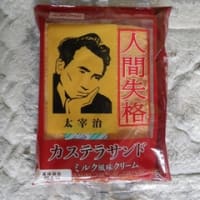沼津市のHPにも、考古学のおやつにもどこにもお知らせが載っていないんだけど、3月10日は興国寺城の現地説明会でした。昨年は震災の翌日だったなぁと思い出した。あまり宣伝しないのは、たくさん人が来ると対応出来ないからかなぁ。最近、春風亭昇太サンが山城の魅力をTVで語っているから、人気が出ちゃって人がたくさん来てしまうかも・・と恐れたのかな。チラシを一部に配っていただけだった。それでも1台多摩ナンバーの車が来ていたのは驚きだった。秘密の情報網があるのかなぁ。
今年は、昨年に引き続き三ノ丸の調査です。
根方街道の北側では、外側の濠とその土留めの石垣、杭などが発見されました。土層断面を見る限りではこの石垣以前にも掘り込まれた堀の跡が2つはあって、それを埋めてまた掘り込んでいることが分かる。いずれも一旦堀を埋めた後、その外側を掘り込んでいるので、城の拡張を思わせる。船着場の伝承のある地区の南側とのことで、ここを小舟が通行して城へ物資を運び入れることが行われていたのだろうか。

石垣の外側に杭が打たれていたので、石垣の時期と杭で土留めをしていた時期が見られるので、最終的な濠だけでも2つは時期が設定出来る。最後の堀を埋めている土はあまり急激に埋めたという土ではないので、廃城となった後に徐々に埋まっていったのかも知れない。ということは江戸時代に書かれた絵図の段階では、現地には堀跡がある程度残存していたのかな。

現在の根方街道を渡り、南の調査区では昨年発見された土塁の下に石列を伴う整地面が発見されました。中部ロームの面まで掘り下げてしまっていますが、上に黒い土の整地面があり、写真の石列の右側が平坦に仕上げられている。ここには何か建物があったかも知れないとの説明があった。石列の左側は一段下がった面があり、さらに中部ロームが高くなっているので、ここには排水用の溝があったのかも知れない。この日は前日から降り続く雨により、かなり水がたまっている。中部ロームは水がたまりやすく、また濡れるととても滑りやすいので整地面にはあえて別の土(黒土)を敷いているのかも。また、排水が最大の問題となるだろう。

南の調査区東側にある土塁跡と堀跡。雨で堀に水がたまっているので分かりやすいね(笑)ここには近年まで民家があったので土塁は完全に中部ローム面まで削平されてしまっている。また、あちこちの撹乱もひどい。


そんな堀から今年はいろいろと遺物が出て来たという。16世紀末のかわらけ、すり鉢、初山や志戸呂焼などもあった。江戸時代の物も多く、やはり堀は江戸時代にも残されていたらしい。そして徐々に埋まっていったのだろう。

城からは木製品ってあまり出ないのだけど、下駄が出ていました。ただし、時期不明。下駄はあまり形が変わらないから時期差が出ないよねー。

滑石制の石鍋などもありました。城が出来る前の時代からずっと人がここにいたのは確かです。阿野荘もあったことだし。
三の丸もいくつかの時期が発見され、興国寺城の変遷をいろいろとつなぎ合わせながら考察しなければならないので、ちょっと大変。なんせ100年以上も存続した城なので、その間に様々な拡張が行われている。それぞれの遺構の変遷は部分的に見えるけど、遺構同士がどのような併行関係にあるかを、「城の縄張り」という視点から考察する必要があるだろうと思う。
今年は、昨年に引き続き三ノ丸の調査です。
根方街道の北側では、外側の濠とその土留めの石垣、杭などが発見されました。土層断面を見る限りではこの石垣以前にも掘り込まれた堀の跡が2つはあって、それを埋めてまた掘り込んでいることが分かる。いずれも一旦堀を埋めた後、その外側を掘り込んでいるので、城の拡張を思わせる。船着場の伝承のある地区の南側とのことで、ここを小舟が通行して城へ物資を運び入れることが行われていたのだろうか。

石垣の外側に杭が打たれていたので、石垣の時期と杭で土留めをしていた時期が見られるので、最終的な濠だけでも2つは時期が設定出来る。最後の堀を埋めている土はあまり急激に埋めたという土ではないので、廃城となった後に徐々に埋まっていったのかも知れない。ということは江戸時代に書かれた絵図の段階では、現地には堀跡がある程度残存していたのかな。

現在の根方街道を渡り、南の調査区では昨年発見された土塁の下に石列を伴う整地面が発見されました。中部ロームの面まで掘り下げてしまっていますが、上に黒い土の整地面があり、写真の石列の右側が平坦に仕上げられている。ここには何か建物があったかも知れないとの説明があった。石列の左側は一段下がった面があり、さらに中部ロームが高くなっているので、ここには排水用の溝があったのかも知れない。この日は前日から降り続く雨により、かなり水がたまっている。中部ロームは水がたまりやすく、また濡れるととても滑りやすいので整地面にはあえて別の土(黒土)を敷いているのかも。また、排水が最大の問題となるだろう。

南の調査区東側にある土塁跡と堀跡。雨で堀に水がたまっているので分かりやすいね(笑)ここには近年まで民家があったので土塁は完全に中部ローム面まで削平されてしまっている。また、あちこちの撹乱もひどい。


そんな堀から今年はいろいろと遺物が出て来たという。16世紀末のかわらけ、すり鉢、初山や志戸呂焼などもあった。江戸時代の物も多く、やはり堀は江戸時代にも残されていたらしい。そして徐々に埋まっていったのだろう。

城からは木製品ってあまり出ないのだけど、下駄が出ていました。ただし、時期不明。下駄はあまり形が変わらないから時期差が出ないよねー。

滑石制の石鍋などもありました。城が出来る前の時代からずっと人がここにいたのは確かです。阿野荘もあったことだし。
三の丸もいくつかの時期が発見され、興国寺城の変遷をいろいろとつなぎ合わせながら考察しなければならないので、ちょっと大変。なんせ100年以上も存続した城なので、その間に様々な拡張が行われている。それぞれの遺構の変遷は部分的に見えるけど、遺構同士がどのような併行関係にあるかを、「城の縄張り」という視点から考察する必要があるだろうと思う。