
2016年あけましておめでとうございます。
2014年2月。2期目の市議会に送り出していただいてから2年が経ち、折り返し地点となりました。
右も左もわからなかった1期目と比べれば経験が蓄積され、見通しを持って仕事にとりくむことができるようになってきた気がしています。
同時に、わからないということもとても大事で、ふとした疑問や違和感、日常生活を送る地域の人としての生活の感覚も大切に活動していきたいと感じています。
常に、実践と検証をくり返し、原点に立ち返っていくことを誠実にやっていきたいと思います。
参院選を軸に、政治を大胆に転換する歴史的な一年にするために微力ながら力を尽くしていく決意です。
みなさまのご指導、ご鞭撻をよろしくお願いします。
■□■□■□■□■□
元日の「朝日」──オピニオン選べない国で──にフォトジャーナリストの安田菜津紀さんが登場していました。
そこで論じられていた「若い人に届く言葉で政治を」の内容は、地方議員である私が心がけていきたいと感じていることと通じるものでした。
一部引用させていただきます。
政治に選択肢がない、選びたくても選べないと言われます。その通りですが、私はそれ以前に、そもそも政治と関わる方法の選択肢がとても少ないように思います。
例えば昨年、盛んになった国会前のデモ。確かに政治と関わる選択肢の一つです。デモに参加することによって自分の意思を表明する、という。ただ、安保法制には疑問があるけれど「安倍(首相)はやめろ!」と叫ぶには抵抗があるという若い人たちもいる。私もその一人です。
激しいデモに行くのか、だんまりなのか、どっちなんだという、無言の圧力みたいなものがあったような気がして。「デモに行けない自分は何も出来ていない」と無力感を持った高校生もいました。デモに行く、行かないの間に、もっと多様な選択肢や関わりがあったほうがいい。
(中略)
SEALDsのような抗議行動も大事だけれど、日常的に対話すること、生の対話を重ねていくことも大事なはずです。日頃のコミュニケーションが健全にとれていないと、投票でも正確な選択はできないですから。発信するだけ、声を上げるだけではだめ。相手に届かなければ、コミュニケーションしたことにはならないですね。
(中略)
政治家のみなさんに考えてほしいのは「自分が何を伝えたいか」ではなく、「若い人たちが何に問題意識を持っているか」です。彼らはやがて社会を築く側になります。政治とつながっていると実感を持てたかどうかで、大きく変わるはず。そのきっかけをつくり、共通言語を見つけた政党や政治家が、やがて支持を得られる可能性が出てくるのかな。そこに変化の兆しが見えるかもしれない。
(中略)
メディアで大きく取り上げられて、多くの人に「問題だ」と共有されないと「問題」にならない。でも当事者たちは、自分から声を上げるのが難しい立場にあることがほとんどです。政治とは小さな声を置き去りにしないことが役割ではなかったでしょうか。まずそこから正さないと選択肢が偏ってしまい、選択する機能自体がマヒしてしまう気がします。
(「朝日」2016.1.1 オピニオン 選べない国で 「若者に届く言葉で政治を」フォトジャーナリスト 安田菜津紀)
にほんブログ村←池川友一のつながるブログを見ていただきありがとうございます。一日1回、応援クリックをお願いします。
┏┓池川友一|日本共産党町田市議会議員
┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【事務所】
〒195-0061 町田市鶴川5‐10‐4
電話・FAX/042(734)1116
メール/up1@shore.ocn.ne.jp
※無料の生活相談、法律相談をおこなっています。お困りごとはなんでもお気軽にご連絡ください。











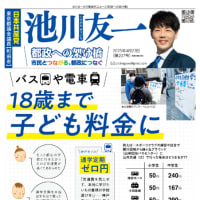


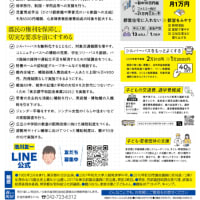
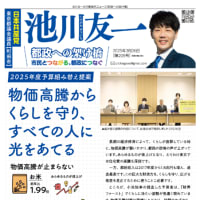



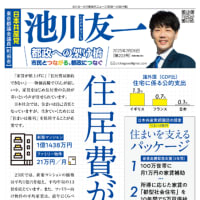
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます