A「ブログで帽子の女の子描いたんだよ。」
B「んー、なんかあまりよくわからない。」(苦笑)
A「まぁちょっと後で加えたからかな。」
B「もっと涼しくなるような絵ってない?」
B「たしか前に水浴びの絵とか。」

B「あれを完成させてみれば」
A「まぁ、あれはテストだったからね。」
A「もっと雰囲気を出すには、もう1人は欲しいね。」
A「いつやる?え?お盆前?」
A「やさしいキャラだったから、次はすこし元気のいいキャラがいいかな。」
A「まぁ、お盆前にできたらやるよ。」
自宅から画像メールして

B「うん、いいね。何か少しそんな雰囲気が出てきたよ。」
A「ありがとう。」
A「後で描きいれるのは、出来るかどうか不安だったけど」
A「描く前と何とか絵がつながりました。」
とまぁ、こんな話を以前ブログに書いた例のキャラ(おい)と話しました。
こんなことも★
ジオシティーズのアクセス解析はどうなるのか、わからないので
とりあえずみなさんで、アクセス数を見てみましょう。
これはhttp://www.geocities.jp/fullmsx2/u-yan/のホームページの一覧です。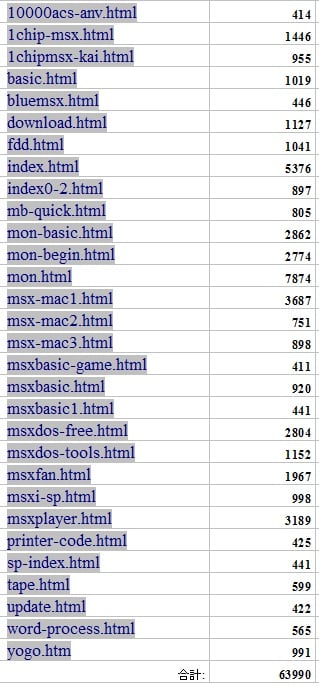
10000acs-anv.htmlはアイコン表示ファイラーのダウンロードができます。
download.htmlはまぁ、とにかくDLしてやってみようというもので、
これはカテゴリ別に紹介したものです。
fdd.htmlはFDDが動かない時の対処法などを考えてみたものです。
mb-quick.htmlはMSXBASICの解説のクイックリファレンスのページです。
頭にmonというのはマシン語モニタの解説とマシン語関連のページです。
msx-macはZ80マシン語をわかりやすくしたアセンブラ言語関連のページです。
とまぁ、このような結果です。
1chipMSX、MSXPLAYer、BlueMSXとMSXサイトとしては高いアクセス結果でした。
リストにないページは統合したり削除したり整理の対象のページになります。
コンプティークの2011年9月号を拝見しました。
シュタインズゲートの8ビット版はp44,45に大きく記事が載っています。
国民機ともされていたPC9801,PC8801をベースとしたような画面構成で
当時のパソコンイメージを思い出すような感じです。
なぜIBMではないのかと、ツッコミがありますが、
パソコンではなく汎用機で、このようなビジュアルな機能が全くなかったと思われます。
たしかネットワークの用途のみのコンピュータとしての役割でしたね。
それでPC98は16ビットでしたね、PC88のような640×400の画面構成?
に近くなったのでしょう。
ローレゾで描くと絵が下手に見える、歳をとった感じ、雑な感じとなりやすいです。
色数が減るとぼかしがなくなるので、ソフトがシャープになったりするところもあります。
曲線がポリゴンになるので、なかなか難しいのですが描いたとしたら、どうなんでしょうね。
最近のゲームは映画のような現実感あふれるリアル感が増えましたが、
逆にゲーム的なアニメのようなカラフルな雰囲気がなくなったと思います。
---
レトロポイント3
驚愕のコマンド直接入力方式
完全攻略は至難の業…?
<コンプティーク2011/09 より>
---
これは「見る 缶」をlook canと入力しますが、
このように動作、物の順番で入力していき、メッセージが変わるかどうか(フラグ変化)をさぐりながら
隠された選択肢をさがしだしていかなければならないようです。
また、RetroPC.NETでもこのような書き込みがありました。
---
>この作品をきっかけにレトロPCのAVG文化が盛り上がりを見せてくれると、
>大変に嬉しいなと思う管理人@RetroPC.NETなのでありました。
---
Windows3.1以前に多かったゲームシステムで、Windows95以降では自動化してマウスで選択する方式になりましたからね。
それでも、ある場所で選択肢の2を選ばないとバッドエンドというゲームは少なくありませんでした。
MSXパソコンでは「は~りぃふぉっくす」の雪の魔王編が有名ですね。
ウチのはたしかASCIIでこんなのがあります。
これはASCIIのダウンロードサービスで、
この時代はネットではなく誌面のプログラムのダウンロードという意味で
その中の1つのゲームアーツの作品です。
当時のMSXは記憶装置が10万程度していましたので、
ROMも高価だったのか、誌面から打ち込む形式でした。
本当のところはマシン語まじりのMSXBASICで何でもできていきました。
これはグラフィック画面ではなくて、多色刷りとスプライトで描いています。
で
(c) 1SceneAdventure 1987 GameArts
まだシステム的には近いのですが、数字で選択肢を選ぶものです。
ただ、今のゲームシステムと違うのは自分で動作して進めて行きます。
今のフルボイスのアドベンチャーゲームはストーリー進行型で自由なところはあまりありませんが、
電気を点けたり、ひきだしを開けたり、窓を開けたりと自分で動作をします。
「あ、手紙があった。」とか、「カギがかけられている」とか見えない発見があることがあります。















