
マイルス・デイヴィスを聴く際に気をつけなければならないことがある。
60年代の前半と後半で全くその色が変わっていることだ。
デビューから60年代中期頃までマイルスの音楽はまさしく「ジャズ」だった。
60年代の後半に入ってくるとマイルスの音楽に変化が訪れる。
まぁ、変化と言っているのは僕だけで、
当の本人にとっては全くの自然の流れだったのかもしれない。
マイルスがちょうどエレキ楽器を使うようになってきたのもこの時期ぐらいからだ。
そもそも60年代も後半になるとロックではエレキ楽器の使用が当たり前になってくる。
70年にはビートルズが活動休止状態になることを考えれば、
ただ単にフォービートのジャズを演奏していただけでは、若者は取り込めないだろう。
しかもロックの影響でレコードも売れるものを求めるようになってくる。
ブルーノートやプレスティッジのようにジャズレコードレーベルにとっては
苦しい環境が生まれてくるわけだ。
「オレ様」的マイルスが「かっこよさ」を求めて音楽に変化が生まれるのも当然だろう。
よく言われるのがリズムの追求である。
『イン・ア・サイレント・ウェイ』『ビッチェズ・ブリュー』などは、
一定のリズムに他の楽器が乗り、多様の変化を生み出していく。
『イン・ア・サイレント・ウェイ』では
グループを抜けたトニー・ウィリアムスを呼び戻している。
それだけリズムへのこだわりが感じされる人選だ。
よく『オン・ザ・コーナー』はその集大成的なアルバムで語られるが、
そこまでに積み重ねられてきたものは結果として後の
1976年、マイルスが休止状態になるまで生かされることになる。
『ダーク・メイガス』ではドラムとパーカッションのうねるようなリズムが
僕たちの耳をとらえる。
アル・フォスターはマイルス復帰後まで支えたドラマーであり、
エムトゥーメはその名を付けられた曲があるほどマイルスの70年代を支えた
パーカッション奏者である。
そこにまだ完全ではなかった2人のギタリストとデイブ・リーブマンが加わる。
いわゆる1973年バンドである。
前に『ジョン・レノンから始まるロック名盤』の時、
中山氏が「70年代は夢から覚め、現実的な部分が明らかになってきた時代」と
言っていたと書いたが、この時代のマイルスもまさに夢と現実の狭間にあるかのように
分厚く、かつ病的なリズムを従え、ひたすら何かに邁進していった様子が伝わってくる。
煙立ちそうなリズムの洪水はその時代を透かし見せているかのようである。
60年代の前半と後半で全くその色が変わっていることだ。
デビューから60年代中期頃までマイルスの音楽はまさしく「ジャズ」だった。
60年代の後半に入ってくるとマイルスの音楽に変化が訪れる。
まぁ、変化と言っているのは僕だけで、
当の本人にとっては全くの自然の流れだったのかもしれない。
マイルスがちょうどエレキ楽器を使うようになってきたのもこの時期ぐらいからだ。
そもそも60年代も後半になるとロックではエレキ楽器の使用が当たり前になってくる。
70年にはビートルズが活動休止状態になることを考えれば、
ただ単にフォービートのジャズを演奏していただけでは、若者は取り込めないだろう。
しかもロックの影響でレコードも売れるものを求めるようになってくる。
ブルーノートやプレスティッジのようにジャズレコードレーベルにとっては
苦しい環境が生まれてくるわけだ。
「オレ様」的マイルスが「かっこよさ」を求めて音楽に変化が生まれるのも当然だろう。
よく言われるのがリズムの追求である。
『イン・ア・サイレント・ウェイ』『ビッチェズ・ブリュー』などは、
一定のリズムに他の楽器が乗り、多様の変化を生み出していく。
『イン・ア・サイレント・ウェイ』では
グループを抜けたトニー・ウィリアムスを呼び戻している。
それだけリズムへのこだわりが感じされる人選だ。
よく『オン・ザ・コーナー』はその集大成的なアルバムで語られるが、
そこまでに積み重ねられてきたものは結果として後の
1976年、マイルスが休止状態になるまで生かされることになる。
『ダーク・メイガス』ではドラムとパーカッションのうねるようなリズムが
僕たちの耳をとらえる。
アル・フォスターはマイルス復帰後まで支えたドラマーであり、
エムトゥーメはその名を付けられた曲があるほどマイルスの70年代を支えた
パーカッション奏者である。
そこにまだ完全ではなかった2人のギタリストとデイブ・リーブマンが加わる。
いわゆる1973年バンドである。
前に『ジョン・レノンから始まるロック名盤』の時、
中山氏が「70年代は夢から覚め、現実的な部分が明らかになってきた時代」と
言っていたと書いたが、この時代のマイルスもまさに夢と現実の狭間にあるかのように
分厚く、かつ病的なリズムを従え、ひたすら何かに邁進していった様子が伝わってくる。
煙立ちそうなリズムの洪水はその時代を透かし見せているかのようである。













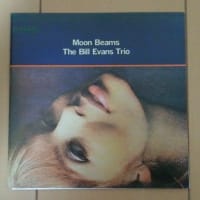
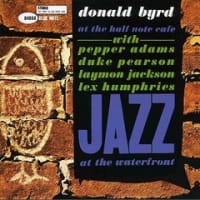

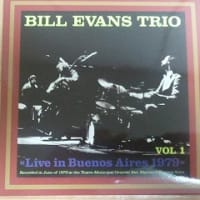


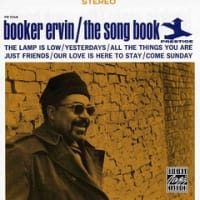
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます