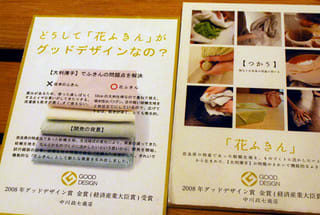うーん参った、こんな宿泊プランがあったとは。昨日(6/11)のフジサンケイビジネスアイで知ったのだが、ネット上に詳しい情報が出ていた。烏丸経済新聞(ネット新聞)の記事「『癒やし』求める女性向け尼僧修行体験宿泊プラン-グランヴィア京都」(6/2付)から引用する。
http://karasuma.keizai.biz/headline/782/
《ホテルグランヴィア京都(京都市下京区烏丸通塩小路下ル)は6月から、笠原寺(山科区)で実施される「1日尼僧修行体験」とホテル宿泊を組み合わせた女性限定の「『1日尼僧修行体験』宿泊プラン」の販売を始めた》。
http://www.granvia-kyoto.co.jp/stay/entry/000882.html

《大本山川崎大師京都別院である笠原寺は、1979(昭和54)年に笠原政江尼が開山し、翌年から来山する悩める女性を一堂に集めて話し相手になることを目的に「1日尼僧修行体験」を開始した。体験者は中学生から80代までと幅広く、延べ3,000人以上にのぼる》。
《同プランは2006年から毎年期間限定で販売しており、首都圏を中心とした「癒やし」を求める30~40代の女性をターゲットに据えている。同ホテル広報担当者は「尼僧体験という普段とは違う空間を無心で体験していただくとともに、京都を感じ楽しんでほしい」と話す》。
《スケジュールは、1日目に同ホテルチェックイン後自由行動。2日目の朝、笠原寺に移動し約6時間の尼僧体験後、現地解散となる。尼僧体験では、香をまたぎ心身を清浄にする儀式「足香」から始まり、精神統一をする「安座」、願い事を念じながら大日如来を描く「写仏」などを行う》。

ホテルグランヴィア京都のHPより拝借
《同担当者は「期間限定で尼僧体験を行う日程のみの設定にもかかわらず反響があり、例年20人前後の利用がある」と話す。「普段と違う空間と体験から自分を見つめ直し、癒やしを全身で体験できる。さらに京都の文化にも触れながらゆったりとした時間を過ごせて、現代に暮らす女性にはぜいたくなひとときになるはず」(同)とも》。
《設定日は6月~来年3月の指定日。料金は1人=25,000~30,000円(1室2人利用の場合)で、ホテル宿泊(朝食付き)・尼僧体験(昼食付き)・笠原寺までの往復タクシー代が含まれる。問い合わせ、予約は宿泊予約係(TEL 075-344-4433)で受け付けている》。
※ホテルグランヴィア京都のニュースリリース(PDF形式)
http://www.granvia-kyoto.co.jp/release/pdf/200905262_uploadfile.pdf

同 上
《首都圏を中心とした「癒やし」を求める30~40代の女性》というターゲットが良い。好奇心が旺盛で、おカネを持っている。口コミによる情報発信力もある。修行体験を終えると修了証と法名(戒名)もいただけるという。「戒名だけで○○万円」という話も聞くから、3万円の料金設定には割安感がある。写経だけの体験より、ずっと深い。
ホテルグランヴィア京都では、「『日本茶の味わい教室』宿泊プラン~京老舗 一保堂茶舗で学ぶ~」というプランも販売していて、これも好評だという。
http://karasuma.keizai.biz/headline/356/
尼さんもお茶も、奈良は京都の先輩格である。お茶は、空海が唐から持ち帰った種子を仏隆寺(宇陀市榛原区)で育てたのが、日本でのお茶栽培の始まりとされている。
他にも京都では、京都ブライトンホテルの「竹かご制作プラン」(元禄元年創業の「竹又 中川竹材店」で京都産「白竹」を材料にした「四海波(しかいなみ)かご」を製作するプラン)を始め、1日陶芸教室や豆腐、和菓子、ガラス工芸、箸袋づくりなど、様々な体験プランが用意されている。
http://www.kyoto-okoshiyasu.com/play/PlaySearchList.aspx?ctg=030400
奈良でも、ホテルサンルート奈良がおん祭りの際に行われる「遷幸の儀(せんこうのぎ)」(12月17日の深夜0:00~)に案内してくれるガイドツアーを実施したり、料理旅館・大正楼が「収穫体験プラン」を販売しているが、遷幸の儀は年に1回きりだし、収穫体験は「尼さん体験」ほどのインパクトに乏しい。
手漉き和紙や柿の葉寿司作りは私も体験したことがあるが、坊さん体験、山伏体験、雅楽体験、そうめん作り体験、、栃餅作り体験、奈良晒の箸袋作り体験、遺跡発掘体験など、奈良にはネタが満載だ。これを宿泊と結びつければ、全国最下位の宿泊者数も少しは増えると思うのだが…。
http://karasuma.keizai.biz/headline/782/
《ホテルグランヴィア京都(京都市下京区烏丸通塩小路下ル)は6月から、笠原寺(山科区)で実施される「1日尼僧修行体験」とホテル宿泊を組み合わせた女性限定の「『1日尼僧修行体験』宿泊プラン」の販売を始めた》。
http://www.granvia-kyoto.co.jp/stay/entry/000882.html

《大本山川崎大師京都別院である笠原寺は、1979(昭和54)年に笠原政江尼が開山し、翌年から来山する悩める女性を一堂に集めて話し相手になることを目的に「1日尼僧修行体験」を開始した。体験者は中学生から80代までと幅広く、延べ3,000人以上にのぼる》。
《同プランは2006年から毎年期間限定で販売しており、首都圏を中心とした「癒やし」を求める30~40代の女性をターゲットに据えている。同ホテル広報担当者は「尼僧体験という普段とは違う空間を無心で体験していただくとともに、京都を感じ楽しんでほしい」と話す》。
《スケジュールは、1日目に同ホテルチェックイン後自由行動。2日目の朝、笠原寺に移動し約6時間の尼僧体験後、現地解散となる。尼僧体験では、香をまたぎ心身を清浄にする儀式「足香」から始まり、精神統一をする「安座」、願い事を念じながら大日如来を描く「写仏」などを行う》。

ホテルグランヴィア京都のHPより拝借
《同担当者は「期間限定で尼僧体験を行う日程のみの設定にもかかわらず反響があり、例年20人前後の利用がある」と話す。「普段と違う空間と体験から自分を見つめ直し、癒やしを全身で体験できる。さらに京都の文化にも触れながらゆったりとした時間を過ごせて、現代に暮らす女性にはぜいたくなひとときになるはず」(同)とも》。
《設定日は6月~来年3月の指定日。料金は1人=25,000~30,000円(1室2人利用の場合)で、ホテル宿泊(朝食付き)・尼僧体験(昼食付き)・笠原寺までの往復タクシー代が含まれる。問い合わせ、予約は宿泊予約係(TEL 075-344-4433)で受け付けている》。
※ホテルグランヴィア京都のニュースリリース(PDF形式)
http://www.granvia-kyoto.co.jp/release/pdf/200905262_uploadfile.pdf

同 上
《首都圏を中心とした「癒やし」を求める30~40代の女性》というターゲットが良い。好奇心が旺盛で、おカネを持っている。口コミによる情報発信力もある。修行体験を終えると修了証と法名(戒名)もいただけるという。「戒名だけで○○万円」という話も聞くから、3万円の料金設定には割安感がある。写経だけの体験より、ずっと深い。
ホテルグランヴィア京都では、「『日本茶の味わい教室』宿泊プラン~京老舗 一保堂茶舗で学ぶ~」というプランも販売していて、これも好評だという。
http://karasuma.keizai.biz/headline/356/
尼さんもお茶も、奈良は京都の先輩格である。お茶は、空海が唐から持ち帰った種子を仏隆寺(宇陀市榛原区)で育てたのが、日本でのお茶栽培の始まりとされている。
他にも京都では、京都ブライトンホテルの「竹かご制作プラン」(元禄元年創業の「竹又 中川竹材店」で京都産「白竹」を材料にした「四海波(しかいなみ)かご」を製作するプラン)を始め、1日陶芸教室や豆腐、和菓子、ガラス工芸、箸袋づくりなど、様々な体験プランが用意されている。
http://www.kyoto-okoshiyasu.com/play/PlaySearchList.aspx?ctg=030400
奈良でも、ホテルサンルート奈良がおん祭りの際に行われる「遷幸の儀(せんこうのぎ)」(12月17日の深夜0:00~)に案内してくれるガイドツアーを実施したり、料理旅館・大正楼が「収穫体験プラン」を販売しているが、遷幸の儀は年に1回きりだし、収穫体験は「尼さん体験」ほどのインパクトに乏しい。
手漉き和紙や柿の葉寿司作りは私も体験したことがあるが、坊さん体験、山伏体験、雅楽体験、そうめん作り体験、、栃餅作り体験、奈良晒の箸袋作り体験、遺跡発掘体験など、奈良にはネタが満載だ。これを宿泊と結びつければ、全国最下位の宿泊者数も少しは増えると思うのだが…。