今日(25日)は、雑司が谷・鬼子母神境内で開催された劇団唐組公演『盲導犬』(作演出・唐十郎)を観、そのイマジネーションの高さに圧倒された。
実は私は、最近の唐組の芝居を比較的よく観ており、頭の中で、唐組といえばこういう内容でこういうレベルの芝居というイメージができあがってしまっているのだが、今回の公演は、よい意味でそのイメージを裏切り、いつもの水準をはるかに超えるすぐれた舞台になっていた。
物語は、盲人・影破里夫(えいはりお)がはぐれてしまった盲導犬ファキイルを探して新宿のコインロッカーにたどり着き、そこで現実とも幻想ともつかないさまざまな光景を目撃するという話。唐十郎の芝居は、その大半が自分が演出・主演するために書き下ろされているのだが、この『盲導犬』に関しては、1973年に蜷川幸雄率いる櫻社のために書かれ、石橋蓮司の主演で初演されており、唐にとっては初の演出。主演は唐組の稲荷卓央で、とらえどころのない役を好演。ちなみに「ファキイル」はイスラーム・スーフィズムに由来する言葉で、ほんらい托鉢僧・乞食僧を指すが、それが芝居の内容とつかず離れず結び付いている。きけばこれは澁澤龍彦の小説『犬狼都市』からとった命名(澁澤はこれを「断食僧」と解説している)というが、澁澤の小説を深く読み込んだ結果、そこから犬の名前を借りただけでも、作品のなかに澁澤的世界がたくみに溶け込んでいるということなのだろう。
さて私は初演の舞台も観ていないし、台本も読んでいなかったので、まっさらの状態で今回の公演を観たのだが、言葉が機関銃のように次々に発せられ、そのぶつかり合いのなかで、物語が予想もできない方向にどんどん進んでいくのが非常に刺激的で、実に気持ちが良かった。芝居のなかに心情的な要素が皆無というわけではないのだが、それでも作品全体を突き動かしているのは、登場人物の心ではなく、あくまでも彼らが発する言葉だ。言葉がそれを発した人間から離れて独り歩きし、一つの世界を形成していく。ある言葉に対する別の人物の対応も、けして心情的なものではなく、言葉に対する自動反応として処理され、新たな言葉に還元されてそれがさらに別の言葉へと増幅されていく。いつもの唐作品は、最初に不可思議な場面が提示され、後からその謎解きがあるのだが、『盲導犬』は謎が謎のまま放り出されてどこまでいっても解決がない。作品のテンションの高さが、意味づけや解釈の入り込む余地を見事なまでに拒んでいるのだ。こうして、舞台は、文字どおりの虚の世界にむけて、ものすごいエネルギーでまっしぐらに突進していく。言わばシュールな世界がシュールなままに宙吊りにされた感じで、観終わって、充実した高揚感がそのまま残る。そうしたなかで、ところどころで物語の世界が停止し、登場人物による歌が挿入されるのが、進行中の物語の虚構性を強調して絶妙の効果をあげている。
では『盲導犬』という作品は、一種のファンタジーとして成り立っているかというと、そうではない。このあたりがまた実におもしろいし、見事なのだが、この作品には、1973年の新宿の猥雑な光景(シンナー遊びをする少年の存在やその少年と主人公・影破里夫の同性愛関係)をそのまま写取ったような部分があり、初演の舞台を観た観客は、この点でも、リアルな世界と舞台の細部がもっているリアリティーのあいだの不思議な類似や乖離に虚をつかれたような感じを味わったのではないかとおもう(この芝居を観ているあいだ私はまったく気づかなかったが、この作品に映画『真夜中のカーボーイ』のパロディを読み取ったひともいた。1973年という時代性を考えれば、それは当然ありうるとおもう)。そしておそらくは、蜷川演出もそうした方向性を狙ったものだったのであろう。ところが、30数年という時間を経て、『盲導犬』が取り入れた現実の世界へと開かれた要素は生々しいリアリティーを失い、回顧の対象となってしまっている。その辺のギャップを計算して、唐は作品のもつリアル志向をほとんど封じてしまったようにおもえるが、そのために今回の公演は、「言葉の芝居」としての作品の良さが前面に押し出されるような結果となっている。
また唐組の芝居といえば、最後は会場となっている特設テントが割れて、テントの裏の現実にむけて舞台が開放されるのが決まりごとのようになっているのだが(この決まりごとはいつみても実におもしろい)、今回のそれは、やっていることはいつもと同じなのに非常にスリリングにおもえた。
ところで今日は公演の最終日だったので、芝居が終わると会場となったテントに円陣を組み、打ち上げの小宴会があった。私もそれにいれてもらって、唐十郎氏に直接感激を伝えることができた。ちなみに、唐氏によれば、今回の公演は初演の蜷川演出よりも時間的にかなり長いとのことだったが、それは、自分の作品だけにいろいろ思い入れがあって長くなったのではないかとおもった。また今回の公演は、唐氏がちょい役で出演しているのだが、目立とうとするところをベテランの役者にたしなめられるなど、軽妙でとてもおもしろい。聞けばこの役はオリジナルにはなく、自分が出るということで書き足した役だそうで、セリフも日によって少しづつ変えているという。そうした、基本となる台本はきちんとあって、その上に作者ならではのアドリブが加わるということも、作品に不思議な雰囲気を付加していたとおもう。
小宴では、来場した渡辺えり、大久保鷹、山崎哲、坪内祐三氏らがそれぞれの感想を述べたが、いずれもなるほどと納得できるものばかりだった。たとえば渡辺氏の感想は、30数年前に蜷川演出の『盲導犬』を観たことが自分の演劇活動の原点となっているが、今回の公演はそれとはまったく違う印象で、それなのにものすごく強烈で、今後演劇活動を続けていくうえで大きな刺激を受けたという主旨のものだった。
また山崎哲氏と言えば、私は、去年の11月に彼の作・演出の芝居『シャケ』と軍手を観ているのだが(小ブログ2008年11月19日付記事『秋田の実娘・少年殺害事件をテーマにした芝居を観る』参照)、今日は、この山崎氏とも少し話をし、私の翻訳のコピーをわたすことができた。
ということで、最後は自分の話になってしまったが、今日の芝居はほんとうにすばらしい公演だった。
実は私は、最近の唐組の芝居を比較的よく観ており、頭の中で、唐組といえばこういう内容でこういうレベルの芝居というイメージができあがってしまっているのだが、今回の公演は、よい意味でそのイメージを裏切り、いつもの水準をはるかに超えるすぐれた舞台になっていた。
物語は、盲人・影破里夫(えいはりお)がはぐれてしまった盲導犬ファキイルを探して新宿のコインロッカーにたどり着き、そこで現実とも幻想ともつかないさまざまな光景を目撃するという話。唐十郎の芝居は、その大半が自分が演出・主演するために書き下ろされているのだが、この『盲導犬』に関しては、1973年に蜷川幸雄率いる櫻社のために書かれ、石橋蓮司の主演で初演されており、唐にとっては初の演出。主演は唐組の稲荷卓央で、とらえどころのない役を好演。ちなみに「ファキイル」はイスラーム・スーフィズムに由来する言葉で、ほんらい托鉢僧・乞食僧を指すが、それが芝居の内容とつかず離れず結び付いている。きけばこれは澁澤龍彦の小説『犬狼都市』からとった命名(澁澤はこれを「断食僧」と解説している)というが、澁澤の小説を深く読み込んだ結果、そこから犬の名前を借りただけでも、作品のなかに澁澤的世界がたくみに溶け込んでいるということなのだろう。
さて私は初演の舞台も観ていないし、台本も読んでいなかったので、まっさらの状態で今回の公演を観たのだが、言葉が機関銃のように次々に発せられ、そのぶつかり合いのなかで、物語が予想もできない方向にどんどん進んでいくのが非常に刺激的で、実に気持ちが良かった。芝居のなかに心情的な要素が皆無というわけではないのだが、それでも作品全体を突き動かしているのは、登場人物の心ではなく、あくまでも彼らが発する言葉だ。言葉がそれを発した人間から離れて独り歩きし、一つの世界を形成していく。ある言葉に対する別の人物の対応も、けして心情的なものではなく、言葉に対する自動反応として処理され、新たな言葉に還元されてそれがさらに別の言葉へと増幅されていく。いつもの唐作品は、最初に不可思議な場面が提示され、後からその謎解きがあるのだが、『盲導犬』は謎が謎のまま放り出されてどこまでいっても解決がない。作品のテンションの高さが、意味づけや解釈の入り込む余地を見事なまでに拒んでいるのだ。こうして、舞台は、文字どおりの虚の世界にむけて、ものすごいエネルギーでまっしぐらに突進していく。言わばシュールな世界がシュールなままに宙吊りにされた感じで、観終わって、充実した高揚感がそのまま残る。そうしたなかで、ところどころで物語の世界が停止し、登場人物による歌が挿入されるのが、進行中の物語の虚構性を強調して絶妙の効果をあげている。
では『盲導犬』という作品は、一種のファンタジーとして成り立っているかというと、そうではない。このあたりがまた実におもしろいし、見事なのだが、この作品には、1973年の新宿の猥雑な光景(シンナー遊びをする少年の存在やその少年と主人公・影破里夫の同性愛関係)をそのまま写取ったような部分があり、初演の舞台を観た観客は、この点でも、リアルな世界と舞台の細部がもっているリアリティーのあいだの不思議な類似や乖離に虚をつかれたような感じを味わったのではないかとおもう(この芝居を観ているあいだ私はまったく気づかなかったが、この作品に映画『真夜中のカーボーイ』のパロディを読み取ったひともいた。1973年という時代性を考えれば、それは当然ありうるとおもう)。そしておそらくは、蜷川演出もそうした方向性を狙ったものだったのであろう。ところが、30数年という時間を経て、『盲導犬』が取り入れた現実の世界へと開かれた要素は生々しいリアリティーを失い、回顧の対象となってしまっている。その辺のギャップを計算して、唐は作品のもつリアル志向をほとんど封じてしまったようにおもえるが、そのために今回の公演は、「言葉の芝居」としての作品の良さが前面に押し出されるような結果となっている。
また唐組の芝居といえば、最後は会場となっている特設テントが割れて、テントの裏の現実にむけて舞台が開放されるのが決まりごとのようになっているのだが(この決まりごとはいつみても実におもしろい)、今回のそれは、やっていることはいつもと同じなのに非常にスリリングにおもえた。
ところで今日は公演の最終日だったので、芝居が終わると会場となったテントに円陣を組み、打ち上げの小宴会があった。私もそれにいれてもらって、唐十郎氏に直接感激を伝えることができた。ちなみに、唐氏によれば、今回の公演は初演の蜷川演出よりも時間的にかなり長いとのことだったが、それは、自分の作品だけにいろいろ思い入れがあって長くなったのではないかとおもった。また今回の公演は、唐氏がちょい役で出演しているのだが、目立とうとするところをベテランの役者にたしなめられるなど、軽妙でとてもおもしろい。聞けばこの役はオリジナルにはなく、自分が出るということで書き足した役だそうで、セリフも日によって少しづつ変えているという。そうした、基本となる台本はきちんとあって、その上に作者ならではのアドリブが加わるということも、作品に不思議な雰囲気を付加していたとおもう。
小宴では、来場した渡辺えり、大久保鷹、山崎哲、坪内祐三氏らがそれぞれの感想を述べたが、いずれもなるほどと納得できるものばかりだった。たとえば渡辺氏の感想は、30数年前に蜷川演出の『盲導犬』を観たことが自分の演劇活動の原点となっているが、今回の公演はそれとはまったく違う印象で、それなのにものすごく強烈で、今後演劇活動を続けていくうえで大きな刺激を受けたという主旨のものだった。
また山崎哲氏と言えば、私は、去年の11月に彼の作・演出の芝居『シャケ』と軍手を観ているのだが(小ブログ2008年11月19日付記事『秋田の実娘・少年殺害事件をテーマにした芝居を観る』参照)、今日は、この山崎氏とも少し話をし、私の翻訳のコピーをわたすことができた。
ということで、最後は自分の話になってしまったが、今日の芝居はほんとうにすばらしい公演だった。











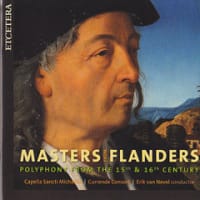


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます