一月もなかばを過ぎ、正月気分はもうほとんど抜けてきた。ただし私は年賀状をかなり遅く出したのでその返礼がまだぽつぽつ届く。大半は儀礼的なあたりもさわりもないものだが、なかに一通、ユニークなものがあったので、ちょっとそれをとりあげてみたい。
やりとりの相手はとある女性で、私からは「お兄さんが亡くなって20年がたちましたね」といった意味の、こちらからするとあたりもさわりもない儀礼的な文を書いて送ったつもりなのだが、彼女から戻ってきた季節の便りは、「私のアイデンティティは兄の妹ではないのです。私も一個の人格ですから、兄のことばかり書かれてもなんかうんざりです」という、ある意味でとてもキツイ内容のもの。
確かにそれはその通りで、彼女からすれば、彼女自身が一個の人格であり、単なる兄の妹ではないということになるのだろうが、こちらからするとそれ以外の彼女のアイデンティティは思い浮かばず、お兄さんの妹として彼女を尊敬している。いやこれはほんとうは「尊敬」などというものではなく私の自己満足に過ぎないかもしれず、彼女はその欺瞞を見抜いているということだろう。だから要するに、彼女独自のアイデンティティが見出せない以上、もう彼女にあてて年賀状を書いて欲しくないという、これは彼女からの義絶状と解すべきなのだろう。
それはさておき、このことからちょっとゲイのアイデンティティということを考えてしまった。つまり、多くのゲイは、ゲイであることをものすごく深刻で自分がつねに立ち返るべき決定的なアイデンティティと考えているような気がするのだが、ゲイであるということ(セクシャリテイ)はその人(ゲイ)の最も根本的なアイデンティティなのだろうかということだ。
例にあげては失礼かもしれないが、直前の記事に書いた青山吉良さんの演技、私からするとやはりそうしたアイデンティティにからむ問題をなげかけているようにも思えるので、その観点から『カルテット』をもう一度とりあげてみたい。
さて、最近、ゲイであることをおおやけにしている役者や劇団、またゲイをテーマにした作品がかなり出てきているように思うが、青山さんの演技も『カルテット』という作品も、表面的には性や性の超越を問題にしているが、ゲイであることを前提にしたものからは一線を画すものであることを、まずはっきりさせておかなくてならないと思う。つまり、『カルテット』という作品では、主役は女と男を演じ分けなくてはならず、そうした点からすると、一見、男と女の曖昧な境界線上に立つゲイの役者に有利な、ゲイという問題と直結する作品にも思えるのだが、話はそう単純ではないのだ。
この作品、一昨年、「女優」大浦みずきがベニサンピットで演じているといい(私は未見)、この場合、大浦はメルトゥイユ夫人だけでなくヴァルモン子爵をも演じなくてはならないわけだから、男が女を演じるということと、女が男を演じるということの基本条件は、誰が演じても同じ。また主役が演じる四つの役は、男女を超越させて中性的に演じればいいというのではなく、女は女、男は男としてそれぞれ屹立していなくてはならない。だから、中性的な曖昧な演技しかできない役者には、この役は演じようがない。
要するに、この芝居は、男が演じても女が演じても、「リアル」なものとしては演じようがないのだが、ある役柄を「リアル」なものとしては演じることができないという制限のなかでのリアリティの追求が、この芝居の眼目だと思う。
実はこの芝居から、私は人形浄瑠璃的な雰囲気を感じたのだが、人形浄瑠璃は、構造的に、(男でも女でもない)人形がある役を演じている(虚である)ということをつねに露出させながら、「実」に迫っていく。こちらとしては、舞台のうえで行われていることが完全に「虚」だとわかっているから、逆に安心して「虚の実」に入っていけるようなところがある。
また周知のように、人形浄瑠璃と古典歌舞伎は、歌舞伎が人形浄瑠璃の先行台本を取り入れたために多くの台本を共有しているが、同じ作品を上演しても、歌舞伎が一人一役による芝居によって戯曲のもつリアリティを抽出するという方向へ向かっていくのに対し、人形浄瑠璃は「虚」であることに固執し、いうなれば芝居のもつ象徴性の探究に向かう。人形浄瑠璃の人形は、もちろん、一体の人形が一つの役を演じるが、人形のそばで台本を語る大夫は、一人ですべての登場人物のセリフを語り、状況を説明していく(人形浄瑠璃でも、大勢の大夫がいろいろな役のセリフを語り分けることはある)。『カルテット』の台本は、性の超越というより、そうした義太夫の語りを思わせるところがあるのだ。
こうなると、語り分け、演じ分けというのは、リアリズムというより芸の問題になってくるのだが、そうした意味でのレベルの高い芸への指向を、青山吉良さんの演技は感じさせてくれた(つくられた「語り」のうまさ)。要するに青山さんの場合、演技者がゲイであるということであって、その逆の、ゲイが演技者であるのではないということだ。
これはどういうことかというと、青山さんの演技のすばらしさは、彼がゲイであるということからきているのではないということ。だから、ゲイを前面に打ち出して、ゲイであるという「問題意識」をつねに投影しながら演技する役者とは、青山さんは一線を画している。青山さんの演技は、まず青山吉良という個人から切り離された演技として確立されており、そういう演技をする青山さんがたまたまゲイであるというだけのことなのだ。
ゲイとしてのアイデンティティの問題が、『カルテット』という芝居とどのように結びつくかつかないか、私は以上のように考える。
そして私は、プロとしての明確な自覚と高い技術をもった青山吉良さんの演技が好きだ。
やりとりの相手はとある女性で、私からは「お兄さんが亡くなって20年がたちましたね」といった意味の、こちらからするとあたりもさわりもない儀礼的な文を書いて送ったつもりなのだが、彼女から戻ってきた季節の便りは、「私のアイデンティティは兄の妹ではないのです。私も一個の人格ですから、兄のことばかり書かれてもなんかうんざりです」という、ある意味でとてもキツイ内容のもの。
確かにそれはその通りで、彼女からすれば、彼女自身が一個の人格であり、単なる兄の妹ではないということになるのだろうが、こちらからするとそれ以外の彼女のアイデンティティは思い浮かばず、お兄さんの妹として彼女を尊敬している。いやこれはほんとうは「尊敬」などというものではなく私の自己満足に過ぎないかもしれず、彼女はその欺瞞を見抜いているということだろう。だから要するに、彼女独自のアイデンティティが見出せない以上、もう彼女にあてて年賀状を書いて欲しくないという、これは彼女からの義絶状と解すべきなのだろう。
それはさておき、このことからちょっとゲイのアイデンティティということを考えてしまった。つまり、多くのゲイは、ゲイであることをものすごく深刻で自分がつねに立ち返るべき決定的なアイデンティティと考えているような気がするのだが、ゲイであるということ(セクシャリテイ)はその人(ゲイ)の最も根本的なアイデンティティなのだろうかということだ。
例にあげては失礼かもしれないが、直前の記事に書いた青山吉良さんの演技、私からするとやはりそうしたアイデンティティにからむ問題をなげかけているようにも思えるので、その観点から『カルテット』をもう一度とりあげてみたい。
さて、最近、ゲイであることをおおやけにしている役者や劇団、またゲイをテーマにした作品がかなり出てきているように思うが、青山さんの演技も『カルテット』という作品も、表面的には性や性の超越を問題にしているが、ゲイであることを前提にしたものからは一線を画すものであることを、まずはっきりさせておかなくてならないと思う。つまり、『カルテット』という作品では、主役は女と男を演じ分けなくてはならず、そうした点からすると、一見、男と女の曖昧な境界線上に立つゲイの役者に有利な、ゲイという問題と直結する作品にも思えるのだが、話はそう単純ではないのだ。
この作品、一昨年、「女優」大浦みずきがベニサンピットで演じているといい(私は未見)、この場合、大浦はメルトゥイユ夫人だけでなくヴァルモン子爵をも演じなくてはならないわけだから、男が女を演じるということと、女が男を演じるということの基本条件は、誰が演じても同じ。また主役が演じる四つの役は、男女を超越させて中性的に演じればいいというのではなく、女は女、男は男としてそれぞれ屹立していなくてはならない。だから、中性的な曖昧な演技しかできない役者には、この役は演じようがない。
要するに、この芝居は、男が演じても女が演じても、「リアル」なものとしては演じようがないのだが、ある役柄を「リアル」なものとしては演じることができないという制限のなかでのリアリティの追求が、この芝居の眼目だと思う。
実はこの芝居から、私は人形浄瑠璃的な雰囲気を感じたのだが、人形浄瑠璃は、構造的に、(男でも女でもない)人形がある役を演じている(虚である)ということをつねに露出させながら、「実」に迫っていく。こちらとしては、舞台のうえで行われていることが完全に「虚」だとわかっているから、逆に安心して「虚の実」に入っていけるようなところがある。
また周知のように、人形浄瑠璃と古典歌舞伎は、歌舞伎が人形浄瑠璃の先行台本を取り入れたために多くの台本を共有しているが、同じ作品を上演しても、歌舞伎が一人一役による芝居によって戯曲のもつリアリティを抽出するという方向へ向かっていくのに対し、人形浄瑠璃は「虚」であることに固執し、いうなれば芝居のもつ象徴性の探究に向かう。人形浄瑠璃の人形は、もちろん、一体の人形が一つの役を演じるが、人形のそばで台本を語る大夫は、一人ですべての登場人物のセリフを語り、状況を説明していく(人形浄瑠璃でも、大勢の大夫がいろいろな役のセリフを語り分けることはある)。『カルテット』の台本は、性の超越というより、そうした義太夫の語りを思わせるところがあるのだ。
こうなると、語り分け、演じ分けというのは、リアリズムというより芸の問題になってくるのだが、そうした意味でのレベルの高い芸への指向を、青山吉良さんの演技は感じさせてくれた(つくられた「語り」のうまさ)。要するに青山さんの場合、演技者がゲイであるということであって、その逆の、ゲイが演技者であるのではないということだ。
これはどういうことかというと、青山さんの演技のすばらしさは、彼がゲイであるということからきているのではないということ。だから、ゲイを前面に打ち出して、ゲイであるという「問題意識」をつねに投影しながら演技する役者とは、青山さんは一線を画している。青山さんの演技は、まず青山吉良という個人から切り離された演技として確立されており、そういう演技をする青山さんがたまたまゲイであるというだけのことなのだ。
ゲイとしてのアイデンティティの問題が、『カルテット』という芝居とどのように結びつくかつかないか、私は以上のように考える。
そして私は、プロとしての明確な自覚と高い技術をもった青山吉良さんの演技が好きだ。











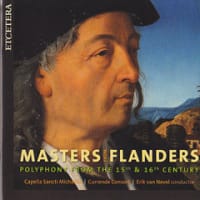


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます