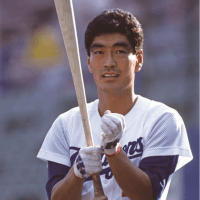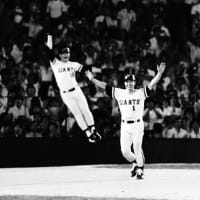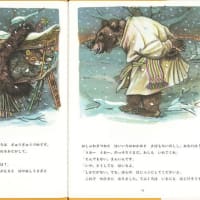2月22日 名古屋フィルハーモニー交響楽団第531回定期演奏会を聴きに行く。
地下鉄の駅を降りて、会場の愛知県芸術劇場に至る公園を歩く。
もう少しで芸術劇場の扉にたどり着くという時に後ろから「すみません」とちょっと中国のなまりのある声が聞こえた。
振り向くと中国人と思しき女性が僕の方に向かってメガネを差し出している。
そうか、公園を歩いているときにズボンのベルトに引っ掛けていた老眼鏡を落としたんだな。それを拾って声かけてくれたんだとわかった。
僕は差し出されたメガネを受け取って 「ありがとう おおきに」と言った。
すると彼女がニコッとしてくれたのでなんとなく今日は幸先がいいぞと思った。
人は何のために生きているのかというのはそんなに大げさな問いではなく、きっと、こういう瞬間を体験するために生きているのだろうと思った。
さて、2月22日のコンサート、川瀬賢太郎さんの指揮でマーラーの交響曲第6番が演奏された。
第一楽章、冒頭 低音の弦楽器(たぶんコントラバスとチェロ)がダッ ダッ ダッ ダッというリズムの核になる音を奏でるのだけれど そこが ドライで重々しくかつ鋭いという感じに思えた。
ここがリズムの核になるのでうまくいってよかったと思った。
川瀬さんもキビキビと鋭い気を送っておられてなんだか今日は、そして今日も、うまくいきそうと思った。
第一楽章で甘いラブソングのような旋律(演奏会当日プログラムの楽曲解説に第二主題と書いてある旋律と思う)が様々な楽器で何度となく出てくるけれど、あるときちょっと低めの弦の音でそれが出てきたので ビオラかなと思って見るとそうではなく その音は第二バイオリンから出ていた。
ふだんそんなに弦の音を聴き分けられるほど耳がよくないので その旋律が第二バイオリンで奏でられた時 バイオリンって思ったより低い音もオーケストラの中で担っているんだなと思った。
どうしても高音で旋律を歌う時にバイオリンに目が行くので普段気づかないことに気付けてよかった。
どの楽章かと言うのは忘れてしまったけれど 管楽器が木管を中心に静かに和声を伴った旋律を奏でるときは天国のような平安を感じることが多かった。
旋律もマーラー交響曲第二番の第一楽章の平安的な旋律(第二主題と思う)を思い出させるようものが何回か出てきた。
そして、この6番にでてくる平安的な雰囲気も交響曲第二番の特に第一楽章 第二楽章に表れてくる平安的な雰囲気に似ていると思った。
コンサートミストレスの方がスーッと上体を前に出して演奏されるタイプの方なのでそこから生まれる目の錯覚と言うか聴覚の錯誤だと思うのだけれど なんだかバイオリンは前の方からだけ音が出ているように思えることが演奏中何度かあった。
コンサートミストレスばかり見ているからそんな風に聴こえるんだと思って 第三楽章では意識的に後ろの方の奏者の方を見ていたらちゃんと音が聴こえてきたのでやはり目の錯覚と言うか聴覚の錯誤とわかってよかった。
ただ第三楽章でも音が細かく動くところはバイオリンの後ろの方からもよく音が聴こえてきたけれど 指揮者がバイオリンの前の方に気を送る場面になるとまた前の方からだけ音が出ているような感覚が芽生えてきた。
前の方の奏者がぐっと踏み込んでいて後ろの方がポーカーフェイス的な感じて奏でているとそのような錯誤がおきてしまうのだと思った。
コンサートでは視覚から得る印象がかなり大きいものだなと思った。
第四楽章は よかったけれど マーラーの良い所と言うか悪い所と言うか 盛り上がったと思うと盛り下がり、下がったかと思うとまた上がり 一体いつ終わるんや? という感覚にさいなまれたことも何度かあった。
中学生の頃、マーラー巨人の 第四楽章をレコードで聴いて いつも、「せっかく盛り上がったんだからここで終わればいいのに なぜ また盛り下げるのかよくわからんわ」 としばしば感じていたことを思い出した。
どうでもいいことだけど ホルンがソロ的に活躍する場面も全曲を通してかなりあったけれど 僕の席からだとホルン奏者は譜面台で半分隠れてしまう位置だったので 一体どこから音が出ているのだろうと探してしまう場面が何回かあった。
ホルンのソロは木管に近いような感じで 平安的と言うかスピリチュアルな雰囲気を醸し出すことが多かった。
一方でホルンからは堂々とした音が聴こえてくることもあり 本当に一つの楽器がいろんな音色を持っているんだなと思った。
今まで長い笛を持っていた人が気づくと短い笛に持ち替えていることもあり ややこしいことやなと思ったことも何度かあった。
マーラーは指揮者としても偉大な人だったらしいから こういうことを思いつくのだと思う。
木管が金管と同じ構えで奏することも何度かあった。
これはマーラーの交響曲を聴く楽しみの一つだと思う。
たぶん第四楽章の終わり近くにトロンボーンのコラールのようなものが出てきたけれど ちょうど僕の席にいわゆるラッパの口の開いたところが向かってくる感じで あれは 僕の席はちょっと得したなと思った。
でも金管には本当に若くてパワフルな方が多いので 盛り上がる所は 怒涛の盛り上がりと言う感じで それを聴くのが最近は楽しみの一つになってきた。
マーラーの音楽自体は金管を中心に怒涛の盛り上がりを見せた後 盛り下がって静かに終わるという構成になっていて ここにも 盛り上げ 盛り下げの構造がよく表れていると思った。
あと全体を通して、曲想の変化に演奏がよく対応していたと思った。
柔いところは柔らかく 悲しいところは悲しく 楽しいところは楽しく 力強いところは力強く 神秘的なところは神秘的にという具合に。
このところの寒さで こんなに寒いならどうしようと出かける前に一瞬思ったけれど、行ってよかったと心から思えるコンサートだった。
それはともかく一日いちにち無事に過ごせますように それを第一に願っていきたい。