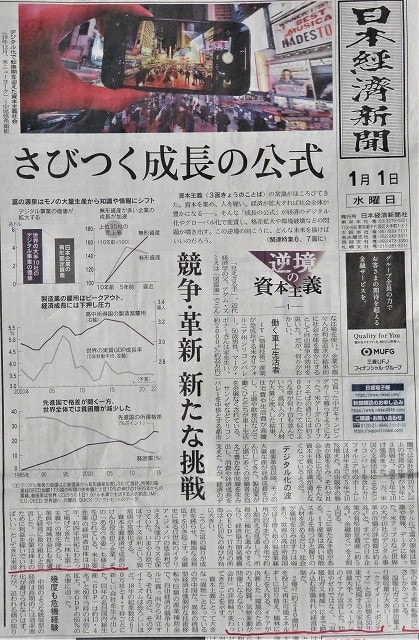元旦の午後、新聞を買いにわざわざ街のコンビニに出かける。コンビニには新聞の殆んどが無くなっていて4か所を探し回る。いつもは新聞の社説を読むのを毎年心掛けてきたが、どういうわけか、出版社の広告のキャッチコピーが気になった。
まずは岩波書店。「現実を見よと言われ、夢想を止めよと笑われながら、それでも想像を止めない。その力がいまをつくりあげた。その力が未来を切り開く。 そんな想像力をはぐくむ本をつくり続けるー わたしたちの新年の決意です。」と結び、『想像力が明日をつくる』というキャッチコピーと宮崎駿の絵コンテで全面広告とした。しかし、表現が従来的で心をキャッチするほどのパワーが足りない。言いたいことはよくわかるが、老舗に安住している環境から一歩も出ていない、と言ったら言い過ぎだろうか。

その点では、文芸春秋社の『活字のなかに<人間>がいる』という言葉でグッと惹きつけられる。スペイン風邪のときの菊池寛の小説の紹介で、中身は岩波書店には及ばないものの、このキャッチコピーには迫力がある。


光文社のこうあったらいいなという写真に、『ニューノーマルな、朝の絶景』という取り合わせは遊び心のなかに思いを貫徹している。また、大修館書店の明鏡国語辞典のキャッチもオーソドックスに特色を伝えている。

新潮社の『私たちは人類史上かつてなく他人と<接続>しているのに、なぜ孤独を感じるのだろう』という、コロナ禍を踏まえた不安感に入り込む。「私たちを取り巻く環境と、人間との進化の結果が合っていないことが、私たちの心に影響を及ぼしているのだ」と、引用したハンセンの『スマホ脳』を紹介している。
そして最後に、「読書そのものは孤独な作業なのに、そこからは大きな充足感を得ることができる」と結ぶところはさすがの新潮社だ。しかも、荒木経惟(ノブヨシ)の写真がまた惹きつけられてしまう。中身が秀逸。保守論壇の覇者ともいうべき新潮・文藝春秋はさすがに鍛えられている。(つづく)