足腰がだいぶ弱くなってきたのでウォーキングを始める。ふだんは車で通り過ぎてしまう所だったが歩いてみるとやはり発見がある。歩いてみると効率や速いだけがすべてではないことを実感する。そこで見たものは、「笠」と「火袋」が特異な変形石灯籠だった。「火袋」の形は花弁のように丸く先端に切込みがある。三日月・満月(太陽)・茶筒・瓢箪などの形を刳り貫いている。この形も珍しい。てっぺんの「宝珠」が大きすぎて全体のバランスを崩しているのがもったいない。

なんといっても、その「笠」にマグマのような彫りこみがあるのが珍しい。石灯籠というと「春日燈籠」のような伝統的な定型パターンが圧倒的に多い。そんな中でこうした前衛的な「笠」は見たことがない。何を表現したかったかはわからないが、まさに伝統の固定的な概念を打ち破る作家のエネルギーマグマが表象されているように思える。それが成功しているかどうかは迷うところだが、創作歌舞伎のようにこうした挑戦に賛意を表したい。

その近くにも、自然石を乗せた石灯籠を発見。「火袋」だけがオーソドックスだが、自然石の「笠」が大き過ぎて圧迫感があるのが残念。地震の時はその笠は崩落してしまう心配が先行してしまう。いかにも、建設業らしい庭の大胆な石灯籠だが、やはり自然との調和が欲しいところだ。ウォーキングした場所はたまたま都会の住宅街だった。創作燈籠の刺激に楽しんだものの、設置した場所がいかにも狭い庭なのが残念。里山を借景にすれば風景から生かされるんだけどと、ないものねだりをした街中散歩だった。






















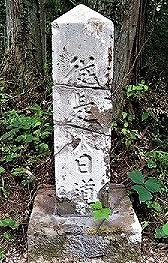


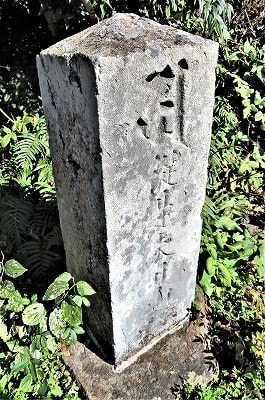



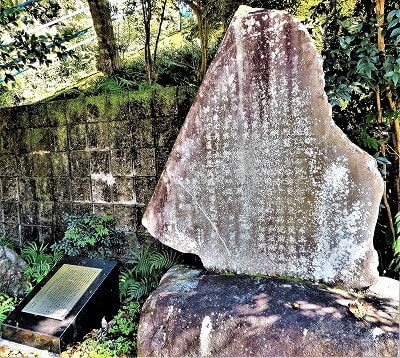

 (画像はwikipediaから)
(画像はwikipediaから)



















