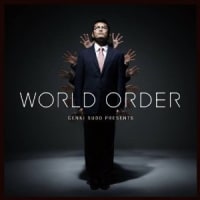日本海軍の「戦艦」というと、世間的に名が挙がるのが、かの「大和」。
沖縄への海上特攻作戦のため、無謀な命令に従い、悲劇的最後を遂げるそのシーンは日本的美意識に訴えかけるのか、戦後60年たっても風化することなく語り継がれている。
しかし、自分にとっての悲劇の戦艦というと「山城」「扶桑」の2隻の名を挙げる。この船の名は大和・武蔵などとは比較にならぬほど世の人々の記憶に残ってないんではないか?
↓以下、61年目の終戦記念日にちなみ、つらつらと書いてみる。
------------------------------------------
1944年10月、フィリピン奪還を目指すマッカーサー将軍指揮のアメリカ陸軍がフィリピンのレイテ島に上陸開始。これを撃破すべく出撃するはずの日本海軍は、満足な戦力を持つのは「大和」・「武蔵」を始めとする戦艦部隊だけで、南方のシンガポール沖のリンガ泊地で訓練中だった。
そこに本土からおっとり刀で駆けつけてきたのが、扶桑型2隻。つまり戦力外なのに急遽登板となった訳だが、それはこの戦艦が当時既に旧式で、防御力に深刻な欠陥があったとも云われ、司令部は実戦に耐えられないと想定していた。
逆にいうと、骨董品でも戦力と名がつくものを使用しなければならないほど、当時の日本海軍は追い詰められていた。
その「第2遊撃部隊」と名づけられた部隊を率いてたのが西村祥治(中将)。一度も陸上勤務なしの水上勤務一本で、中将まで出世した稀有の人物。簡単のようだが陸上勤務のキャリアなしに普通は無理。その司令部が置かれたのが「山城」だった。
もっとも現場の叩き上げである西村司令にとっては、勇ましい名前の割に戦力的には?マークだらけの部隊を指揮しての出撃が果たして望みであったかどうか。
しかも第2遊撃部隊には、大和を主力とする第1遊撃部隊とは別行動でレイテに進撃するよう命令が下された。旧式の2隻では大和等と速力などの面で、行動が共に出来ないと判断されたためらしい。
レイテ島のアメリカ軍を北から「大和」と「武蔵」の部隊が、南は「山城」部隊が突入して挟撃せよ、と云う命令だが、旧式戦艦2隻と護衛艦含めて7隻の小艦隊で、敵の戦力は、強力な空母機動部隊。それに加えて、上陸部隊の直衛艦隊が待ち構えている所に突入する訳だから、生還の可能性は0に近い。
命令が下った時点で、既に西村司令は将来を見越して達観していたように思われる。出撃前夜の艦長会議には、普通同席する筈の司令は顔を見せなかった。
「この後に及んで顔合わせも作戦会議も無いだろう。(こーいう書き方をすると怒られそうだが)後は靖国で合おう。」という感じではなかったか。
前途のとおり、防御力に難有りの実戦訓練不足の小艦隊。しかも空襲を受ければ一たまりもない状況では、彼が「帝国海軍伝統の夜戦あるのみ」と、それこそ死中に活ありと猛進したのはやむを得ない。
しかし悲劇的なことに、既にレイテの南の入口、スリガオ海峡には既にアメリカ海軍が2重3重の防御を引いており、格段に差があるレーダー技術により、完全にアウトレンジ(敵の射程外より攻撃し、味方の損害を防ぐ)される結果となった。
陸地と艦影が区別できない狭いほど狭い海峡で、魚雷艇と駆逐艦の雷撃によって、護衛の駆逐艦が真っ先にやられ、「扶桑」も魚雷2本が命中した。ここで懸念された防御の低さが露呈し、一撃で艦の全機能を喪失して漂流した「扶桑」は、その後真っ二つに裂けて前半分は轟沈。後半分は夜通し溶鉱炉のごとく燃え続けたのち沈んだ。生存者は一人としていなかった。
「扶桑」が無電一つ発信せず沈んだのち、「山城」は戦艦6隻の集中攻撃を受けることになった。後年アメリカのレーダー射撃は自慢するほど正確でなく、2千発発射して命中したのは30発前後だったことが判明しているが、それでも「山城」には十分致命傷となった。護衛の巡洋艦「最上」も大破炎上したあとに味方艦に衝突、沈没した。
艦の沈没後、脱出できた水兵も多くはフィリピンの孤島に漂着後、現地民に虐殺されるという2重の悲劇に見舞われることになった。生還者は最終的に10人前後だったという。
沈没直前、西村司令の最後の無電が「山城」より発信された。
「我、艦橋火災、舵故障。各艦、我を省みず突撃せよ」
それは、後続していると思っていた「扶桑」宛だったか、「大和」宛だったろうか。
この闇夜の目くら撃ちにより弾薬を消耗した直衛艦隊は、翌日レイテ沖に現れた「大和」を始めとする第2艦隊の姿に騒然となった。肝心かなめの空母部隊は、「おとり艦隊」につられて遥か北方に行ったまま。このまま「大和」等が突入していれば、西村艦隊の犠牲は十分報われたはずであった。
ちなみに、この先の歴史は知られているとおり。「大和」はこのとき突入せず引き返し、半年後の沖縄特攻であえない最後を遂げた。このときの「レイテ沖の謎の反転」の理由は、現在でもまったく不明である。
ただ、航空機に虚しく沈められるより戦艦同士の戦いで果てる結果の方が、「大和」にとっても(兵員にとっても)本望であった気がする。一方、反転して引き返したのは艦隊(と人名)の保全を図る意味では、良かったという意見もある。
逆にこの作戦で「大和」等が果てていれば(直衛艦隊はまったくの無力ではなく、小型空母も健在、完勝は有り得ない)、全艦艇を喪失した日本軍が史実より早期に和平に傾いたんじゃないかといわれるが、それこそIF戦記に任せるしかなかろう。
そもそも「捷一号作戦」とは、勝っても負けても日本海軍最後の戦いになるものであり、全艦隊をすり潰してでもフィリピン死守の命令が出ていた。なにしろ、次のチャンスを待つという訳にはいかなかった。フィリピンが占領されたら南方からの石油や資源の輸入ルートが絶たれ、日本は干上がってしまう。この半年後「大和」の沖縄特攻の際、艦隊の燃料が片道分しかなかった逸話は有名だろう。
燃料が切れれば、あとは港に係留されたまま空襲で破壊されるのみ。「座して死を待つより、敵わずともせめて一太刀」と玉砕を選ぶのは、旧軍というより、日本人の悪しき?美意識だろうか。
この作戦とは、「艦隊による神風特攻」そのものであり、西村司令はその作戦命令を誰よりも理解し忠実に実行した。アメリカの軍事評論家をして「評価するに価しない愚将」といわれる西村司令であるが、恐らくほとんどの外国人には理解できない行動であったことが前記の評価に繋がったと思われる。
--------------------------------------------
戦艦「大和」の最後は、日本海軍の最後を象徴するものとして、今でも映画になったり小説になったり、TVや新聞に特集されたりしている。
連合艦隊司令部から沖縄特攻を命令され、無謀な作戦と拒否していた伊藤司令が「一億玉砕の先駆けとして死んでくれ」といわれ、「それでは立派に死んできましょう」と諦めとも悟りとも言える返答をするシーンは、広く知られている。そのシーンを美しいというか、感動するか、馬鹿にするか、気分が悪くなるか、感じ方は人それぞれだと思う。
けれども、「大和」以外にも太平洋戦争の期間中、「山城」と「扶桑」を始め、同じように無謀な命令を受けても、受容として戦闘に従事し散っていった船と兵がいたことを忘れないでいたいと思うのだ。
沖縄への海上特攻作戦のため、無謀な命令に従い、悲劇的最後を遂げるそのシーンは日本的美意識に訴えかけるのか、戦後60年たっても風化することなく語り継がれている。
しかし、自分にとっての悲劇の戦艦というと「山城」「扶桑」の2隻の名を挙げる。この船の名は大和・武蔵などとは比較にならぬほど世の人々の記憶に残ってないんではないか?
↓以下、61年目の終戦記念日にちなみ、つらつらと書いてみる。
------------------------------------------
1944年10月、フィリピン奪還を目指すマッカーサー将軍指揮のアメリカ陸軍がフィリピンのレイテ島に上陸開始。これを撃破すべく出撃するはずの日本海軍は、満足な戦力を持つのは「大和」・「武蔵」を始めとする戦艦部隊だけで、南方のシンガポール沖のリンガ泊地で訓練中だった。
そこに本土からおっとり刀で駆けつけてきたのが、扶桑型2隻。つまり戦力外なのに急遽登板となった訳だが、それはこの戦艦が当時既に旧式で、防御力に深刻な欠陥があったとも云われ、司令部は実戦に耐えられないと想定していた。
逆にいうと、骨董品でも戦力と名がつくものを使用しなければならないほど、当時の日本海軍は追い詰められていた。
その「第2遊撃部隊」と名づけられた部隊を率いてたのが西村祥治(中将)。一度も陸上勤務なしの水上勤務一本で、中将まで出世した稀有の人物。簡単のようだが陸上勤務のキャリアなしに普通は無理。その司令部が置かれたのが「山城」だった。
もっとも現場の叩き上げである西村司令にとっては、勇ましい名前の割に戦力的には?マークだらけの部隊を指揮しての出撃が果たして望みであったかどうか。
しかも第2遊撃部隊には、大和を主力とする第1遊撃部隊とは別行動でレイテに進撃するよう命令が下された。旧式の2隻では大和等と速力などの面で、行動が共に出来ないと判断されたためらしい。
レイテ島のアメリカ軍を北から「大和」と「武蔵」の部隊が、南は「山城」部隊が突入して挟撃せよ、と云う命令だが、旧式戦艦2隻と護衛艦含めて7隻の小艦隊で、敵の戦力は、強力な空母機動部隊。それに加えて、上陸部隊の直衛艦隊が待ち構えている所に突入する訳だから、生還の可能性は0に近い。
命令が下った時点で、既に西村司令は将来を見越して達観していたように思われる。出撃前夜の艦長会議には、普通同席する筈の司令は顔を見せなかった。
「この後に及んで顔合わせも作戦会議も無いだろう。(こーいう書き方をすると怒られそうだが)後は靖国で合おう。」という感じではなかったか。
前途のとおり、防御力に難有りの実戦訓練不足の小艦隊。しかも空襲を受ければ一たまりもない状況では、彼が「帝国海軍伝統の夜戦あるのみ」と、それこそ死中に活ありと猛進したのはやむを得ない。
しかし悲劇的なことに、既にレイテの南の入口、スリガオ海峡には既にアメリカ海軍が2重3重の防御を引いており、格段に差があるレーダー技術により、完全にアウトレンジ(敵の射程外より攻撃し、味方の損害を防ぐ)される結果となった。
陸地と艦影が区別できない狭いほど狭い海峡で、魚雷艇と駆逐艦の雷撃によって、護衛の駆逐艦が真っ先にやられ、「扶桑」も魚雷2本が命中した。ここで懸念された防御の低さが露呈し、一撃で艦の全機能を喪失して漂流した「扶桑」は、その後真っ二つに裂けて前半分は轟沈。後半分は夜通し溶鉱炉のごとく燃え続けたのち沈んだ。生存者は一人としていなかった。
「扶桑」が無電一つ発信せず沈んだのち、「山城」は戦艦6隻の集中攻撃を受けることになった。後年アメリカのレーダー射撃は自慢するほど正確でなく、2千発発射して命中したのは30発前後だったことが判明しているが、それでも「山城」には十分致命傷となった。護衛の巡洋艦「最上」も大破炎上したあとに味方艦に衝突、沈没した。
艦の沈没後、脱出できた水兵も多くはフィリピンの孤島に漂着後、現地民に虐殺されるという2重の悲劇に見舞われることになった。生還者は最終的に10人前後だったという。
沈没直前、西村司令の最後の無電が「山城」より発信された。
「我、艦橋火災、舵故障。各艦、我を省みず突撃せよ」
それは、後続していると思っていた「扶桑」宛だったか、「大和」宛だったろうか。
この闇夜の目くら撃ちにより弾薬を消耗した直衛艦隊は、翌日レイテ沖に現れた「大和」を始めとする第2艦隊の姿に騒然となった。肝心かなめの空母部隊は、「おとり艦隊」につられて遥か北方に行ったまま。このまま「大和」等が突入していれば、西村艦隊の犠牲は十分報われたはずであった。
ちなみに、この先の歴史は知られているとおり。「大和」はこのとき突入せず引き返し、半年後の沖縄特攻であえない最後を遂げた。このときの「レイテ沖の謎の反転」の理由は、現在でもまったく不明である。
ただ、航空機に虚しく沈められるより戦艦同士の戦いで果てる結果の方が、「大和」にとっても(兵員にとっても)本望であった気がする。一方、反転して引き返したのは艦隊(と人名)の保全を図る意味では、良かったという意見もある。
逆にこの作戦で「大和」等が果てていれば(直衛艦隊はまったくの無力ではなく、小型空母も健在、完勝は有り得ない)、全艦艇を喪失した日本軍が史実より早期に和平に傾いたんじゃないかといわれるが、それこそIF戦記に任せるしかなかろう。
そもそも「捷一号作戦」とは、勝っても負けても日本海軍最後の戦いになるものであり、全艦隊をすり潰してでもフィリピン死守の命令が出ていた。なにしろ、次のチャンスを待つという訳にはいかなかった。フィリピンが占領されたら南方からの石油や資源の輸入ルートが絶たれ、日本は干上がってしまう。この半年後「大和」の沖縄特攻の際、艦隊の燃料が片道分しかなかった逸話は有名だろう。
燃料が切れれば、あとは港に係留されたまま空襲で破壊されるのみ。「座して死を待つより、敵わずともせめて一太刀」と玉砕を選ぶのは、旧軍というより、日本人の悪しき?美意識だろうか。
この作戦とは、「艦隊による神風特攻」そのものであり、西村司令はその作戦命令を誰よりも理解し忠実に実行した。アメリカの軍事評論家をして「評価するに価しない愚将」といわれる西村司令であるが、恐らくほとんどの外国人には理解できない行動であったことが前記の評価に繋がったと思われる。
--------------------------------------------
戦艦「大和」の最後は、日本海軍の最後を象徴するものとして、今でも映画になったり小説になったり、TVや新聞に特集されたりしている。
連合艦隊司令部から沖縄特攻を命令され、無謀な作戦と拒否していた伊藤司令が「一億玉砕の先駆けとして死んでくれ」といわれ、「それでは立派に死んできましょう」と諦めとも悟りとも言える返答をするシーンは、広く知られている。そのシーンを美しいというか、感動するか、馬鹿にするか、気分が悪くなるか、感じ方は人それぞれだと思う。
けれども、「大和」以外にも太平洋戦争の期間中、「山城」と「扶桑」を始め、同じように無謀な命令を受けても、受容として戦闘に従事し散っていった船と兵がいたことを忘れないでいたいと思うのだ。