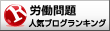わたしたちの涙で雪だるまが溶けた<o:p></o:p>
-子どもたちのチェルノブイリ-<o:p></o:p>
(梓書院:1995年6月初版一刷発行。菊川憲司訳。チェルノブイリ支援運動・九州監修)
抜粋による連載(第20回)<o:p></o:p>
【第三章 これもだめ、あれもだめ 】<o:p></o:p>
空に鳥の震えるような声を聞く<o:p></o:p>
ナタ―リア・コジェミャキナ(女)
第三中等学校十一年生 スベトロゴールスク町<o:p></o:p>
幸いなことに、私の家族や知人の中に事故処理作業に従事した人はいませんでした。私たちの住んでいたところは、役人さんの言葉を借りれば「放射能の許容線量以下」のところでした。だけど、放射能は、許容されるようなものでしょうか。放射能によって私の家族の中に病気が侵入しても、だから病気も許容されるなんていうんでしょうか。
チェルノブイリ原子力発電所で事故が発生した直後、「チェルノブイリ」の言葉が、「大惨事」、「悲劇」、、「災難」、「苦痛」、「涙」の代名詞になることを、いったい誰が予想したことでしょう。
放射能は目には見えず、色もなく、匂いもありません。炎のように夜空に舞いあがり、空の見えない空気の流れに乗って、春の香りにあふれた山河に広がって行きます。しかし、そのことをわかるようになったのは、もっと後のことでした。
事故処理が一段落して、リクビダ-トルたちが、家族や、両親や妻のもとに帰ってきました。作業から戻った夫や息子たちは恐ろしい病気に犯され、まるで老人のようでした。作業に出る前は、若くて、健康で、すばらしい未来を夢見ていた人たちだったのに・・・・・。<o:p></o:p>
乾いた熱風 たとえそれが毒されていても
吸わずにはいられない
病人だって吸う<o:p></o:p>
病院も薬局もあてにはならない<o:p></o:p>
病人を救う知恵などもっていないから<o:p></o:p>
私たちが大惨事を初めて感じたのは、数十、数百という村が鉄条網で囲まれ、広大な土地が「ゾーン」と飛ばれるようになったときでした。ふるさとには「汚染地区」という名前がつきました。人々は恐怖の中で、今までの生活の基盤をすべて捨て、わずかな希望をたよりに、知らないところへと脱出しました。でも、どこに行ったらましになるというのでしょう。
ここスベトロゴルスク地区にもゾーンから移住してきた人はたくさんいます。みんなは、移住の時に指導者が約束してくれたことを信じていました。人間的な水準の生活を期待し、人の親切を期待し、それがふるさとへの郷愁に勝てると信じていました。しかし、その通りにはなりませんでした。じめじめした家、小さ過ぎる納屋、不十分な物質的支援、援助の不足、そしておまけに「お役所仕事」・・・・・・・みんなこんな目にあいました。
ブラ―ギン地区出身のマリア・ミロンチックさんはこう言いました。「クラスノフカ村の人たちはいい人ばかりよ。でも、しょせんうちの田舎の人じゃないのよね。やっぱり自分の家の方がいいわ。たとえ土地は病んでいたとしてもね」と。
このようにして、たくさんの家族が行列をなして、帰って行きました。ゾーンへと、閉鎖された村へと。そして今、何千人もの人が放射能という目に見えない死のベールに包まれて生活しています。そこに住む母親たちは涙ながらに自分の子どもの目を見つめます。まるで、自分や周りの人たちの不幸が自分のせいだと責め、許して下さいと言っているかのように。
私は空高く 鳥がかん高い声で鳴くのを聞いた
チェルノブイリの不幸の日々を予告したのか
だが親たちにはわが子を守るすべがない
<o:p></o:p>
疑問だらけです。どう生きればいいのでしょう。外で遊んではだめ。イチゴを摘んではだめ。幼い子どもにこれをどう言い聞かせたらいいのでしょう。みんなだめだと言えば、子どもらしい生活はできなくなってしまいます。これではまるでカゴに閉じ込められた鳥です。
私たちの地区で、もっとも汚染されている場所の一つが、コロレバ・スロボダ村です。そこの中でも特に汚染のひどいのが小学校の校庭です。放射能を測定する係官の線量計の針が振り切れて使い物になりませんでした。それにもかかわらず、休み時間には子どもが校庭を駆け回り、砂遊びをしています。この学校では今でも授業が行われています。誰も心配しないのでしょうか。この子たちは、将来一体どうなるのでしょうか。そしてその子の子孫はどうなるのでしょうか。
森はいつでも私たちに憩いの場所を与えてくれました。しかし、今は入口に「厳禁」の立て札が立っています。そこでは、人間の生活で当たり前のことが禁止されています。刈り、キノコ狩り、イチゴ集め・・・・、今はみんな危険なこととなってしまいました。土地も、森も、花も、鳥も、獣もみんな地雷と同じです。それは爆発するものもあるし、爆発しないものもあります。放射能がいっぱい詰まっていて、人間の機能を爆破し、死に至らしめることさえできるのです。
プルトニウムは減りつつある
だが おそらく 今後永遠に
畑も庭も それに育てられるのだ
プルトニウムは減っている
木の幹は既に 不機嫌に
スクリューのように 毒を吸いこんでいる<o:p></o:p>
時はたち、政府は人々が置かれている状況をよくするために動き始めています。大人には補償を与えています。しかし、これから生まれてくるものや、生まれたばかりのものたちへの補償のことは誰も言いません。せめて、来るべき問題や心配ごとから子どもたちを守ってやれないのでしょうか。子どもたちの笑顔がますます見られなくなったのはなぜでしょう。どのような補償が問題を解決できるのでしょうか。死者の苦痛、ふるさとのすでに死んでしまった土地、先祖の墓をあとにする苦痛、死者を思う悲しみをどんな方法で計れるというのでしょうか。若者や健康な人も病気に脅かされています。彼らの肉体は、魂と、いのちと、幸福と、愛を求めています。<o:p></o:p>
私は信じたい。政府の指導者、裁判官が、今まで続けていたようなことにも顔を向けてくれることを。ぜいたくな別荘を建てたこともない普通の人々の気持ちを理解してほしい。自分の子どもの命がながらえるように、そして少しでも喜んでもらえるように毎日がんばっている人たちの気持ちを分かってほしい。この現実を信じないとでもいうのですか。ゴメリ州立病院循環器科に行って見てごらんなさい。何にも興味を示さない赤ちゃんの目や、赤ちゃんが助かる希望をなくし、悲しみから髪が真っ白になってしまった若い母親の姿を見ることができます。この光景を見たら、みんあに、そして一人ひとりにこうたずねたくなるでしょう。<o:p></o:p>
「みなさん。この苦しみにもてあそばれているような日々は、いつまで続くのでしょうか。母親の悲しみ、子どもの早すぎる死、民族の滅亡に対して、誰が責任をとるのですか」と。<o:p></o:p>
この質問に対する答えをいつかは聞けることと信じています。<o:p></o:p>