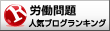「財政危機」は公務員のせいか?
・・・「財政再建」デマ掲げた公務員攻撃打ち破ろう
杉並・田中新区政は「10年ビジョン」「杉並版・新しい公共」「事業仕分け」の三つの政策を掲げ、そのために区長直属の「特設専門チーム」を設けその実施施策を策定・執行しようとしています。田中が都議会議長を辞して「民主党のエース」として杉並区長に菅民主党から抜擢されたこと、菅民主党政権が「新しい公共」「戦後行政の大掃除」「税金のムダ遣いの根絶」「公務員総人件費2割削減」等を政策の柱として公務員攻撃に最大の力を注いでいることは参院選から臨時国会所信表明の過程でご存じの通りです。杉並区長として田中良が「杉並版・新しい公共」というとき、この民主党政権の公務員攻撃の先頭に新区政を位置付けていることは明らかです。
そこで菅民主党がそれを全政策の突破口とし基軸としようとしている公務員攻撃からまず見ていきたいと思います。結論的に言って、菅首相がしばしば強調している「このままではギリシャのようになる」という政財界の危機感は、「財政破たんか財政再建か」という以上に、国家統治の危機の中で燃え上がっていく労働運動を主力とした反政府闘争の永続的発展、その阻止に照準があります。
昨年8・30衆院選以降の政治過程がまざまざと示している統治の危機とは何に核心があるのでしょうか?強固な政府と権力政党を持ち合わせないままに、世界恐慌の拡大の中で二進も三進もいかない経済危機と空前の財政危機に悶々とする日本の支配階級にとっての最大の脅威は、労働者階級の生きんがための反乱がギリシャのように燃え上がっていくという一点にあります。
(ギリシャの場合もそうですが)「財政危機」を公務員制度と公務員労働者のせいにして槍玉に挙げ、「財政再建」を掲げて公務員制度改革と公務員労働者への大量人員削減、全面給与カットの公務員攻撃を強行しようとしていることに対して、このデマゴギッシュな扇動と攻撃の構造を全面的に暴露し批判しつくして打ち破る必要があります。公務員攻撃の核心は労働運動の一掃です。民主党政権が連合指導部を使い、全政党が翼賛的に束になって強行してくる公務員攻撃(国と地方自治体にわたる公務員削減・公務員給与カット、公務員制度改革)に対して反対していく場合にこの視点と認識が重要になります。
今回はまずこの点を中心に見ていきます。
財政危機と財政再建の議論をめぐって
確かに、日本の財政危機は未曾有の深刻なものです。これは言を待ちません。
対GDP比200%になんなんとする政府債務残高は世界最悪。税収をついに国債発行額が大きく上回った。企業であればとっくに破たん・倒産している。
ギリシャ危機の打開、ギリシャ危機の波及・世界化の阻止のための首脳会談で全参加国に財政再建の数値目標や政策目標が「取り決め」されたが、日本だけ例外として国際的目標から外された。それは、日本国債を購入しているのは9割方国内投資家であり投機にさらされるリスクが低いからというようなものではまったくなく、日本の財政危機の深刻さが、解決・再建への数値目標を立てようにも立てようがないほど絶望的に出口がないものだからだ。
日本国債のバブルとその炎上・崩壊についていえば、120兆円規模の投資ファンドを保有・運用し、ギリシャをターゲットにぼろ儲けに売り抜けた何とかいうファンドには、「SPIIGs(※スペイン、ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ)が《炎の環》の中にあるだけではない。アメリカも日本もその《炎の環》の中にある」「次はどこか?日本は狙い目」とあからさまに言われている(テレビ東京「ガイアの夜明け」)。
長期金利(10年国債)もつい先日1%を割ったばかり。為替は1ドル84円台の円高に振れ、いっそうの円高に進む可能性が高い。ギリシャ・欧州危機、アメリカの景気減速のもとで、《消去法》で円と日本国債に市場のマネーの流入が強まっている。この「日本買い」は言うまでもなく「日本(経済・財政)の強さ」の表れではまったくない。株価の下落が示している。格付け機関は日本国債の格下げの方向で検討している。別にここでファンドや格付け会社の肩を持っているわけではない。要は日本の財政危機はすさまじいということ。現実味を帯びている国債バブルとその崩壊から国債暴落の道行きは国家としての日本の文字通りの沈没。日本の「国際的信用」は崩れ去る。日本政府に対する国民の「信頼の最後のひとカケラ」も砕け散る。
むろん、政財界は、だからこそ「このままではあと2年ももたない」とわめき散らして「財政再建」に躍起になっています。だがそもそも問題となっているのは果たして「黒字化」や「再建」が可能なような規模の債務残高なのでしょうか?
既に堤防は決壊し、日本の財政は破たんしている。この財政危機は、1000兆円を超える債務残高をみても明らかなように、消費税の大増税や公務員の人員削減や給与カットなどでとうてい解決されるようなものではない。逆立ちしても「正常化」や「再建」など不可能な天文学的な借金財政(財政出動=国債発行)を国家の基本政策として繰り広げてきたということです。
ぜんぶ資本家のせいだ!公務員のせいにして労働者を犠牲にするな。政府と資本家こそ退陣しろ。
ハッキリさせなければならないことは、この財政破たんの危機は公務員労働者のせいか、ということです。とんでもないデマです。
政府も政党も「公務員の数が多すぎる」「公務員の人件費が高すぎる」というが、国の年間予算の10倍を超え、国のGDPの2倍にも達するような桁外れの債務残高が、たかだかの公務員人件費で積みあがったとでもいうのでしょうか?
「税金のムダ遣い」というが財政赤字にしても債務残高拡大にしても、公務員人件費に税金を回し過ぎたために生じたとでもいうのでしょうか?
冗談じゃありません!財政赤字も債務残高の拡大も、借金(国債発行)の野放図な拡大によって銀行や大企業の救済・支援のために湯水のように公的資金の注入を繰り返した結果もたらされたものではないですか。
実際この10年間、20年間というもの、クビきり・リストラと非正規化で大失業と貧富格差を極限まで拡大して得た利潤を元手に、企業と銀行は金融バブルで巨利を貪ってきた。それが行き詰るたびに国家の名において資本家支援の借金(国債)を乱発・増発してきたのが政府だ。あげく国家として政府として財政破たんに行き着いた。これが財政破たんにかかわるすべてです。
財政危機、財政破たんでをめぐる議論でつきだされるべき問題とは何か。全部、政財界=支配階級のせいだということです。公務員のせいではない!労働者に責任をなすりつけて労働者を犠牲にするな!ほかでもない、このことにほかなりません。
財政破たんは私たちのあずかり知らぬことです。私たちにはこれっぽっちも財政破たんや財政危機の責任はありません。政府が破たんしようが私たち労働者人民がその破たんした政府と資本家の道連れにならねばならぬいわれはありません。
政府と資本家こそ、この社会の支配、経営、運営から退場しろ、ということです。政府の緊縮財政策と公務員攻撃に対して官民2大労組を先頭にゼネストと反政府闘争に立ち上がっているギリシャの労働者が切り開いている闘いこそ、私たちが「財政再建」を掲げた公務員制度改革・公務員攻撃に対して進むべき闘いを示しています。
※次回に続く。数回にわたります。公務員攻撃をめぐる攻防が労働運動の岐路となっているという主題に入っていきます。▲いま公務員攻撃がもっている位置、▲民主党政権の公務員制度改革、▲公務員攻撃の先兵=杉並・田中区政との闘い等々についてお伝えしていきます。