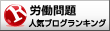四月杉並区議選に児童館全廃阻止で全力で勝利し、安倍の4月子育て支援制度実施を打ち破って大反乱の口火を切ろう
★ 「子育て支援」のウソとだまし打ちの無責任看板はげ落ち、むきだしの民営化・非正規化で、子どもたちを残酷悲惨な犠牲に、女性を超低賃金酷使の非正規労働力に、労働者家族は高齢から若年まで貧困地獄へ!だって!!! ⇒冗談じゃない!
★ もはや黙っていない!「命よりカネ」「富める大企業と大金持ちにカネを回し、大減税。食うこと、生きることも厳しい労働者人民に無慈悲な増税と強搾取」のこの国の1%勢力をたおせ!私たちは職場でも地域でも、ましてや戦場で死ぬ、殺される、使い捨てられるわけにはいかない!
★ 新自由主義的資本主義の時代は終わった!次の社会・世界を担う若者と子どもの未来のことなどどうなってもかまわないという政府・政治家、目先の、そして永遠の「カネがすべて」の資本家にもう社会をいいようにさせない!社会は99%の私たちのものだ。私たちに権力をよこせ!連中に奪われたすべてを取り戻し、労働者中心、人間主体の社会につくりかえよう!
安倍はじめこの国の政府財界は、子どものために動かすカネはないという考え
(1) この4年と6カ月の間、民主党政権(菅政権・野田政権)、自民党(自公)政権(安倍政権)は子育て支援、子育てと就労の両立を看板に掲げ続けてきた。鳴り物入りで「子ども子育て新システム」を民主党政権が打ち出し、「税・社会保障一体改革」自公民合意で2015年新制度実施を国会に通し、安倍自民党政権下で「子育て支援・待機児童解消加速」を看板に、2015年を待たず前倒し、「保育所待機解消に保育受け皿40万人増」「学童保育待機解消に学童保育定員枠30万人増、放課後子ども教室2万箇所への倍増」の数値目標を掲げてきた。それでどうなったか?何か「進捗」はあったのか?
(2) いかなる「進捗」もない。宣言した政府「数値目標」に対する現在的「達成」数値の報告もない。二桁の万単位の目標を繰り返し言っていれば、ごまかせるとでも思っているのか!安倍は、「税・社会保障改革一体改革」法に基づく10%消費税の実施の1年半の延期によって、「税・社会保障改革一体改革」自公民合意・法制化に明記した「子育て支援」への10%増税分からの7000億円の投入も1年半先延ばしにした。
(3) 仮に消費税率10%となっても、「子育て支援」で国が想定している必要額に4000億円不足を生じるということは、民主党政権時代から今の自民党政権にいたるまで一貫して政府国会答弁で明らかにされていることだ。安倍・自公もこのことは百も承知している。そもそも10%消費税で捻出できる「子育て支援」国費は7000億円で必要な規模に逆立ちしても4000億円たらないということが国会で最初に明らかになったのは民主党・安住財務大臣の公明党・松あきら質問への答弁だ。以来、10%税率への消費増税で「子育て支援」に充てられるのは7000億円という枠が継承され不変のものとされている。この国は「子育て支援」にはそれ以上のカネを追加的に注がないということだけが確認され、そのうえで、デタラメな「数値目標」だけが並べられ、実際には「子育て支援・待機児童解消」にはいかなる政策努力も政府責任もとらなかったということだ。4年6カ月!である。
(4) 安倍首相は、2014年12月衆院選後の第三次安倍政権発足に際して「10%への消費税率引き上げは延期したが、子育て支援は我が国の将来にとって喫緊の重大問題であり、全力で政権として取り組む」とまたぞろアナウンスしている。しかも「子育て支援で新たな国債は発行せず、医療費の削減、介護報酬の引き下げ、生活保護費の効率化で賄う」としている。それも7000億円が基準額で、足らずの4000億円とされている不足は頬かむりしている。同様の議論はこの数年間何回も繰り返されてきた。これは、何もやらないか、社会保障費の全体としての底下げ(削減)ということだ。
(5) これは政府財界の根本的な考え方と勝手で一方的な都合によるものだ。ふざけるな。1200兆円になんなんとする世界最大の借金国(ギリシャどころではないGPD比243%の債務比率)といえどもカネはあるところには屋上屋を超す340兆円もの大企業の内部留保として隠され、労働者人民の食っていけない貧困地獄をよそにどんどん膨れ上がっている。オリンピックに関連予算も含めれば兆のケタのカネをつぎ込むこの国は、国自身が算定する1兆1000億円の「子育て支援」費に、「いまは増税実施までとても7000億円も準備できない。やるとしたら他の社会保障費を削減しそれを回すしかない。足らずの4000億円については10%実施後の消費税再増税によるしかない」と言っているのだ。
(6) 保育所待機にしても学童保育待機にしても、財界と政府の10割非正規化の雇用政策、超低賃金不安定非正規雇用への労働力動員政策、女性労働力の超廉価な動員政策のもとで、不可避につくりだされているものだ。貧困地獄のもとで働くしかない、しかし、子どもを預けるところがない、この非正規共働き労働者世帯の苦しみと叫びを何だと思っているのか。労働者の労働でまわっているのがこの社会だ。労働者人民の血税によって養われているのがこの国であり、政府だ。こんな国とそれを牛耳る財界・企業・政府・政治家はうちたおし、私たちがとってかわって、労働者人民、子どもたちが人間らしく生きられ、人間として育っていける社会につくりかえるしかない。
(7) 「子ども・子育て支援」「待機児童解消」の看板は完全にはげ落ち、大ウソとだまし打ちは完全にあからさまになった。ここでは細々としたああだこうだは枚挙にいとまがないが、結論的に確認しておこう。
① もともとの「子ども・子育て支援」関連法の目玉であった幼保連携認定こども園はどうなっているか?
2015年度実施までに2年間で2000達成の目標値は6割前後。しかも、いったん認定こども園への移行を決めた園が1割超辞退している。こんな制度には経営上も運営上もいかなる希望も持てない、やっていけないというのが、これまで幼稚園や保育園を経営・運営してきた施設当事者の端的な意見・所感だということだ。移行した園には手厚い補助を継続するという幼保連携認定こども園と政府新制度への移行への利益誘導、移行しない園には補助金交付打ち切りという脅しで進められてきたが、実施を前に、また実施後も辞退、拒否は相次ぎ激増する。根本に、園経営者・運営者の危惧とともに、何よりも園で働く職員、園に子どもを預ける親たちの怒りと危機感がある。実施・強行しても、ボロボロに形がい化し、頓挫する。新制度とはそういう代物だということだ。
② 新制度に向かう以前に、保育の規制緩和と民営化の動いの中で顕著になっていたが、新制度実施を前に保育事故はけた違いに激増している。

厚生労働省の発表は、アンケート調査への回答があったものだけであり、総数・全体像はもっと件数は多いと考えられるが、2013年に認可保育所等の保育施設で起きた重大事故は年間162件にも上り、2010年の3倍以上となっている。そのうち死亡事故は19件であり、年々増加している。放課後小学生を預かる学童保育でも、毎年200件を超える事故の発生が続いている。幼児が昼寝中に心肺停止になった、おやつの白玉団子を喉に詰まらせた、川での水遊び中に流された、・・・・こういった事故が増えている。保育所や幼稚園、学童クラブでの事故の頻発は、職員のせいや職員への教育不足のせいではない。定員を超える園児数や職員数の規制緩和、パート・アルバイトのシフト・ローテーション制で低賃金非正規で職員を確保すること、就労している職員もダブルジョブ・トリプルジョブで疲労困憊の中で「かたときも目を離せない子どもたち」に目が届かない現実が、過酷劣悪な労働条件のもとで起きているからである。あいつぐ命の事故、重大事故、園の安全崩壊は、規制緩和、民営化、非正規化からひき起こされている。

写真:日比谷野外音楽堂埋め尽くした「子ども子育て支援新システムNOの大集会
政府の方針は、公立認可保育所の拡充・増設ではない。政府の方針は、公立保育所の廃止・民営化であり、株式会社立の大型認可保育園の促進、大型の幼保連携認定こども園の拡大、保育ルーム・保育ママを中心とした認可外小規模保育(施設保育ならざる密室保育)の促進による待機児童解消の受け皿づくりであり、保育者の資格要件の全面的規制緩和(ごく短期間の研修受講)である。放課後学童保育については、児童館を廃止し、学童クラブと放課後子ども事業を一括して、小学校の放課後子ども教室に統合し、民間委託のもとで子どもを放課後空き教室にとじこめるというものだ。幼稚園も保育園もこども園も、学童保育も、新制度のもとで、子どもたちにとって、より危険な場所となる。
安倍は、2013年4月の成長戦略スピーチのトップで、「子育て支援・待機児童解消加速」を掲げ、要は「やるかやらないかだ」「ありとあらゆる政策手段を動員して女性の就労支援と待機児童解消を果たす」として「空きビルの活用はじめ何でもやる」と言い、2014年の「小1の壁の突破、30代~40代の女性の就労支援が成長戦略の成功のカギ」の力説で「学童保育30万人増、放課後子ども教室倍増」方針を打ち出した際も「空き教室の利用」と言っている。安倍の眼中には子どもたちの姿はない。あるのは「子どもを放り込む入れもの(場所)さえあればいい、入れものつくらせるから、四の五
の言わずに女性は働きに出ろ」ということだけである。しかも、株式会社の民営保育にせよ、無認可民間保育にせよ、非正規世帯の収入では保育料に手が届かない。これほど無責任な「子育て支援」があるか。子どもは人間だ。わが子を危険がある場所に預けようとか、子どもを教室に閉じ込めておけば安心だ」などという親がどこにいるか。子どもはモノじゃない。もっとも保育、学童保育を必要としている、そして働かなくては生きていけない非正規共働き世帯が、その保育を切り捨てられ、あるいは犠牲になれと、奪われている。
③ それでは、この「子育て支援」で「子育てと就労の両立」は進んでいるか?
まったく目に見える「進捗」はない。起きている現実は、この新制度が準備する「名ばかり保育」では安心してわが子をそこに預けることはできないからであり、また準備された「名ばかり保育」もみな有料高額で、非正規世帯やひとり親世帯には経済的理由から手が届かないからだ。確かにM字型カーブといわれる、これまで就労率が低かった女性の30代・40代の就労人口は微増した。しかしきわめて不安定な非正規不規則就労が増えたに過ぎない。
この中で鋭く突き出されている重大問題とは、
第一に、爪に灯をともすような乏しい生計の中で貧しくとも入れられる公立認可保育所への入所を絶望的に希望して待機耐乏生活でしのいでいる世帯が増えていることであり、
第二に、同じ生活困窮状況下で、どんな劣悪でもとにもかくにも食うためには一時預かりであれ密室保育であれ、子どもをそこに預けて就労せざるを得ない世帯も増えていることであり、そうした世帯では、親子が同じ食卓につくことはなく、親子が一緒にいるのは預けるまでと家に帰るまでと寝る時間だけという対話も遊びもない深刻な状態が起きている。
第三に、今や2千万人を超え、ますます増えるばかりの、そして財界・企業も国も労働力を全部非正規にするまで増やす方針である非正規労働者は保育がもっとも切実に必要としている膨大な層であるにもかかわらず、口先は別として保育をきりすてられているということであり、
第四に、この現状の中で、若い世代は結婚も子どもをつくることもあきらめざるを得ない非人間的な現実が社会的にひろがっていることだ。
人間社会は、自分と他人とその生活を生産・再生産することによって、人類として社会たりえている。それが自分自身が食うこともままならず、子どもを作ることも育てることも絶望的な閉塞状態に「命よりカネが全て」の新自由主義的資本主義によって直面させられている。利潤を産む(カネ儲け)がすべての資本とその人格的表現である資本家階級にとっては、わが世の際限なき富の独占がすべてでそれを維持し護持するためには99%の人々の生き死にや貧困地獄などどうでもいいことで、挙句の果ての戦争に突き進んでも次世代や人類の未来のことなどどうでもいいのだろうが、私たちはそうはならない。私たちには贅沢や強欲は縁がないが、生きる必要があり権利があるのだ。人間史、人類史がここで資本家たちのせいで幕を閉じることなど起こしてはならないし、絶対にそうはならないし、そうはさせない。新自由主義的資本主義こそ、こうして貧困地獄と戦争と未来の担い手である子どもたちを犠牲にする子殺しによって、私たちに重大な歴史選択、それも人類の歴史が続けられるかどうかという意味で、新しい人類史の扉を開けろと促迫している。人間社会は、社会をまわし動かしている労働者階級を中心にして、もはやつくりかえるしかない。
「もっと低賃金の労働力が必要だ、女性労働力を非正規で極限的に動員することによってしか利潤はあがらない」―これが「子育て支援・待機児童解消」の正体。子ども・保育をダシに使って、企業のカネ儲けのために強搾取と福祉撲滅・民営化、さらに子ども支配の国家主義教育めざす!
(1) 民主党が政権担当時に打ち出した「子ども子育て新システム」要綱は、「成長戦略と連携し」「新たな雇用とマーケットの創出」という二つのサブタイトルで出されたものだ。御手洗経団連が準備した産業構造審議会答申がベースだ。
以来、菅、野田(以上民主党政権)、安倍第一次~第三次政権が目玉政策としてきた「子育て支援」は、安倍第一次政権時の安倍首相「成長戦略スピーチ」はじめ「学童30万人増・放課後子ども教室2万確保・倍増」宣言まですべて「成長戦略」とリンクして打ち出されてきた。
(2) 政府財界にとって、「子どもの安心・安全」「子育て支援」「待機児童解消」など口先・名ばかりであって、基軸、核心は、大恐慌・大不況下で没落から再生するための企業の利潤向上のためには、労働条件の切り下げ、労働力のほとんど10割を非正規雇用にすることが戦略とされ、そのカギは廉価労働力としての女性を超低賃金非正規雇用に動員することであり(「子ども子育て支援新システム」がいう「雇用の創出」とはこのことだ!)、労働者派遣法の派遣26業種を規制撤廃し、男女を問わず生涯非正規で使いまわし使い捨て自由にすることであり、労働組合を解体・一掃することであった。
(3) 公務員労働者・自治体労働者の団結、保育労働者・児童館労働者の団結によって守られてきた保育・学童保育(社会保障・福祉の最後の砦)を解体・廃止し、労働組合もろとも児童福祉を廃止し、株式会社を全面的に参入させカネ儲けビジネスとして展開させる(「子ども子育て支援新システム」がいう「マーケット(市場)の創出」とはこのことだ!)、つまり、保育のまるごと民営化であった。
(4) しかも、新制度の実施開始を前ににわかに前面化した児童館廃止・学童保育解体、小学校での放課後子ども教室への統合で明らかになったことは、これまで児童福祉法による福祉実施として行われてきた学童保育をなくし、学校基本法による小学校・放課後子ども教室へ統合することで、児童福祉そのものを撲滅・解体・廃止することだった。(杉並区の田中区政が施設再編整備計画による区立施設の廃止、売却・転用、民営化の最大の実体となっている42児童館の全廃と小学校への学童機能の移転はその先端である。)ここでハッキリ確認すべきことは、「子育て支援関連法」の核心の一つである幼保連携認定こども園は、幼保一体型、幼稚園型、保育所型の3形態としているが、これは、0~2歳児保育の保育所型への特化以外は、児童福祉法ではなく学校教育法に基づくものとして再編させるものだということだ。核心は、小学校就学前の3~5歳児については、学童保育を小学校子ども教室への統合によって廃止し、福祉ではなく教育に変えるのと同様に、3~5歳児を児童福祉の対象ではなく、学校教育の中にくみこむということなのである。
(5) ここに0~2歳児保育の株式会社への開放・民営化、3~5歳保育の幼保一体型・公私連携型幼保連携認定こども園と学童保育の小学校への統合と民間委託・民営化という新制度法実施の行き着く先、この国の政財界が狙う正体が確定する。待機児童をどう解消するのか、財源があるのか等々、ああだ、こうだの議論の大紛糾がありながら、安倍政権が一向に何の手も打たないのは、この隠された正体があるからだ。幼保一体型・公私連携型幼保連携認定こども園は、民設民営化であり、国費補助は必要なく、放課後子ども教室も小学校の活用で民間委託だから国費補助は必要ないからである。経営や運営は民間企業が行い、施設にはまさに子どもを放り込むだけでよいからである。保育園や幼稚園の創始者と言われるフレーベルやロバート・オウエンは子どもの自然との触れあい、自由遊びの重要性、その中での子どもの成長を重視した。

写真:児童館行事
子どもたちは、入れものに放り込む、学校にとじこめ、そのいれものさえあればいい、という「子育て新制度」はその対極・反対物であり、子どもたちから自由を奪い、遊びを奪い、学校教育の監視・おしつけのもとに子どもたちを閉じ込めるものだ。子どもたちの健やかでのびのびとした成長は圧殺の対象であり、そこは子どもたちが自分たちの居場所と実感できる居場所ではない。そこは子どもたちの自由を抑圧し、監視する、暗欝たる行きたくない場所となる。安倍ら政財界は、むしろ、そうした教育環境こそ、やれ自由だ、やれ遊びだという子どもたちを強制に殉じさせる秩序であり、幼い時からこの国を守る気概を植え付けるのに格好の環境だと国家主義的にこのプランの制度実施に血道をあげている。
(6) 麻生太郎の「子を産まない女が悪い」という大暴言は、この国家主義的な「子ども支配」「子ども教育」と表裏一体の本音である。子どもをつくらない、子どもをつくれないという世帯、これでは結婚もできない、結婚しても夫婦非正規共働きで生計費やっとの現実では子どもをつくれないと結婚をあきらめている青年が圧倒的に増えているのは、新自由主義の国策で政財界がつくりだしている現実だ。その張本人の政界の大ボスが恫喝まがいの言辞で「産めよ増やせよ」と言っているのだ。「お国のために、子どもをつくれ」というのと、「お国のために、子どもを産んで、子どもは国の新制度に委ね、就労して、お国のために働け」というのはイコールだ。
(7) すべてのウソ看板がはぎ落された中で、始まっているのはむきだしの激突だ。公的保育廃止・民営化、児童館全廃・学童保育廃止・民営化との闘いは、非正規労働者世帯の死活を賭けた闘いであり、子どもたちの自由と命と未来の懸った闘いであり、保育労働者、自治体労働者のおのれの職場と仕事、自分の首が懸った闘い、使命と誇りを賭けた闘いであり、地域・住民にとっても保育園・児童館という地域コミュニティ拠点の存亡を賭けた闘いである。2015年新制度実施に断固たる抗議と絶対反対、安倍政権たおせの闘いに立とう。

安倍の4月子育て支援新制度実施に対し、杉並から児童館全廃ぜったい阻止、安倍たおせ、田中区政たおせの大闘争で大反乱の口火を切ろう!

写真:荻窪駅南口のあんさんぶる荻窪
ここでは詳述しないが、正規250名・非正規250名の職員が職員の団結と住民との連帯で守り抜いてきた児童館42館の全廃が、田中区政の「区立施設再編整備計画」(例外なき廃止、売却・転用、多機能化・複合化、民営化)の最大の攻撃として開始されている。しかも、それは麻生財務大臣と田中区長のあんさんぶる荻窪と荻窪税務署の資産交換の「最終合意」による強行計画のもとで、あんさんぶる荻窪内にある杉並区内最大の児童館、荻窪北児童館の廃止、2年後に改築工事を急きょ決定した桃井第二小学校の工事中にその同じ現場の仮設校舎内への学童クラブの移転を最大の突破口にしようとしている。

写真:あんさんぶる荻窪の二階にある荻窪北児童館
2013年の荻窪北児童館総利用者数は年間5万7675名、学童クラブ利用児童数は年間1万4785名だ。区議会は麻生・田中談合による「最終合意」の発表があった全員協議会でこれに異議や抗議を申し立てる議員がひとりもいないオール与党で荻窪北児童館廃止にもあんさんぶる廃止にも全面的に協力している。杉並区職労児童館学童保育分会は児童館全廃に対する反対を決議して闘っており、区立施設再編整備計画の攻防の帰趨と荻窪駅南北再開発がらみの田中区政の住民無視・子どもの居場所(児童館)廃止のあんさんぶる荻窪廃止・荻窪北児童館廃止に区民の鋭い反撃が区議会の翼賛に屈せず、開始されている。2016年3月第1回区議会定例会に区はあんさんぶる荻窪と荻窪税務署の交換に係る条例案を提出するとしている。

2015年は、あんさんぶる荻窪の存続か廃止か、荻窪北児童館廃止・桃井第二小学校への学童機能移転か、その阻止かを賭けた攻防となることは必至である。その来春4月には統一地方選(杉並区議選)が実施される。4月杉並区議選をあんさんぶる荻窪・荻窪税務署交換ぜったい反対、児童館全廃阻止、施設再編整備計画ぜったい反対の闘い、安倍たおせ、杉並の安倍=田中区政たおせの闘いで大爆発させ、児童館全廃反対の議員を圧倒的支持で翼賛議会打ち破る絶対反対派として送りこみ、空前の大運動をまきおこそう。2015年、大反乱・大運動へ!
(※杉並区の児童館全廃・施設再編整備計画との闘い、あんさんぶる荻窪廃止との闘いについては、当通信のカテゴリーで各記事をごらんください。)・