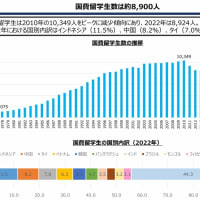(昨日の続きです)
さて、民主集中制の元祖であるレーニンとソ連共産党ですが、ロシア革命の最初からそのような組織原則を持っていた訳ではありません。ソ連共産党の前身のボリシェビキ自体が、元々はロシア社会民主労働党の分派として生まれたのです。ボリシェビキは日本語で「多数派」という意味です。「少数派」を意味するメンシェビキに対立する分派だったのです。十月革命が成功した後もボリシェビキの組織内では分派は盛んに生まれて活動していました。
アイザック・ドイッチャーによれば―(ボリシェビキ内部では)つねに新しい反対派が立ち上がって、党をその革命的な民主主義的伝統と社会主義的誓約につれもどそうとした。・・・1921年と1922年に労働者反対派と民主主義的中央集権派が・・・1923年以後にトロツキストが・・・1925年から1927年にジノヴィエフ主義者が、1928年と1929年にブハーリニストが、その後…スターリニストのグループまでがやったことである―(注)。こうした様々な分派活動は、しかし最終的には1930年代半ばのスターリンの独裁の完成によって消滅してしまいます。ボリシェビキ以外の政党の活動制限、分派禁止と民主集中制の徹底化は、ロシア革命が国内での反革命派の武装蜂起や、アメリカ、イギリス、フランス、そして日本など各国による武力干渉に対抗するために執られた非常措置のはずでした。ところが、そうした危機的要因が全て消え去った後に民主集中制は永続化し、何と1990年まで続くことになったのでした。
こうした歴史的背景を考えますと、21世紀の今日において日本共産党が民主集中制を維持しなければならない必然性は全くないと言えるのではないでしょうか。
(注)アイザック・ドイッチャー『ロシア革命五十年-未完の革命』(岩波新書 pp.51-52)