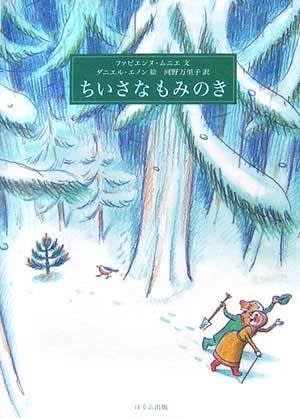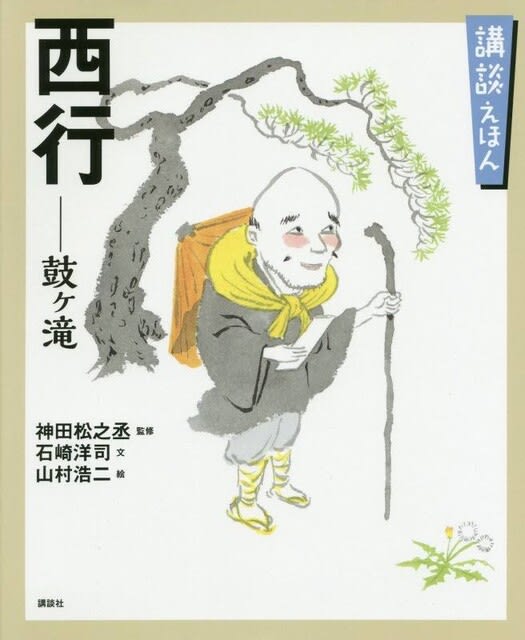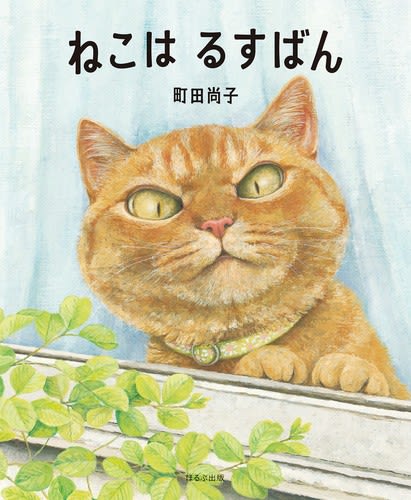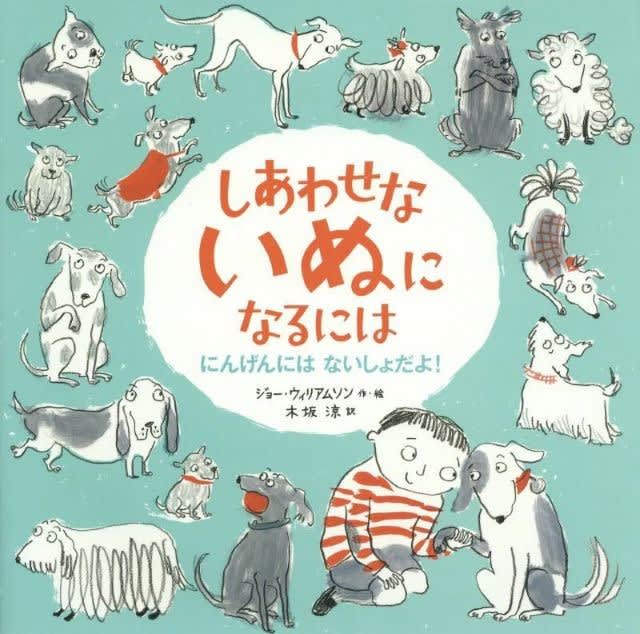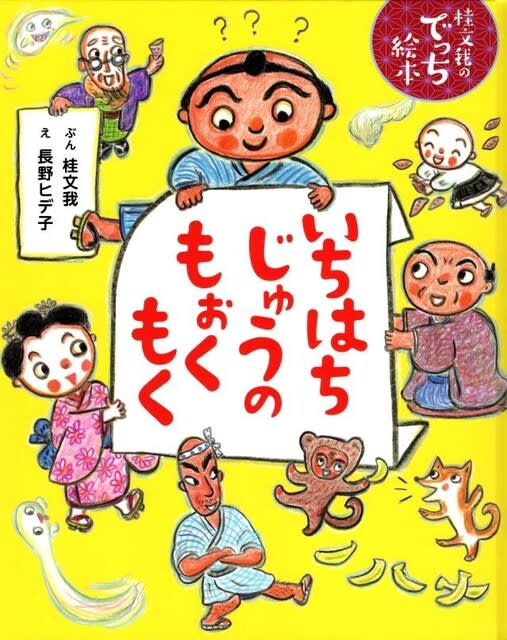去年のうし年は内田麟太郎の『うし』、一昨年はねずみ年だったので『リンドバーグ 小さなねずみの大冒険』を、干支にちなんで読み聞かせる機会があった。今年のとらは、あまりないだろうと真面目に探しもしなかったが、偶然、孫用に借りていた絵本を見つけ、読んでみたらなかなかいいムードのある一冊だった。
『おちゃのじかんに きた とら』
(ジュディス・カー作 晴海耕平・訳 童話館)

ソフィーというちいさな女の子とお母さんが、台所でお茶の時間を楽しもうとした時に玄関のベルがなり、ドアをあけてみるとそこにいたのは、毛むくじゃらでしまもようのとら。お腹が空いているので一緒にお茶させてくれと言う。お母さんは快く招き入れ、サンドイッチをすすめると、とらは一口で呑み込んで…
その後、家中のありとあらゆる食べ物、飲み物をたいらげて帰ってしまう。ちょうどそこへ帰ってきたお父さんはその話を聞き…という展開である。もちろん、とらは恐怖の対象にはなっておらず、次から次へと食べるに従って、ソフィーと親密さを深めていくような絵が描かれている。ファミリーファンタジーかな。
外国に干支は関係ないが、とら(tiger)は何かを象徴しているのだろうか。この異色の訪問者は、家族の歓待?をうけて、結果的には家族に幸せをもたらす存在になった。家族が再訪を望む行動を見せるが、結局二度とは現れないというエンディングだ。こんな終わり方をする外国童話など、結構多い気がしている。
拡大解釈してみれば、様々な環境にある者を素直に受け入れ、温かく見守りなさい。その行為は福音をもたらすでしょう…といった宗教的なイメージにつながる。また、アクシデントを乗り越えるハッピーさという見方もできる。「とらが、いつまたおちゃのじかんにきてもいいように」…せめて、心の準備はしたい。
『おちゃのじかんに きた とら』
(ジュディス・カー作 晴海耕平・訳 童話館)

ソフィーというちいさな女の子とお母さんが、台所でお茶の時間を楽しもうとした時に玄関のベルがなり、ドアをあけてみるとそこにいたのは、毛むくじゃらでしまもようのとら。お腹が空いているので一緒にお茶させてくれと言う。お母さんは快く招き入れ、サンドイッチをすすめると、とらは一口で呑み込んで…
その後、家中のありとあらゆる食べ物、飲み物をたいらげて帰ってしまう。ちょうどそこへ帰ってきたお父さんはその話を聞き…という展開である。もちろん、とらは恐怖の対象にはなっておらず、次から次へと食べるに従って、ソフィーと親密さを深めていくような絵が描かれている。ファミリーファンタジーかな。
外国に干支は関係ないが、とら(tiger)は何かを象徴しているのだろうか。この異色の訪問者は、家族の歓待?をうけて、結果的には家族に幸せをもたらす存在になった。家族が再訪を望む行動を見せるが、結局二度とは現れないというエンディングだ。こんな終わり方をする外国童話など、結構多い気がしている。
拡大解釈してみれば、様々な環境にある者を素直に受け入れ、温かく見守りなさい。その行為は福音をもたらすでしょう…といった宗教的なイメージにつながる。また、アクシデントを乗り越えるハッピーさという見方もできる。「とらが、いつまたおちゃのじかんにきてもいいように」…せめて、心の準備はしたい。