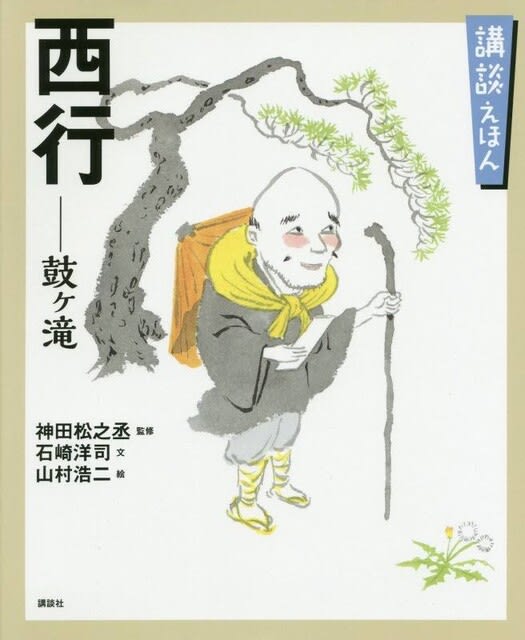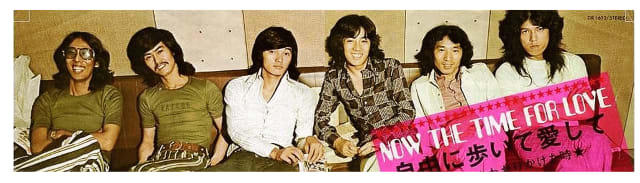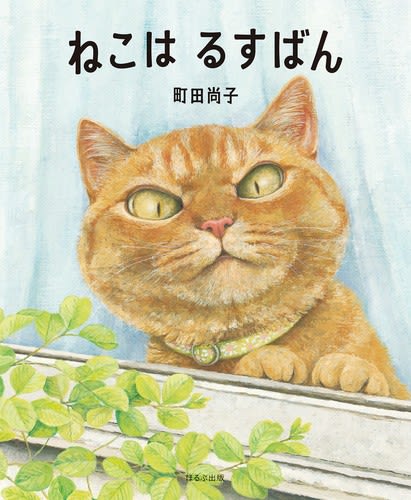最近読んだ対談集の中では実に刺激的な一冊。この本の中で取り上げられている『言葉なんか覚えるんじゃなかった』という書籍も注文をかけた。言葉について少なからず考え続け、仕事や生活を送ってきたつもりだ。その一環としてのこの拙文ブログもあったのだが、根本で何か間違っていたような気にさせられた。

『「言葉」が暴走する時代の処世術』
(太田光・山極寿一 集英社新書)
序章で山極は「ディストピア的な未来」を、このような認識で語った。「そもそものきっかけは『言葉』にあると考えざるを得ない。人は言葉を持ってしまい、その効用の時空を超える広がりという側面を伸ばそうとしたために、ついに他者とのつながりをバーチャルに拡大するようになってしまった。」…しまったのか。
言葉を持ったからこそ、人間は文明を発達させ、地球を牛耳るようになったことは誰にも否定できない。しかし、それゆえに生じてきた様々な問題もまた、言葉があるため、頼りすぎたために膨張している。「伝える」目的で発明、編み出された言葉が単なる記号化した虫のようになり、社会を浸食しているイメージか。
では、そんな時代の「処世術」をどう語っているか。二人ともスマホを持っていない。それが典型的だろう。一つには不要な情報遮断があるだろうが、それ以上にコミュニケーションの身体性重視を貫いていることだ。太田は高校時代、誰とも口を利かなかったという。内実は自己対話であり、その経験から導きだせる。
「伝えようとするより、わかろうとする」意識を持てば、相手や対象に向ける目、傾ける耳が違ってくる。そして言葉が伝達の役目を持つのは、ほんの「一部」に過ぎない。そのことを思い起こし、画面上のテキストに縛られる瑣末さを笑い飛ばす感覚を身につけよう。まずは「顔を見ながら話すこと」。そこからだ。

『「言葉」が暴走する時代の処世術』
(太田光・山極寿一 集英社新書)
序章で山極は「ディストピア的な未来」を、このような認識で語った。「そもそものきっかけは『言葉』にあると考えざるを得ない。人は言葉を持ってしまい、その効用の時空を超える広がりという側面を伸ばそうとしたために、ついに他者とのつながりをバーチャルに拡大するようになってしまった。」…しまったのか。
言葉を持ったからこそ、人間は文明を発達させ、地球を牛耳るようになったことは誰にも否定できない。しかし、それゆえに生じてきた様々な問題もまた、言葉があるため、頼りすぎたために膨張している。「伝える」目的で発明、編み出された言葉が単なる記号化した虫のようになり、社会を浸食しているイメージか。
では、そんな時代の「処世術」をどう語っているか。二人ともスマホを持っていない。それが典型的だろう。一つには不要な情報遮断があるだろうが、それ以上にコミュニケーションの身体性重視を貫いていることだ。太田は高校時代、誰とも口を利かなかったという。内実は自己対話であり、その経験から導きだせる。
「伝えようとするより、わかろうとする」意識を持てば、相手や対象に向ける目、傾ける耳が違ってくる。そして言葉が伝達の役目を持つのは、ほんの「一部」に過ぎない。そのことを思い起こし、画面上のテキストに縛られる瑣末さを笑い飛ばす感覚を身につけよう。まずは「顔を見ながら話すこと」。そこからだ。