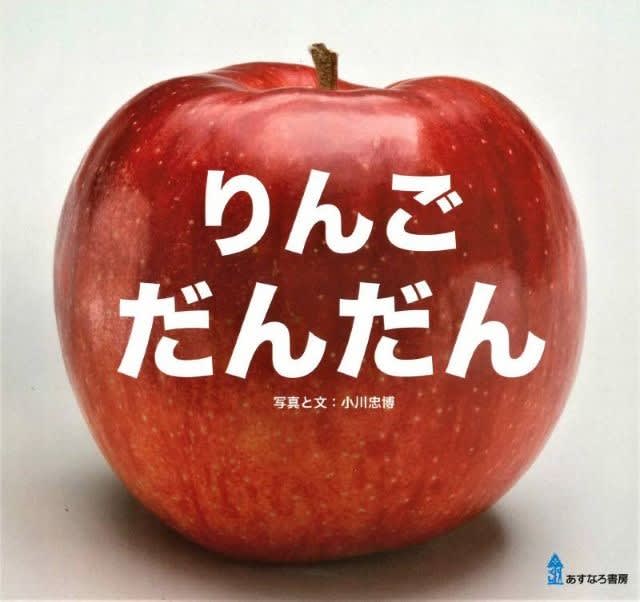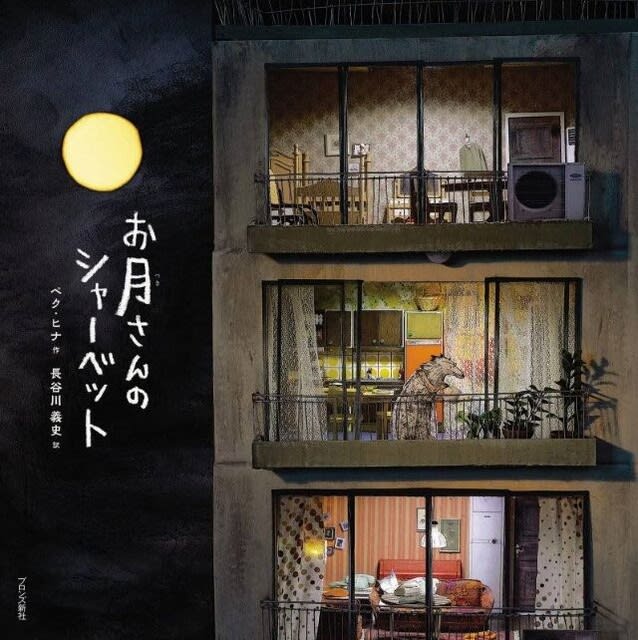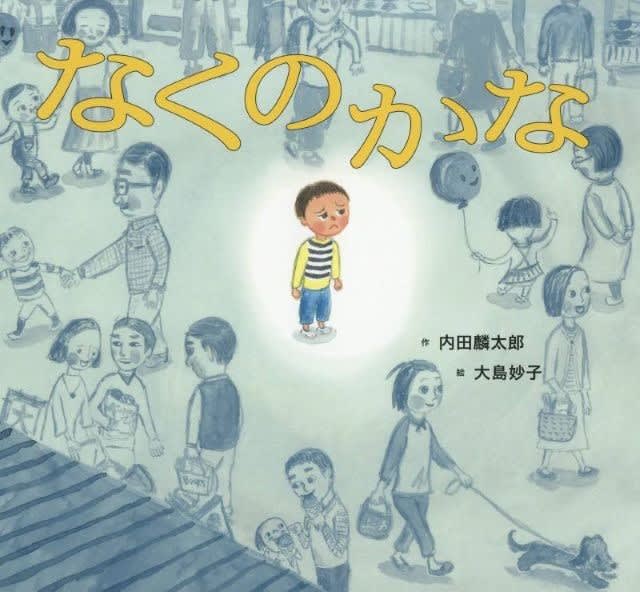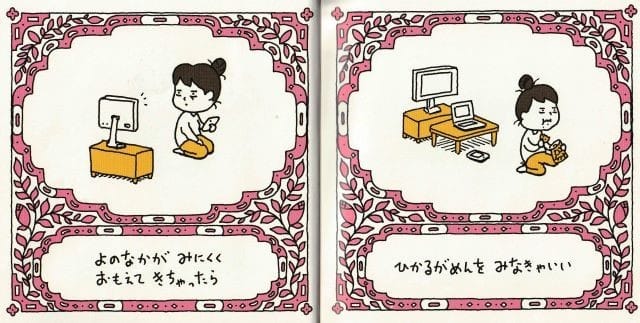次週は2年生が相手なので、ふさわしい絵本はないだろうかと新着棚で見つけた一冊。「くらやみきんしの国」、まずこの題が何だろうと思わせる。黄色と黒を基調とした表紙。王様が城壁からライトを照らして、そこに浮かびあがる題名。題字のデザインもなかなかよい。改めて絵本全体のイメージの大切さを知る。
『くらやみきんしの国』
(エミリー・H・ブース作 おおつかのりこ訳)
あかね書房 2020.11

「くらやみ」が怖い男の子は「王子さま」だった。王様になったら、くらやみをなんとかすると決め、成長して実行する。ところが…という展開で、表紙カバー裏には、次のような文章が添えられていた。「わたしたちに たいせつなことを 教えてくれる おはなしです」。読み終えてみると、確かにその印象が残る。
表紙と同様に、お話の絵も黒と黄色が中心になって構成されている。画材が何かはわからないが、柔らかい線、シンプルかつコミカルな表現が、想像上の国であることにマッチしている。結局、もとに戻る流れは予想されるが、そのクライマックスが「花火」になる箇所が素晴らしい。読み手はここで心が明るくなる。
読みはナレーションを大切にする。会話文もあるのだが、その表現はほどほどに抑えたほうがいいかもしれない。展開として劇的な部分はあるにせよ、抑揚や強弱より、間や緩急で読みを工夫した方がイメージにあう気がする。寓話的な物語と言っていいだろう。どんな種を心に残すか…闇あって光ということ。
『くらやみきんしの国』
(エミリー・H・ブース作 おおつかのりこ訳)
あかね書房 2020.11

「くらやみ」が怖い男の子は「王子さま」だった。王様になったら、くらやみをなんとかすると決め、成長して実行する。ところが…という展開で、表紙カバー裏には、次のような文章が添えられていた。「わたしたちに たいせつなことを 教えてくれる おはなしです」。読み終えてみると、確かにその印象が残る。
表紙と同様に、お話の絵も黒と黄色が中心になって構成されている。画材が何かはわからないが、柔らかい線、シンプルかつコミカルな表現が、想像上の国であることにマッチしている。結局、もとに戻る流れは予想されるが、そのクライマックスが「花火」になる箇所が素晴らしい。読み手はここで心が明るくなる。
読みはナレーションを大切にする。会話文もあるのだが、その表現はほどほどに抑えたほうがいいかもしれない。展開として劇的な部分はあるにせよ、抑揚や強弱より、間や緩急で読みを工夫した方がイメージにあう気がする。寓話的な物語と言っていいだろう。どんな種を心に残すか…闇あって光ということ。