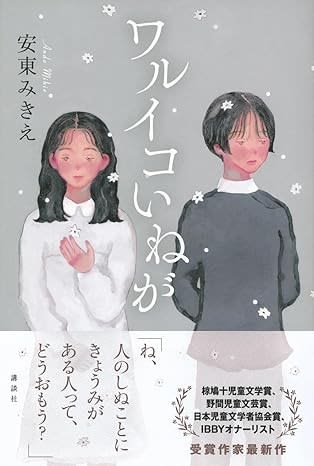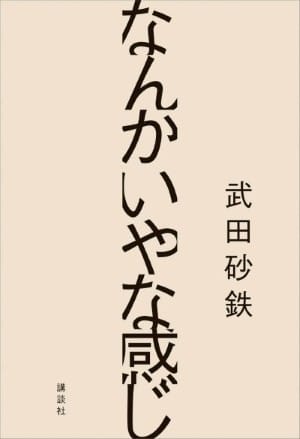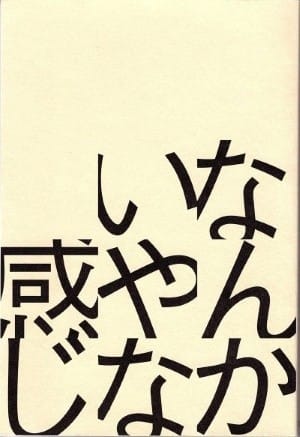著者の存在も名前も知らなかったが、『何かのためではない、特別なこと』(平川克美)で紹介されていて興味をもった。ドキュメンタリー映画の監督が、映画美学校における短期集中講座の内容が書き起こしている。実に刺激的であった。「観察映画」とあるように製作論なのだがまさしく「知」といっていい。
通常TVで観るドキュメンタリーとは全く異なる。事前リサーチもせず、テーマ設定もしない。作品自体にナレーションもBGM音楽もないという。手法の核はもちろん「観察」である。小学校低学年から聞いているごく普通の言葉だが、今改めてその深さに気づくような感覚を持った。著者はこんなふうに語る。
私たちは日常生活の中で、観察しながら生きていないんですよ。だいたいのことは、観察せずに「これはこういうもの」って思い込んだまま通り過ぎていく。(略)よく観てよく聴くとですね、通り過ぎていた、当たり前だと思っていたことが、当たり前じゃなくなってくるんですよ。
わかるよ、けれどいちいちそんなことをしていられないのが世の常だ…そんな言い訳をしながら、社会や世間の動きをTVやネット情報だけで、見た気になり聞いた気になり知った気になって、それだけでなく目の前の事象も手持ちの解釈のみで吟味せずに…そんな毎日こそがじわりと自分を縛り、弱めていないか。
「編集」という言葉も、この本では今までの概念とは異なった様相を見せる。何かめあてやテーマを持って収集し、選択し、構築していくイメージでとらえていたが、ここでは実際の映画作りの過程で得た実感を、著者はこのように語っている。それはよくある「予定調和」や「結論ありき」の世界とかけ離れている。
つくづく思ったのは、編集という作業は、自分が体験した「過去」を現時点から再解釈する作業であるということです。
即効性、効率性が求められる世の中では日の当たらない思考だけれど、少なくない人たちは気づいている。「特に大事なことになればなるほど、すぐに答えようとしないほうがいい」…すぐに明示されることなど、たかがしれている。著者の作った映像が訴えてくるものを体感したい。必ず視聴し観察すると決めた。