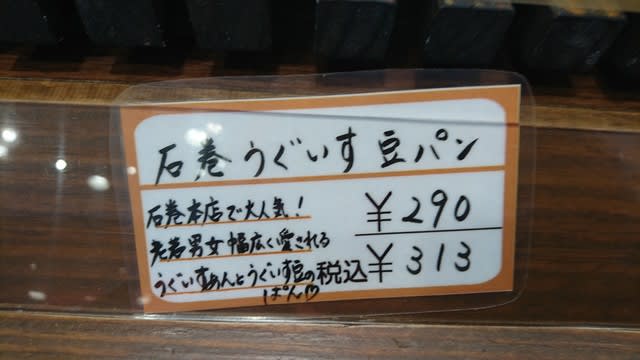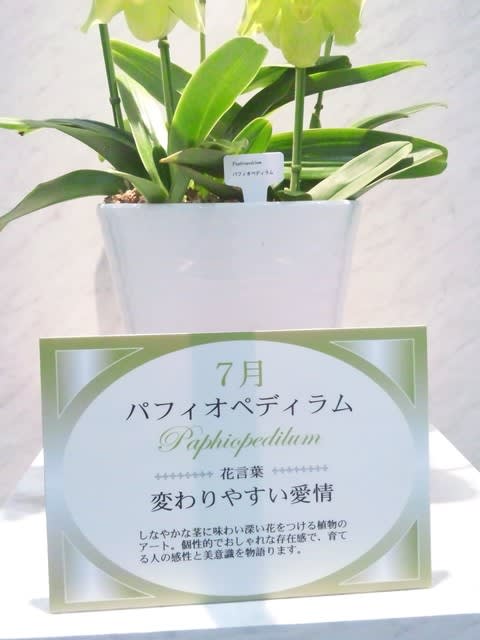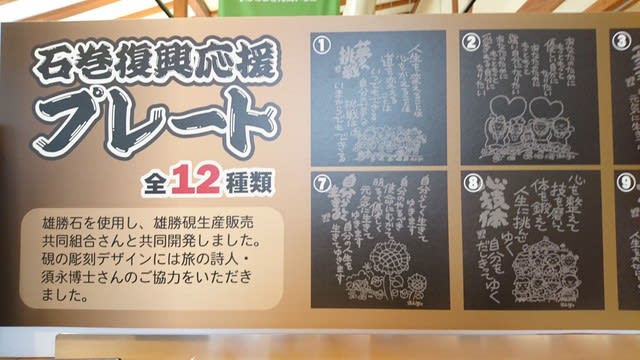上の写真は確か長浜海岸だったような気がしますが、今から60年余り前の門脇小学校の当時1年生の子どもたちと当時の確か1年3組(?だったかな?)の担任の先生、保護者のお母さん2名ほどが写っている海浜学校の写真の上部です。
後ろの景色に見覚えのある方がいらっしゃるのではないでしょうか?
渡波出身の方がこの写真を見たとき、「ああ、あそこが〇〇ね。」と話していたので、近辺に住んでいた方にとってはおなじみの風景なのかもしれません。
この長浜にも、「戊辰150年」の生々しい事実があったことが分かりました。
伊達藩でも新政府軍派と旧幕臣派とに分かれ様々な混乱があったことは、以前の「戊辰戦争150年」の記事でちょっと紹介しましたが、この長浜での事件もその頃のことです。
以下の内容は、2019年2月3日の河北新報によるものです。(途中省略があります。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1868(明治元)年旧暦10月12日、旧幕臣の榎本武揚、新鮮組副長土方歳三、仙台藩額兵隊長の星恂太郎(じゅんたろう)ら2000人を乗せた艦隊は石巻の折浜から蝦夷地(北海道)へ向けて出航した。
当時、石巻にいた旧幕府兵らは4300人。全員は乗せられず「不動の決心を有する忠誠の士」(戊辰役戦史)を選抜した。
この後乗船できなかった者たちは追跡してきた政府軍により、150人が捕縛、斬首されたのだ。
これほど大規模な処刑は戊辰戦争を通じても異例なのに、新政府や仙台藩の記録には載っていない。
目撃者の口伝で語り継がれてきた。
元石巻市図書館長で郷土史家の故橋本昌氏は祖父から目撃談を聞いたという。石巻の生き字引と称された橋本氏の著書などによると、処刑は長浜(現在の石巻漁港周辺)であり、目抜き通りに首がさらされた。
さらに裏付ける証言が2005年、歴史継承の市民団体「石巻千石船の会」(石巻市)の機関紙「ふるさとのかたりべ」に載った。市内の女性(匿名)が1944年に目撃者の高齢女性から聞いた話だという。
話によると、路地を逃げ回る旧幕臣兵が家の雨戸をたたき「入れてくれ」と請う。しかし、助けると責めを受けると恐れた住民はみな知らんぷり。山に逃げた兵たちは空腹や寒さに耐えかね下山して捕まった。手向かおうにも刀や羽織は借金のかたに取られていたらしい。
「処刑がある」というので長浜に見に行くと、兵たちはうなだれていた。斬首の時には「助けてくれ」と泣いた。暴れる時には取り押さえられ、やりで刺された。「威張って歩いていた兵が泣いて殺される姿は見ていられなかった。」という。100人できかない数と振り返っている。
これほどむごたらしい出来事が歴史に埋もれたのはなぜか。
元石巻教育長で郷土史家の阿部和夫さん(80)=同市芸術文化振興財団理事長=は「住民は旧幕府の関係者と思われて処罰されたり、逆に旧幕府兵から報復されたりするのを恐れて口をつぐんだ」と指摘する。
※ 石巻の敗残兵
旧幕府軍の敗残兵らは石巻周辺の各集落や島に潜んだ。現地では民家に押し入って略奪したり、宿泊させるよう強要するなどの事件が相次いだ。仙台藩の統制を離れた脱走兵たちも地域の富豪や米穀船を襲い、軍資金と称して強制的に金品を差し出させた。東北三大地主の一人、前谷地の斎藤善右衛門は現在の貨幣価値だと1億数千万円に上る2200両を奪われた。仙台藩士二関源治の率いる脱走兵らの組織「見国隊」は徴発した軍資金で英国商船を雇い、石巻から函館に渡って榎本武揚と合流。二関は1869年、函館五稜郭の戦いで戦死した。
文・酒井原雄平
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どもの頃、みんなで楽しくキャーキャーと波と戯れ遊んだ砂浜にそのような歴史が秘められていたとは全く思いもよりませんでした。この年齢になって初めて知って驚きました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おまけ (上の記事とは関係ありません。)
「ある晴れた冬の日のカフェテラスの出来事」

スズメがきました!

セグロセキレイも来ました!
私はパンのかけらを投げて与えました。

「アッ!! 食べ物だ!」とセグロセキレイ君?が気がつきました。

「さあ、いただくとしようか..」

大きいのでちぎって一部分を食べました。あっ!!陰にはスズメちゃんがいますね!

いつの間にかスズメちゃんが近づいてきています。右上です。

しかし、セグロセキレイ君は立ち去ろうとしません。

「ああ、まだいる...!」一定の距離を保ってスズメちゃんはその辺にいます。

「まだいるなあ...」スズメちゃんも待っているようです。

「まだいるけど、欲しいなあ..」少しづつ近寄ってくるスズメちゃん。

そして、ついに!! セグロセキレイ君は飛び去っていきました!
「ヤッター!!」スズメちゃんは素早く飛んできて、私たちをも警戒してあっという間にパンくずを加えて立ち去ったのでした。
めでたし!めでたし!