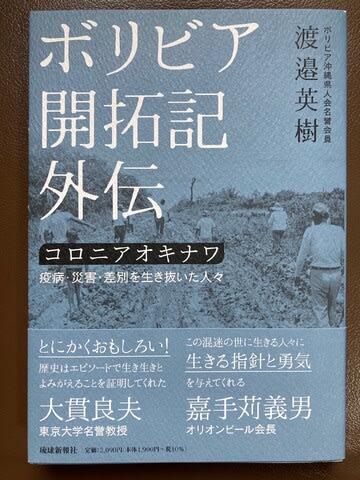短詩グラマトロジー 第十三回:畳音法
斎藤 秀雄
かつて岡井隆は、九鬼周造の論文「日本詩の押韻」を念頭に、押韻を退けた。《むしろ「去嫌(さりぎらい)」の禁のように、「不可押韻の格律」をもうけたほうがよい》(「短歌論――韻律論をめぐる諸問題」『新装版短詩型文学論』紀伊國屋書店、四二頁。以下、同論文からの引用は頁数のみ示す)。そのうえで、彼が《母音律》(四五頁)と呼ぶ、リズム論を展開する。岡井の論旨に、私は、半ば以上に共鳴・同情することを隠さないが、しかし、非常に多くの点で袂を分かたねばならないのもまた事実である。
すべての点に触れる紙幅はない。二点のみ挙げる。第一に、岡井は「芸術」という《途方もないプロブレム》を前に《道をひきかえ》してしまう(一九頁)。過去の集積から、経験的・帰納法的に導かれた、「本質」という名の遠近法的錯視に利はない。芸術というプロブレムを考えるならば、まだみぬ、未経験の、逸脱した、来るべき何かが必要となるはずだ。第二に、岡井は《日本語による韻律詩の(…)美しさ・すぐれた表現力》(十頁)を問題にする(彼は《美(・)し(・)い(・)という言葉が誤解をまねく》(二九頁)ことに気づいてはいるが)。十八世紀前半に「美学」を構想したバウムガルテンは、「芸術作品は美しい」ことを疑っていなかったようであるが、同世紀末のカントは、そうではないことを知っていた。そしてさらに、十九世紀末になると《美と芸術が重ならないという主張が顕在化》(佐々木健一『美学辞典』東京大学出版会、四頁)してくるのである。
例えば、〈畳音法〉という言葉で、私が指し示そうとしている事態は、「すもももももももものうち」にみられるような、何らかのおかしみがあり、注意を引く、情報的意味を超えたなにがしか、である。この言葉遊びは、早口言葉に用いられることから分かるように、発音しにくい。視覚的にも、情報的意味を得難い。つまり美しくない。しかしその「美しくなさ」において、「なにがしか」が発生しているのである。
私は、畳音法を、同じ語の連続する〈畳語法〉と区別する。ちなみにWikipediaの「畳語法」の項目(英語版はEpizeuxis)は、畳語法と畳音法を同意としている。また、辞書に「畳音」は、あいだに間を置かずに「めきめき」「みみ」のように連続することと定義される。本論でみるように、本稿はこの連続性とも袂を分かつから、「特殊な畳音法」と呼ぶべきなのかもしれない。
谷川俊太郎の「ののはな」(『ことばあそびうた』福音館書店、一九七三年)をみてみよう。
はなののののはな
はなのななあに
なずななのはな
なもないのばな
ここで、詩としての出来不出来は問わない。特に三行目から四行目に移行するときの、大衆向けの、だらしのない抒情に、顔をしかめる読者もいるかもしれない。しかしここで注目したいのは、第一行である。先にみた、発音のしにくさ、情報的意味の得難さがある。「花野の野の花」と表記してしまっては失われてしまう、忘れ難い「なにがしか」がある。他行の七音に揃えるために「はなのののばな」とすれば、美しく、スムーズで、快いものになるかもしれないが、しかしそのことでむしろ退屈になる。四行全体に「は」「な」「の」の音(および表記)が散りばめられ、反復されていることは、本作が詩集名のとおり「ことばあそび」であることを示しているだろう。が、本作を「あそび」以上の何かに高めている最大要因は、一行目の、スムーズでなさ、躓き、にあると思われるのだ。
短歌の例をみよう。
あの母をあざむくすべはあらざらむあざ打たれしを冷やして帰る 岡井 隆
はつかりのはつかに戀ふるちちのみの父こそ鳥の道ゆ落ちけれ 水原 紫苑
一首目。歌集『眼底紀行』より。ここにa音の頻出のみをみるならば、岡井の言うように《おどろくべき「応和」氾濫》(四二頁)となってしまう。我々は《あざむく》《あらざら》《あざ》に注目したい。いっけん「頭韻」にみえるが(子音ではないから頭韻的、と言うべきだが)、異なる語に含まれる同音が、ふたつ目は《ら》音を挟みつつ、反復されている。「アザ」の二音が、「狭広狭」のリズムを携えて、一首に伏流している。「打たれしあざを」としない点も、岡井的な屈折への意志を感じさせる。
二首目。歌集『快樂』より。ここにみられる枕詞「初雁の」「乳の実の」はいずれも、同音の繰り返しによって掛かるのだから、改めて畳音法だと呼ぶのは、冗長的ではある。現代短歌の一首に二つの枕詞を導入するのも、執拗さという点で、不思議な感慨を抱かせる。水原の短歌には「ちちのみの父」「ははそはの母」が頻出する。掲歌は同歌集所収の《なかぞらにをりをりねむりわだつみをこゆる鳥たち母たちのごと》と対照的呼応の関係にあるように感ぜられる。
俳句の例をみよう。
甘草の芽のとびとびのひとならび 高野 素十
かさなりの深みへどくだみの緑 鴇田 智哉
一句目。《とびとび》は畳語だが、「トビ」の音が離散して《ひとならび》に含まれる。《とびとび》は連続性を、《ひとならび》は距離を想起させ、つまり中七と下五はシニフィアンとシニフィエが交叉している。この句を論じた対談「句修行漫談」『ホトトギス』(昭和六年)(および昭和三年の虚子による「秋桜子と素十」)をきっかけに、水原秋桜子はホトトギスを離脱することになるが、当時、肯定的にせよ否定的にせよ、掲句がリアリズムとしてしか語られなかったことは、レトロスペクティヴな観点からは、不思議な事態として感ぜられる。
二句目。ai音の三度の反復(応和氾濫)が目立つ。おそらく意図された執拗さであろう。しかし、《かさなり》《どくだみ》《緑》にある、「リドミ」の、離散しかつ反転した反復が、不思議な効果を発揮していることに注意すべきだ。《どくだみ》は白い花で、《緑》なのは葉であるはずだが、反転した「リドミ」により、葉叢の《かさなりの深みへ》いったん潜り込んだあと、そちら側から花を見上げたような、奇妙な奥深さが、読みの知覚領域に伏流してくるのである。 (続)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
雨が上がった隙に
揚羽が何度目かの卵産み付けに

(20250615)
山椒を丸裸にして
葉が茂ってきてちょうどいい頃合いに
また産卵に~
狭庭で収穫した大根
これだけ、なんでこうなるの?

GOOブログの皆さんの引越しが行われているようですね~
10月までに終了しないといけないようですが
なんだかなあ~
あまり気がすすまなくて
ずっと以前、ヤプログからの移動の時に
はてなブログで1回と
一か月前くらいに2回目UPしたように思いますが
画像UPの仕方など使い方がよく分からなくて~
だけど
まあ~引っ越しだけはしておこうかなとも