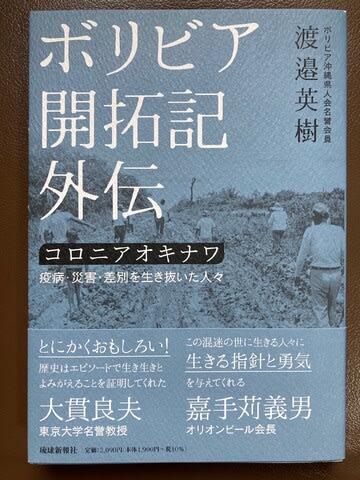前号俳句 ふたり合評
いんそむにあ日は白魚に泥みゐて 楠本 奇蹄
阪野基道 白魚は春を告げる魚。生きた白魚の体に日
が当たればその透明性は際立ち、この世の生き物の不
思議、神秘を思い知らされる。春先は精神が不安定に
なりやすい季節でもある。踊り食いを食べたのがまず
かったのか、喉で白魚が跳ねた。そのための不眠症か。
斎藤秀雄 半透明の《白魚》の、密集したかたまりは悪夢のようだ。しかも《日》が《泥》んでいるとは。「暮れ泥む」の慣用語の通り、ここで《泥み》は「滞り」の意だろう。しかしまた「馴染み」でもあり「病み」でもあり「執心し」の意でもある。不眠の意識に到来する白昼夢。
惑星と惑星を結ぶよう馬洗う 早舩 煙雨
加能雅臣 「惑星」は光らない。恒星の光を反射するだけの、つまり鏡のようなもの。太陽系においては太陽が水金地火木土天海という八つの鏡を持つ。これら八つの鏡を調整して太陽系を万華鏡化すべく、この馬を走らせていたのかもしれない。人と馬の関わりの奥深さに驚く。
小田桐妙女 惑星と惑星の距離は想像しがたい。馬を
洗ったことはないが、近くで見たことはあるので、なん
となく想像はつく。ここには人間と馬との近い距離がある。両者には距離という共通点がある。このことによって、「惑星と惑星」「馬洗う」の季語も結ばれるように思う。
夏の星彼方を吠える野犬をり 貴田 雄介
早舩煙雨 涼やかな星の光のもとで、野犬の声が遠くに聞こえる。しかし、この野犬もあの星を見つめて吠えたのだろうか。もしかして、聞こえたのは遠くの星からの遠吠えなのか。別の銀河の野犬から見れば、私のいる地球も夏の星であり、地球への届かぬ咆哮があるのかもしれない。
小田桐妙女 中学生の頃、体にらくがきをされた野犬がいた。元は誰かに飼われていたのだろうか?田舎だったからか、外で犬を飼う家も多かったが、とんと見かけなくなった。懐かしい一句。「吠える」という字を見ると、すぐに萩原朔太郎の『月に吠える』を思い出してしまう。
白藤やふつりふつりと眠り落つ 籾田 ゆうこ
阪野基道 眠りに落ちるときの快楽は何ともいえない。
ふつりふつりとは言い得て妙。どこから眠りなのか、そ
の境目を誰も知ることができない。季語は白藤。ピュア
な花だが、花房がいく筋も垂れた向こうには死の世界が
ありそう。眠りの裏側にはつねに死が漂っているのだ。
松永みよこ この藤は紫ではなく、白色でなくてはなら
ない。白藤のしずくのようなシルエットはまさしく眠り
に落ちる姿であると共感する。そして眠りを「ふつりふ
つり」と内側から湧き出す、途切れ途切れに見えながら
もつながっているものとして描いている点が面白い。
そう言って蒲公英の種旅立ちぬ 林 よしこ
男波弘志 そう言って、という無言の声をどれだけ聴きとれるだろうか。人は何かに耳を澄ますとき大人になるのかもしれない。決して連れて行って欲しいとは言わない。だけどもうこころが蒲公英の絮に付いて行ってしまった。身体だけが置き去りになっている。そう言っての背後には「そう告げて」のニュアンスが秘められている。
松永みよこ 蒲公英、とても凛々しい青年の姿が浮かぶ。
「たんぽぽ」や「タンポポ」にはない格調の高さがにじ
み出ている。冒頭の「そう言って」が何を言ってなのか
という点は私は気にならなかった。蒲公英がそういった
なら、きっとそうなんだろうと思った次第である。
辺境のたましい灼ける咎なき火 阪野 基道
しまもと莱浮 飛んで火に入る夏の虫だって?冗談じゃない。火あぶりの刑などされてたまるか。フロンティア・スピリット、新しいことに挑戦する気概、もえるような激しい感情、どうしてそれが非難される謂われがあるというのだろう。
斎藤秀雄 掲句からは、この《たましい》が《辺境》にあることは、偶発的であるように感ぜられる。何の《咎》があるというのか、《火》に《咎》が無いように。《灼ける》原因たる「日」が《火》に転じる(対照される)ことで、《たましい》は、《灼》の第二義「輝く」の性質を帯びる。
花筏揺らさぬやうに母の恋 松永 みよこ
籾田ゆうこ 揺らさぬようにという言葉から、恋をして動揺する自分に対して落ち着け〜と言っているような気がしました。母の恋ならシングルマザーかもしれない。また水面を流れていく小さな花弁が崩れないように心を配る優しさを感じました。
男波弘志 この場合の母の恋とは、やはり作者が生まれる以前の恋であろう。ちちとははが出会ったときに、さくらが咲いてそして散っていった。水面をぼんやりと眺めている二人にとめどもなく拡がってゆく花筏、余りにも大きな風景に呑まれてしまった二人。恋という必然さえ忘れて恋におちたのだろう。
ほうたるやカロリーならば足りてます 森 さかえ
籾田ゆうこ この蛍の点滅は儚さとかけ離れた生命力を感じさせる力強い印象を受けて面白いなと思いました。蛍は元気だからこそ光を出して相手を見つけるんだろうなあと。また蛍の活き活きとした様子をカロリーならば足りてますと表現したところに作者の個性を感じます。
早舩煙雨 元気に光り続ける蛍の気持ちであろうか。蛍が光るのは求愛や威嚇などの理由があるそうだが、カロリー燃焼という目的もあるとしたら、まるで現代人のよう。夜更かしをしてスマホを見ながらコンビニに夜食を買いに行く人たちならば、カロリーが足りない蛍であろうか。
背のびする子もしない子も土筆 内野 多恵子
林よしこ 子供等が土筆の原で遊んでいるとも、又土筆そのものが背伸びをしているとも執れる。後者を執りたい。春の気配を感じた土筆の子、最初に背伸びをしたのは先に生まれた兄土筆、続いて間もなく弟土筆も背伸びするに違いない。春の楽しい野原の光景が見えてくる、発見の句。
しまもと莱浮 土手を散歩していると、すくすくと伸びている土筆を見つけた。土筆は「付く子」だという説もあるように、ついつい子供と結びつく。ここは通学路だろうか、ませた子のんびりした子が一緒に下校している。
孫はどうしていただろうか。
古里の地名が消えるかなかなかな 江良 修
籾田ゆうこ 自分の生まれ育ったふるさとは古里となり地名まで消えてしまった。ひぐらしの寂しい鳴き声と共に。下五のかなかなかながデクレッシェンドして最後に消えていくところは乙だなあと思った。こういった音の遊び方が出来るようになりたい。
阪野基道 蜩の哀愁に満ちた鳴き声の中に古里が消えて
ゆく、という感慨を詠っているが、古くはダムに沈む村
が象徴的だった。今の時代ならば空爆後の瓦礫化した世
界も、このように言えるのかもしれない。かなが三回繰
り返されているが、切れをどこに取るか、も楽しめる句。
料峭や唱へてをりし不帰の客 小田 桐妙女
加能雅臣 「料峭」に晒される我が身の束の間、「不帰の客」の声明が聞こえる。この世の時が止まって、あちらの時間が現れる。この「不帰の客」は未だ成仏のさなかにいるのだろう。一人きりではなく大勢の中の一人かもしれない。己自身が己自身へ「唱へて」いる健気。
松永みよこ 一見暖かく穏やかに見えようとも、春には
春の厳しさがあることが「料峭」(寒さがぶり返して肌
寒くなること)、「不帰の客」の漢語表現できびきび描
き出される。亡くなってもう会えない人が生前熱心に唱
えていた経は、今ではその人自身に捧げられている。
わたくしの息継ぎをする金魚たち 男波 弘志
しまもと莱浮 今日もまた暑い。うちで飼っている金魚は大丈夫だろうか。仕事中でも気になってしょうがない。水温が上がって息も絶え絶えになっていないだろうか。苦しい苦しいと訴えかけているんじゃないか。なんでこんなに残業続きなんだ。早く帰りたい。
斎藤秀雄 第一に、《金魚たち》はそれぞれ個別的な《息継ぎ》をする。第二に、《金魚たち》は語り手=《わたくし》の代わりに《息継ぎ》をする。自発的に《息継ぎ》できないのは、ただ語り手一人である。しかし代理がいるのだから、わざわざ《わたくし》がやるまでもないのだ。
ラムネ抜く手に水搔きのなかりけり 加能 雅臣
早舩煙雨 清涼感と幻想性が隣り合う素敵な句。ふと人間であることを思い出すほどに、無心で泳いだ直後なのかもしれない。または、ラムネの泡を視た目の奥に、ある太古の記憶が蘇った瞬間とも思える。別の読みとして、河童が人間の子に化け、川辺でラムネを盗む景も浮んだ。
林よしこ 「良いことをすれば人間になれる」と泉の女神に言われ、せっせと精神を磨き努力した河童。ある日泉の畔に人間の子供が忘れて行ったラムネを皆に分けてあげようと手に取ったが自分の力ではなかなか開かない。毎日工夫を懲らしている内に水掻きが無くなっていた。童話ですね!
人影を吐き空蝉の部屋震ふ 斎藤 秀雄
男波弘志 もし好意的にこの一行詩を鑑賞した人がいたならば、「人影を吐き」を何かの心情として受け止めるかもしれないが、実際にこの特異な現象を一度も見ていない者には解読不能であろう。片言隻語の一行詩がほんとうに力を発揮するのは、一読した突端にその光景が一枚の絵となって映像化されたときだろう。果たしてそれが可能だろうか。
小田桐妙女 人ではなく人影を吐くのが空蝉らしい。その人は本当にいたのか?夢のなかで見かけただけかもしれない。ほら、夢のなかの人影から現実に人が生れそう、空蝉の部屋が震えているもの・・・空蝉の部屋は、源氏物語の空蝉の部屋と読んでも面白いかもしれない。
葉桜となりて余生の戻りけり 島松 岳
林よしこ 人生の大半を過ごした人にとって「葉桜」はぴったりのおとなの趣きがある。余生と言えど、これからが自分だけの至福の時間が取れると言うもの。散ることなど考えなくても良い。生まれ変わりの春はすぐに来るのだから。だからこそ次の世にも心置きなく行くことが出来るのだ。
加能雅臣 〈余生に〉ではなく「余生の戻りけり」とは如何なる事態なのか。すでに「余生」にある者が、桜の匂う季節の束の間、「生」を失っていたということだろうか。「葉桜」とともに我は蘇り、「余生」はいっそうみずみずしく「余生」となってゆく。束の間の輪廻転生。
桜狩り首から下は湿りおり 竹本 仰
阪野基道 子どものころ庭に綺麗な桜が咲いていれば、
小枝を折って振り回して遊んだものだ。そんなヤンチャ
時代を思い浮かべながら、首から下が湿っている状況と
いえば「性への目覚め」しかないようだ。これは男女を
問わず、子供から思春期への分岐点の現象といえそうだ。
加能雅臣 今まさに地中から生まれ出て来たかのような「湿り」のある身体がここに立っている。もののふが蘇ったかのようだが、首から上はどうもはっきりしない。まだ新しい顔が出来上がっていないようだ。花の季節が終わる頃には、その首は座り顔は笑っていることだろう。
深まれば月がゆたゆた風呂にいる しまもと 莱浮
早舩煙雨 湯に映る月が風呂に入っているように見える、または、風呂に入っている丸みを帯びた誰かの背中が湯に影を落としてまるで満月の様に見えるのかもしれない。秋、夜、眠り、思考。一体何が深まるのかということを明示されていない為、その湯が在る背景を様々に想像させる。
小田桐妙女 最後の「風呂にいる」という淡々とした閉めかたが愉快である。ゆたゆた、もまた楽しい。深まればという思わせぶりな入り方。露天風呂であろうか?月も一緒に風呂につかっているような。このひとときの幸福感は独り占めしたい。誰も入って来ませんように。
白手巾裂いて死人を口寄せて 加藤 知子
松永みよこ 生木を裂くという言葉があるように「裂」
の語は非常に激しい。「白手巾」を「裂」く者と「死人
はかつて深い情愛で結びついていたのだろう。「白手巾
」は処女膜のメタファであり、それを裂くとは、つまり
別の男との交わりによって「死人」を呼び起こすのだ。
斎藤秀雄 「夏痩せて」「夕焼けて」といった、名詞の動詞化(逆成)を難ずる向きもあるが、いまや「眼差す」さえ『広辞苑』の見出しにあるのだ。しかしここでは、なかなかに趣のある「かろみ」が漂っている。《白手巾》の効果もあろうか、南方の、明るい《口寄せ》が脳裏に浮かぶ。

昨日は
玉名での現代俳句をやっておられる方々の句会にお邪魔した。
ここで話題にしたいのは
俳句の話ではなく
珈琲の値段なのだが、
物価高の現在、全国的においくらくらいなんだろうか。
菊池で、珈琲一杯のみで6百円にビックリしたが
玉名で昨日行った店は、7百円。
ニセコなどに比べたらなんてことない値段かもしれないが
そういう相場なのかなー。
3週間前に撮った葱坊主

この折れ具合がなんとも言えない~