ラーメンフリークやラーメンファン向けではなく、ラーメン店主向けの専門書。
専門書とはいっても、現在のトレンドの分析や最新調理法や最新調理器具などの本で、決して読みにくくはない。
この本は、読みどころ満載。最近僕が強く感じていることを、一風堂の河原さんが見事に語ってくれていた。
最近開業するラーメン店は『大勝軒』系、『二郎』系、『武蔵』系といった感じのものが多すぎる。「インスパイア」なんて言葉を使ったって、オリジナリティが全然感じられないよ。・・・より厳しい時代を迎えているんだから、それを跳ね返すくらいの強い意志を持たなきゃだめだ。そのためには400軒、500軒のラーメン店を食べ歩きましたじゃなくて、うどん野500軒とか、洋食屋300軒とか、一流のフレンチをつくれるくらいに腕を磨いているとか、それこそ茶道を徹底して追及したうえで、それをラーメンで表現するくらいでなきゃ。(p.17)
極めて同感だ。僕の拠点の千葉や東京でも、最近出てくるお店は、ホント既成の有名店のJrとか、インスパイアとか、巨大グループの一員とか、そういうタイプのラーメン店ばかり。味も(それなりに美味しいが)既に知っている味ばかり。お決まりのパターンにはまるものばかりだ。ある程度の方程式が確立されていて、それを出せばそれなりに動員を得ることができる。しかし、それで本当によいのか、と(ヴィジュアル系が飽和した98年頃にそっくり)。最近の新店はどれも、濃厚豚骨醤油系か、二郎系か、またそれに類するものばかりだ。当然、ある程度の人気が即座に得られるため即効性は高い。が、そこに発展はないし、新しさもないし、斬新さもないし、個性もないし、オリジナリティーもない。作り手からしても、産みの苦しみはないし、悩みはないし、苦悩もない。守りのラーメンでしかない。
そこで、河原さんが提言するのが、他の料理の世界を知る、料理以外の世界を知る、そこから学ぶ、という学びの姿勢だ。ラーメンの技術が高度化すればするほど、職人はその技術の世界に飲み込まれることになる。覚えることも増える。しかし、そうなると、ラーメンの狭い世界しか見えなくなる。最近はラーメンの情報も超飽和状態で、ラーメン店主もその情報に常に振り回されることになる。しかし、職人にとって最も重要なのは、自分がどうするのか、という自分自身の生き方なのだ。河原も、「自分というのがどこにあるのかということをしっかりと認識して挑んでほしい」(同)と述べている。技術の高度化とうらはらに、自己忘却がラーメン界にも起こっている、と言っていいだろう。
*一風堂の味は自分的にはちと・・・って感じだけど、河原さんの言葉は本当にいいなぁ、と思う。彼の本は何気にかなり読んでるからなぁ~ でも極新味は、・・・どうかなぁ・・・(汗)
***
pp.26-27は醤油の作り方の話。醤油を当たり前に使っている店主の知識として是非知っておいてほしい内容だ。自分が知らないものを提供するのってやっぱりちょっと・・・ 醤油って五種類あるのだ。濃口醤油、淡口醤油、たまり醤油、再仕込み醤油、白醤油。さらに、等級として、標準、上級、特級、特選、超特選の五ランクがある。なるほど~と思う内容だった。さらに続けてカドヤ食堂の橘さんのインタビューが続く。彼の素材へのこだわり、理解は半端じゃない。最後にこう言っていた。
ラーメンも立派な料理として認められるように、素材選びもしっかりしないとダメだと思います。単にいい素材を使うというのではなくて、素材をしっかり知ること。たとえば、鶏ガラを使うには、その肉を食べてみてからじゃないと。・・・食べ歩いたり、他ジャンルの料理人さんに教えてもらうことで、素材の使い方を理解していきました(p.30)
ここで注意したいのは、「素材をしっかり知ること」、そして、それに加えて、「食べ歩き」や「他ジャンルの料理人」に教えてもらったりすること、というごく当たり前のことである。このことは、上の河原の考えとも合致する。とりわけ、ラーメンフリークの領域を飛び越えて、様々な料理やジャンルを知ること、学ぶこと、こうしたことが、オリジナルのラーメンを創造する上では欠かせないのだ。なるほど。(カドヤ食堂のラーメンは本当に半端なく美味しかった!keiのレポはこちら)






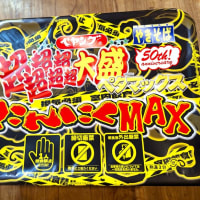



![ローソン[盛りすぎチャレンジ]47%増量でお値段そのまま!「盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり」が凄かった!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0c/22/ce1c21831fa593422e72ccc820e09ca4.jpg)






