日曜日に引き続き、今日も午前中からパワーアンプのスイッチを入れ、午後からながら聴きを続けておりました。
日曜日は本格的に聴く為に絨毯もスピーカーのネットも取り払って聴き込んでおりましたが、
きょうは最初からながら聴きのつもりでおりましたので、そんなに気合を入れず楽しんでおりました。
最初は、先日購入したFRIDE PRIDEの two too
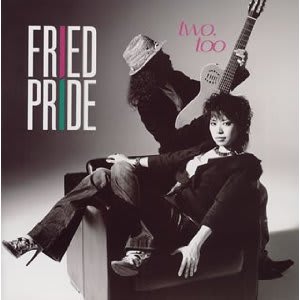
やはり少し詰まった感じで抜けが悪い、しかし聴いていて楽しいし音楽的には良いのでこれでもう少し音が良ければ良いのになぁ!残念。
次はヤマテツお勧めのギターのアルバム

先日、上様宅で聴いた時よりの音が軽い、決して悪い意味ではなくスムーズに倍音も伸びて空間に広がっていく感じ。
そして、武満徹のNAXOS盤 日本作曲家選 「そしてそれが風であることを知った/海へ/雨の樹他」
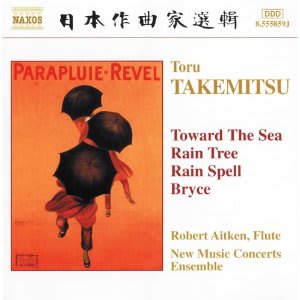
当初から思っていたことですが音離れが非常に良くなって空間表現の幅が大きく広がっています。
先日、吉田苑で聴いたTIDALには遠く及びませんが、CDによってはなかなか良い感じでスピーカーの存在が気にならなくなります。
とても、存在が消えるとまでは言えませんが・・・。
そして、最後はT-TOC RECORDS MASTER CDR-Ⅱから KANKAWA/ORGANIST

我が家のみで味わえていたエモーショナルな表現のオープニングの影が薄れいたってスムーズな表現に変化しています。
これも不思議で低域が飽和するかな?と予想しておりましたが
予想に反してリアルなベースの音が出てきました。
続くヴィブラフォンの響きも柔らかくとてもストレスフリーに空間に広がっていきます。
どこにも誇張した感じがなくてかえって拍子抜けした音です。
加えてサックスがとても柔らかくていい感じです。
サランネットを外して絨毯も取って聴いてみたい気もしましたが、きょうはこのまま良い感じの状態でタイムアップと成りました。
CDによっては飽和するものも出てきましたが総体的に自然な状態に近づいている感じがしたので、当分はこのまま聴き込んで行こうと思います。
今日が良くても明日必ず良いとは限らないのがオーディオの不思議で難しいところですから、じっくり検証してみたいと思っています。
日曜日は本格的に聴く為に絨毯もスピーカーのネットも取り払って聴き込んでおりましたが、
きょうは最初からながら聴きのつもりでおりましたので、そんなに気合を入れず楽しんでおりました。
最初は、先日購入したFRIDE PRIDEの two too
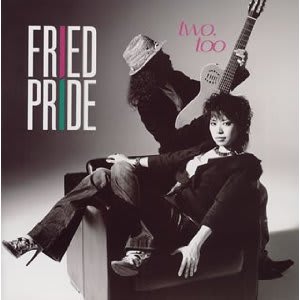
やはり少し詰まった感じで抜けが悪い、しかし聴いていて楽しいし音楽的には良いのでこれでもう少し音が良ければ良いのになぁ!残念。
次はヤマテツお勧めのギターのアルバム

先日、上様宅で聴いた時よりの音が軽い、決して悪い意味ではなくスムーズに倍音も伸びて空間に広がっていく感じ。
そして、武満徹のNAXOS盤 日本作曲家選 「そしてそれが風であることを知った/海へ/雨の樹他」
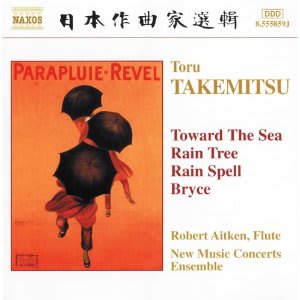
当初から思っていたことですが音離れが非常に良くなって空間表現の幅が大きく広がっています。
先日、吉田苑で聴いたTIDALには遠く及びませんが、CDによってはなかなか良い感じでスピーカーの存在が気にならなくなります。
とても、存在が消えるとまでは言えませんが・・・。
そして、最後はT-TOC RECORDS MASTER CDR-Ⅱから KANKAWA/ORGANIST

我が家のみで味わえていたエモーショナルな表現のオープニングの影が薄れいたってスムーズな表現に変化しています。
これも不思議で低域が飽和するかな?と予想しておりましたが
予想に反してリアルなベースの音が出てきました。
続くヴィブラフォンの響きも柔らかくとてもストレスフリーに空間に広がっていきます。
どこにも誇張した感じがなくてかえって拍子抜けした音です。
加えてサックスがとても柔らかくていい感じです。
サランネットを外して絨毯も取って聴いてみたい気もしましたが、きょうはこのまま良い感じの状態でタイムアップと成りました。
CDによっては飽和するものも出てきましたが総体的に自然な状態に近づいている感じがしたので、当分はこのまま聴き込んで行こうと思います。
今日が良くても明日必ず良いとは限らないのがオーディオの不思議で難しいところですから、じっくり検証してみたいと思っています。














