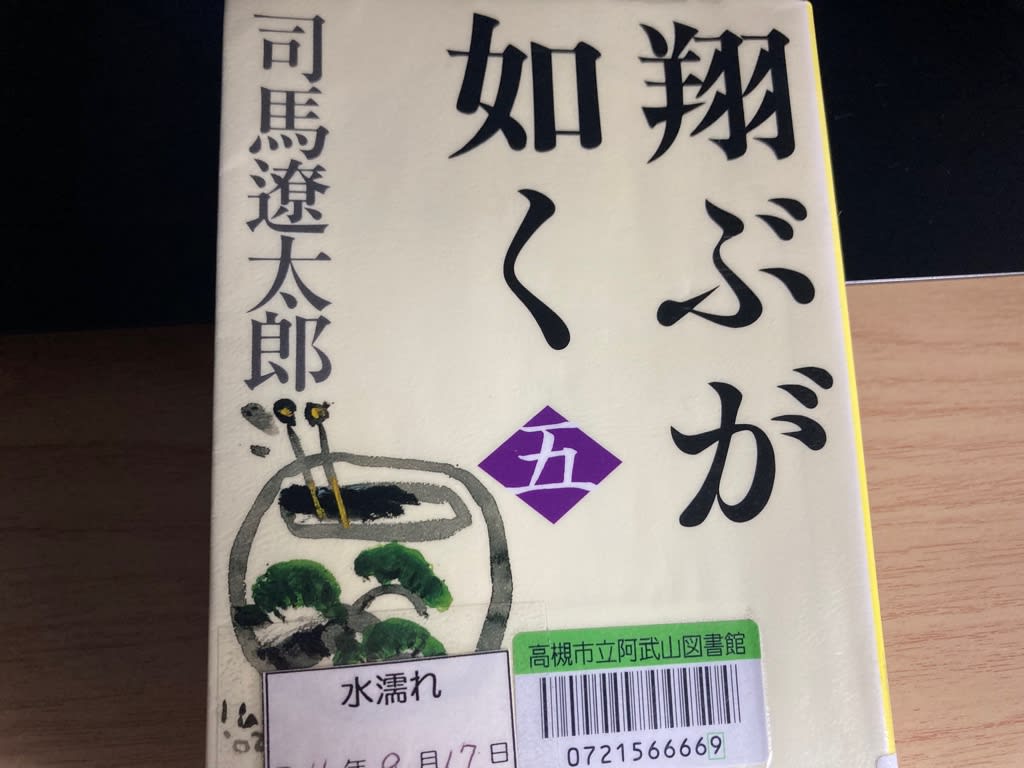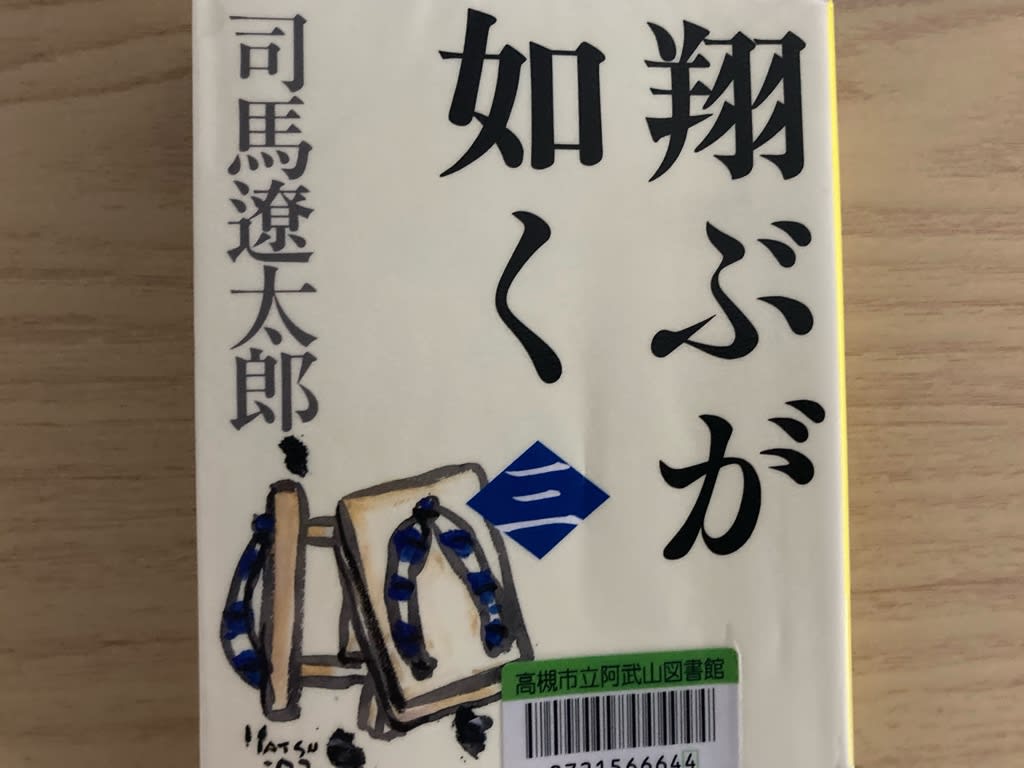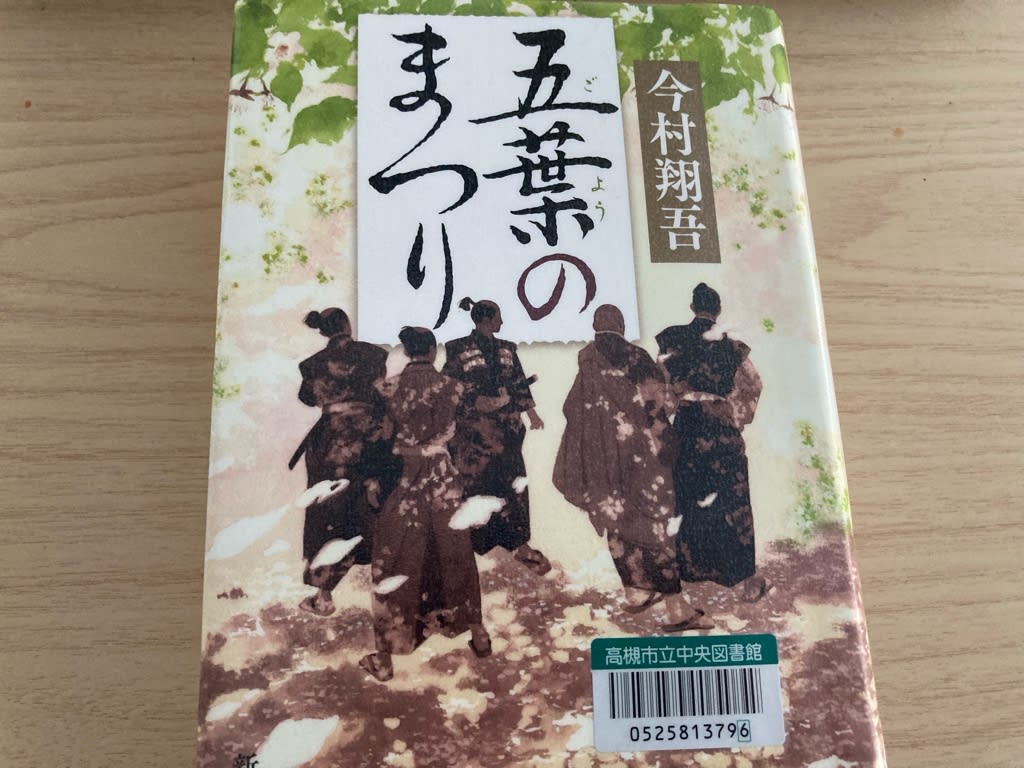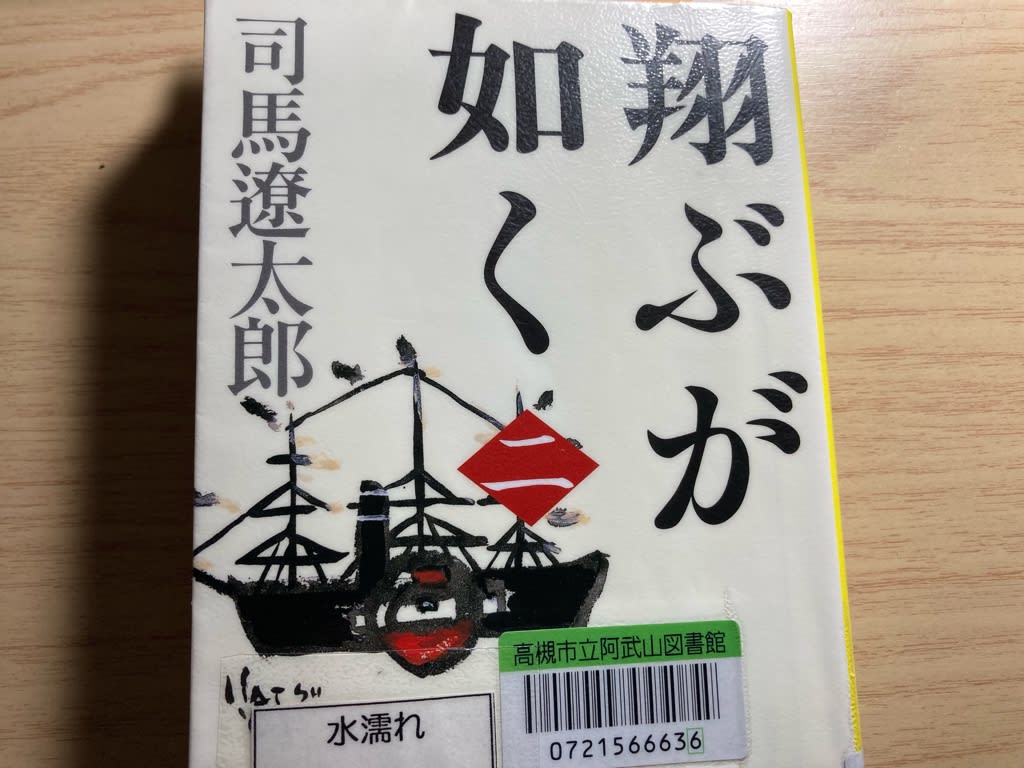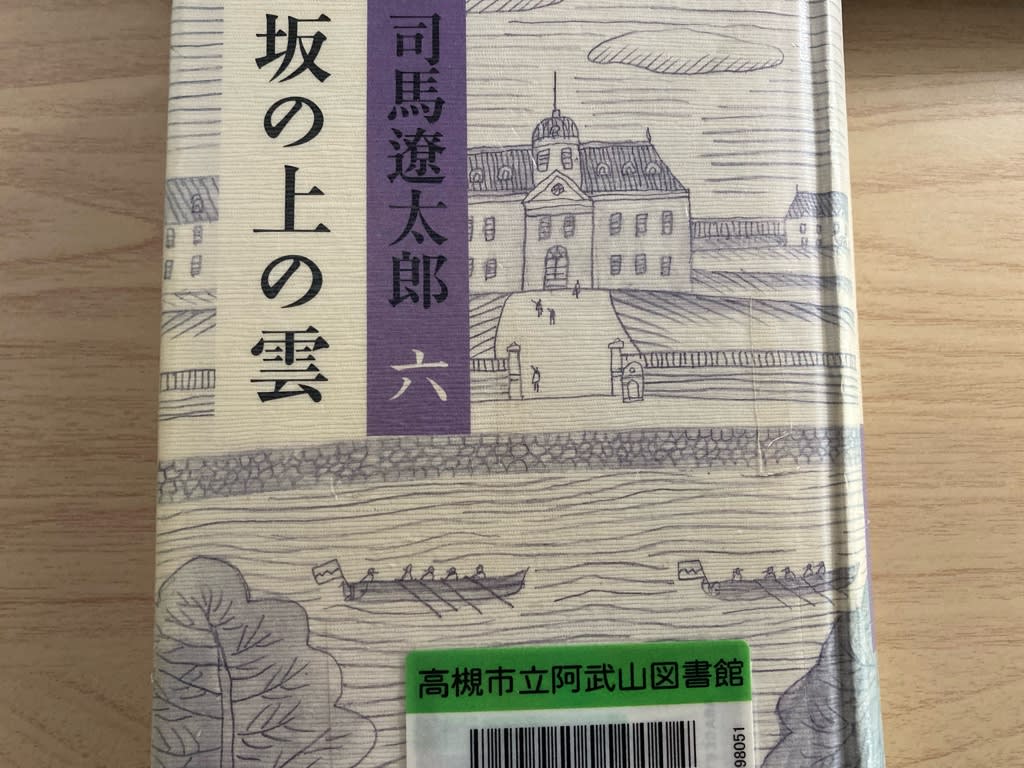台湾撤兵以後、全国的に慢性化している士族の反乱気分を、政府は抑えかねていた。…
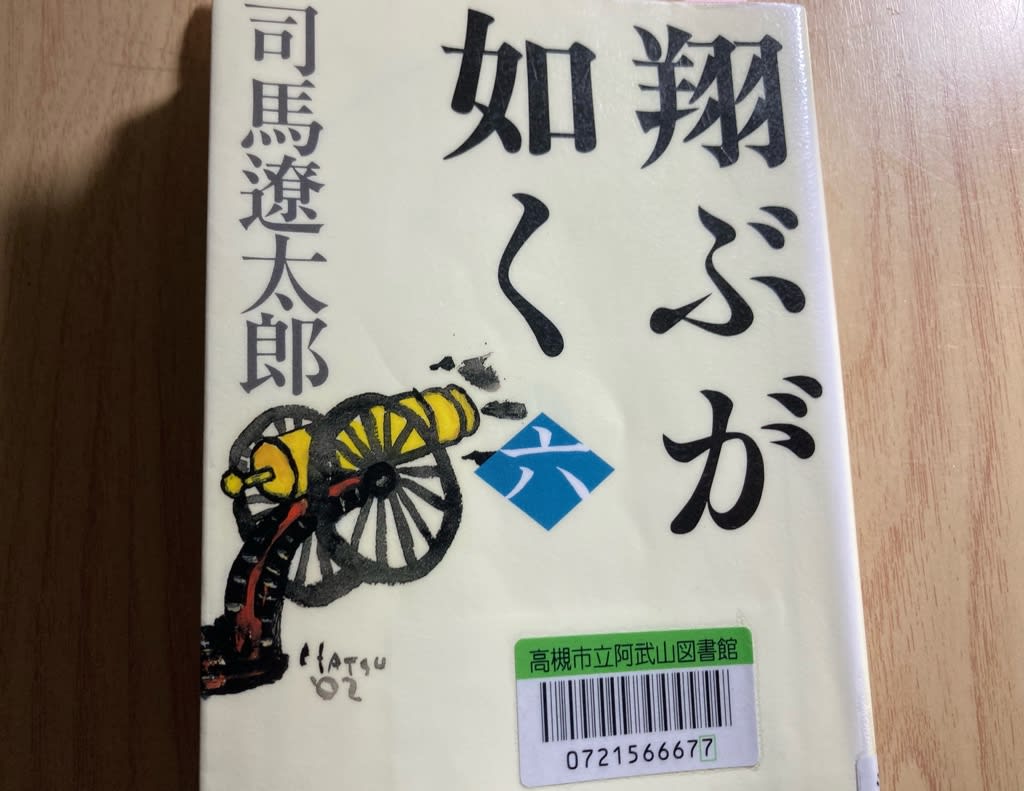
流説の巷
明治九年、新風連ノ乱まで。
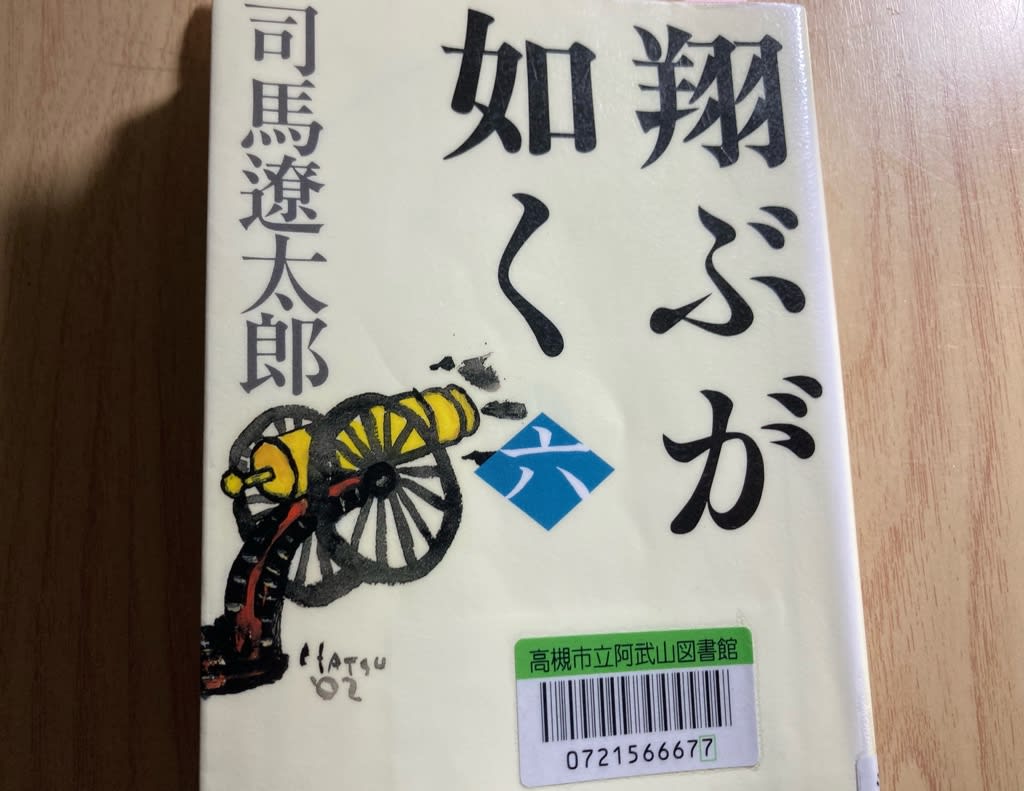
流説の巷
野党の色合いには、封建党もあれば民権党もある。また肥後の学校党のような国権党もあれば、同じく肥後の新風連のような国粋党もある。それらの背景には、封建的特権をうばわれた士族の不満が、全国の各県各郡に充満している。
明治八年九月、江華島事件
明治九年二月、朝鮮にとっての不平等条約…朝鮮が各国に対して門戸をひらくもとにはなった。
鹿児島へ
維新というのは一面において強烈な復古的性格をもっていたが、ひとつには幕末に平田国学系の志士が小さいながらも討幕の努力をなし、それが維新政府に入って神祇官を構成したということもあったであろう。かれらは、仏教をも外来宗教であるとし、鳥羽伏見ノ戦いが終わって二ヶ月後に、政府命令として廃仏毀釈を推進した。
平田国学…復古神道を唱えた思想
蜂起
新風連ノ乱は日本における思想現象のなかで、思想が暴発したという点では明治後最初のものであった。
維新は士族だけでなく「庶人」とよばれる農商階級にも多くの不満をもたらしたが、そのなかでもっとも大きい不満は徴兵令であった。
いろんな出来事や人が、横にも縦にも広がりつながっていくのが面白いです。