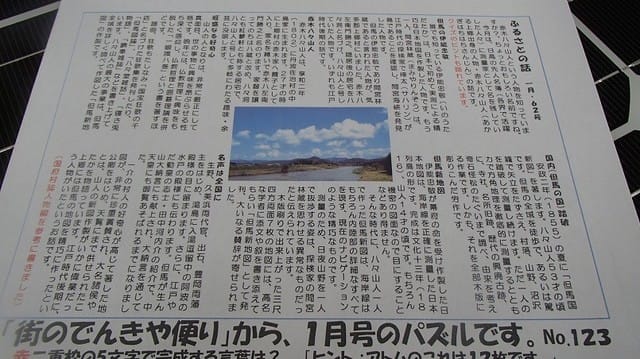
ふるさとの話 一月・62号
赤木八々山人という人物を知っていますか?。ちょっとおもしろい名前ですね。
今月は、日高の先人名簿(各界で活躍した人々)に測量家として名を残している上郷出
身の人物・赤木八々山人(あかぎはちはちさんじん)の話です。
クイズのヒントも隠れています。
但馬の伊能忠敬
誰でも知っている伊能忠敬(いのうただたか)は、日本で初めて実測による精巧な日本
地図を作製した人物です。もう一人、間宮林蔵(まみやりんぞう)は、江戸時代の探検家
で樺太(サハリン)が島であることを確認し、間宮海峡を発見した人物です。
但馬の伊能忠敬であり間宮林蔵であると言われた人物が、気多郡上郷村にいました。
赤木八左衛門勝之、隠居後の居宅を八々洞と名づけ、八々山人と号していた人物です。
いずれも江戸時代後期の話です。
赤木八々山人
赤木八々山人は、享和二年(1802)に丹波佐治村の中島家に生まれます。
27才の時に上郷村の赤木家へ養子として入り、家名を継いで赤木八左衛門勝之と名の
ります。
家督を譲ってのちは八蔵と改め、八々洞とも紅蓼軒とも称する居宅で、八々山人と号し
て多岐にわたる趣味・余芸に没頭します。
旺盛なる好奇心
山人の人となりは、非常に厳正にして真面目、世の事物に興味を昂ぶらせる性格で
す。晩年には、仏教哲理に興味をもち深く信仰し、仏教哲理と囲碁理論を併説した「一
眼識八巻」という書を著すほどです。
謡曲、狂歌もたしなみ「国宝狂歌の千店」と名づけた狂歌集を発刊したり、「但馬図誌」、
「八々堂雑話」、「寝さ兎物語」、「臍車雑誌」などを書き上げています。
八々山人の最大の事業は、但馬全域を詳しく調べて作図した「但馬新地図」の作製で
す。
国内(但馬の国)踏破
安政二年(1855)の夏に「但馬国新図」を著します。八々山人53才の頃です。
但馬の全域を徒歩で、あるいは駕籠で矢立をたずさえ、村落、山野、沼沢を踏破して測
量し続けます。
ただ一人の力で方角地理を徹底的に測量するとともに、寺社、名所旧跡、歴代の興廃古
跡、奇石怪松のたぐいまで調べ、由来を考える作業です。しかも、それを全部木版に彫
りこんだ労作です。
但馬新地図
伊能忠敬が幕府の命を受け作製した日本地図は、海岸線を正確に測量した日本列島
の形です。
完成は文化十三年(1816)、山人14才の頃です。もちろん機密の図面なので目にする
ことなどあり得ません。
そんな時代に、八々山人一人で作った但馬新図は、海岸線はもちろん内陸部の詳細な
すべてを現す、現在のナビゲーションのような精巧なものです。
測量のため、日夜山野を一人で抜渉する姿は、探検家の間宮林蔵を思わせる異常なも
のだったと伝えられています。
木版刷りで出来上がった三尺四方両面7枚の地図には、高名な学者に添文や叙を書き
添えてもらい「但馬新地図」として発刊、大いなる賛辞が寄せられました。
名声は全国に
生野、久美浜両代官、出石、豊岡両藩主をはじめ、湯島に入湯逗留中の阿波の殿様
の目に留まります。さらに、江戸や水戸の殿様にも伝わります。但馬が生んだ勤皇の
志士・田中河内介の紹介で、中山大納言にも献上され、大納言を通じて天皇にも御覧
あそばれるまでになりました。
一介の村人の好奇心が高じて著した地図が、非常に珍重賞賛され、大名諸侯や公卿
をはじめ、天覧にまで供せられたことは、山人の新図作製がいかに偉業だったかを物
語っています。
江戸時代後期に、上郷には但馬の地図を精巧に作ったという人物がいたというお話で
す。
(国府村誌人物編を参考に書きました)















