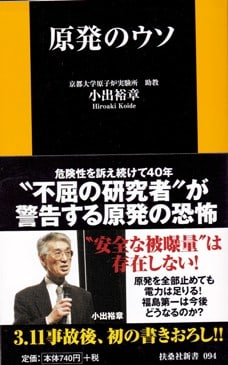先週は首都圏も久しぶりの大雪になりました。あちこちで交通機関がマヒし、路面凍結で歩くのさえかなり神経を使いました。でも、首都圏近郊の住宅地にある各地の公園に作られた雪だるまが元気な子供たちの姿(大人も作ったかもしれませんが・・・)を想像させてくれました。
さて、今回は「疲れすぎて眠れぬ夜のために」です。友人の一人の言葉を借りて言えばここ数年、家族という鉛の鎧がいつも肩にかかっているような状態の私です。でもその私に希望を授けてくれるのも広い意味での家族のような気がします。日中は忙しく動き回っているのに疲れすぎて眠れない状態に陥いることがあります。お守り代わりにかかりつけの医師から処方していただいている睡眠薬も「こんなことで依存症になってもたいへん」となかなか飲むことができず、ぼんやりしながら真夜中にPCを見ながらアマゾンで検索しているうちにこの本に行き当たりました。ちょっと違和感はあったのですが、ウチダ先生の本は何冊か読んだことがあったので、あまり迷わず購入しました。
手元に届いてみると何だか題名と内容とはニュアンスが違うような感じもしましたが、「まっ、眠れない夜にお読みくださいってことなのかな」と思いました。
最初は冒頭のページの「所有しないのが好きなんです。」という言葉に何となく共感して最後まで読み進めることとなりました。
というのは、何度も引っ越しを経験している私は、ウチダ先生のようにさっぱりした気持でいられないのでいつも大量の荷物に四苦八苦しながらの引っ越しです。日ごろから頭の中と家の中をすっきりさせたいというのが悲願だからです。ところが話はちょっと期待とは違う方向へ向かいました。
「心耳澄ませ無声の声を聴く」最初は多くの若者たちが直面している現実をおさらいするところから始まって、最後は家族を愛することへのメッセージへ導かれます。
「人間がどれくらいプレッシャーに弱いか、どれくらい付和雷同するか、どれくらい思考停止するか、どれくらい未来予測を誤るか・・・」私は極限的な貧困も人間性の暗部も見たことはありません。戦争を経験した親たちが築き上げた核家族の中で育ち、核家族の中で子供を育てました。結局人間はどれくらい弱い存在であるかをよく考え把握することができなければ、モラルや古いしきたりの意味をしっかり自分自身の心の中で消化することは難しいでしょう。
この本の中では資本主義社会に関する記述が何箇所かで出てきます。読みながら私は今は亡き父のことを思い出していました。資本主義とはなにか最初に聞いたのは父からでした。私が中学生の時でまだ東西の冷戦時代でした。父からは日本は資本主義社会であることどういう経済のしくみであるかというようなことを聴いたように思います。
実際20世紀の終わりにはベルリンの壁も崩壊し、ソビエト連邦もなくなって中国も市場経済を導入しました。戦争に行った経験を持つ父は「社会がどうのこうの言うよりそこに生きているのだから上手に社会のしくみを利用しなさい」というようなことを私が結婚して子供を持ってからも言っていました。付和雷同みたいに感じて、それでは社会は良くならないと反発したこともありましたが、確かに考えようによっては賢い生き方です。
「資本主義が目指すのは<たくさん生産する、たくさん流通する、たくさん消費する>ということただそれだけです。・・・中略・・・あえて一言でいえば<人間はそういうのが好き>だからというほかありません。」ウチダ先生の言葉は的確だと思います。でも一歩間違えばモラルの低い人間を量産してしまいます。
資本主義社会と人間社会のシステムの説明を受けて考えなくてはならないのは読者です。自由と制約をめぐる問題は結局人間一人ひとりの判断に委ねられますね。
「最強の幸福論」と解説者の銀色夏生氏はおっしゃっていますが、ウチダ先生の論理を本当に理解するには人生のそれなりの経験が必要でしょう。でもこの本にはどの世代の人々にとっても考えるためのヒントはたくさんあるような気がします。
さて、今回は「疲れすぎて眠れぬ夜のために」です。友人の一人の言葉を借りて言えばここ数年、家族という鉛の鎧がいつも肩にかかっているような状態の私です。でもその私に希望を授けてくれるのも広い意味での家族のような気がします。日中は忙しく動き回っているのに疲れすぎて眠れない状態に陥いることがあります。お守り代わりにかかりつけの医師から処方していただいている睡眠薬も「こんなことで依存症になってもたいへん」となかなか飲むことができず、ぼんやりしながら真夜中にPCを見ながらアマゾンで検索しているうちにこの本に行き当たりました。ちょっと違和感はあったのですが、ウチダ先生の本は何冊か読んだことがあったので、あまり迷わず購入しました。
手元に届いてみると何だか題名と内容とはニュアンスが違うような感じもしましたが、「まっ、眠れない夜にお読みくださいってことなのかな」と思いました。
最初は冒頭のページの「所有しないのが好きなんです。」という言葉に何となく共感して最後まで読み進めることとなりました。
というのは、何度も引っ越しを経験している私は、ウチダ先生のようにさっぱりした気持でいられないのでいつも大量の荷物に四苦八苦しながらの引っ越しです。日ごろから頭の中と家の中をすっきりさせたいというのが悲願だからです。ところが話はちょっと期待とは違う方向へ向かいました。
「心耳澄ませ無声の声を聴く」最初は多くの若者たちが直面している現実をおさらいするところから始まって、最後は家族を愛することへのメッセージへ導かれます。
「人間がどれくらいプレッシャーに弱いか、どれくらい付和雷同するか、どれくらい思考停止するか、どれくらい未来予測を誤るか・・・」私は極限的な貧困も人間性の暗部も見たことはありません。戦争を経験した親たちが築き上げた核家族の中で育ち、核家族の中で子供を育てました。結局人間はどれくらい弱い存在であるかをよく考え把握することができなければ、モラルや古いしきたりの意味をしっかり自分自身の心の中で消化することは難しいでしょう。
この本の中では資本主義社会に関する記述が何箇所かで出てきます。読みながら私は今は亡き父のことを思い出していました。資本主義とはなにか最初に聞いたのは父からでした。私が中学生の時でまだ東西の冷戦時代でした。父からは日本は資本主義社会であることどういう経済のしくみであるかというようなことを聴いたように思います。
実際20世紀の終わりにはベルリンの壁も崩壊し、ソビエト連邦もなくなって中国も市場経済を導入しました。戦争に行った経験を持つ父は「社会がどうのこうの言うよりそこに生きているのだから上手に社会のしくみを利用しなさい」というようなことを私が結婚して子供を持ってからも言っていました。付和雷同みたいに感じて、それでは社会は良くならないと反発したこともありましたが、確かに考えようによっては賢い生き方です。
「資本主義が目指すのは<たくさん生産する、たくさん流通する、たくさん消費する>ということただそれだけです。・・・中略・・・あえて一言でいえば<人間はそういうのが好き>だからというほかありません。」ウチダ先生の言葉は的確だと思います。でも一歩間違えばモラルの低い人間を量産してしまいます。
資本主義社会と人間社会のシステムの説明を受けて考えなくてはならないのは読者です。自由と制約をめぐる問題は結局人間一人ひとりの判断に委ねられますね。
「最強の幸福論」と解説者の銀色夏生氏はおっしゃっていますが、ウチダ先生の論理を本当に理解するには人生のそれなりの経験が必要でしょう。でもこの本にはどの世代の人々にとっても考えるためのヒントはたくさんあるような気がします。