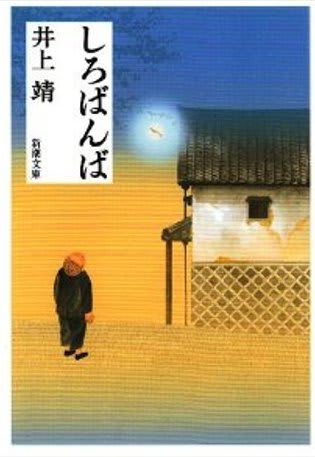日毎に暑さが厳しくなっていくように感じるこの頃です。先日、日本三大祭りの一つの京都の祇園祭で、去年から復活した後祭の山鉾巡行を見に行きました。先祭の山鉾巡行の方は大雨の中、強行されたようですが、後祭の方は夏らしい良い天気に恵まれ、「動く美術館」とも称される10基の山と鉾が都大路を進み、伝統的な京の町衆の美の世界の中に取り込まれていくようでした。
さて、今回はサマセット・モームの「月と六ペンス」です。作者も小説の題名もずっと以前から知ってはいましたが、最後まで読んだのは今回が初めてです。読書家の友人の一人が以前からサマセット・モームは読んでみる価値があると言っていたのをふと思い出し、一番有名そうなこの小説を読んでみることにしました。ポール・ゴーギャンがモデルということにも興味が湧きました。
1919年に発表された小説だそうです。もう100年近く前ですが、全く時代を感じさせない、人間の本質的なものを感じさせます。
ロンドンの株式仲買人、チャールズ・ストリックランドはある日突然仕事も家も妻子も捨て、芸術家としての道を歩み始めます。当然、最初からその生活は周りから見たら理解に苦しむばかりで金銭的にも悲惨なものです。ストリックランドの行動は気違いじみています。駆け出しの若き作家「わたし」、ストリックランドの妻、凡庸でお人好しの画家ストルーヴェとその妻ブランチ・・・・・。ストリックランドがタヒチに渡ったあとは回想形式ですが、絶妙なタイミングで現れる登場人物たちに助けられ、彼らの暮らしを犠牲にして生き抜くストリックランドの逞しさと美を求める生への凝縮のようなものを感じます。彼のような生き方は平穏な日常からはかけ離れています。ストリックランドの死は壮絶です。
ストリックランドの死後、彼の絵が世間に認められ、生前は二束三文としか思われていなかったものが法外な値で取引されるようになります。彼と関わった人々の関心は絵の芸術的価値ではなく、お金に換算していくらになるかが中心です。
訳者あとがきに
<タイトルについてだが、「(満)月」は夜空に輝く美を、「六ペンス(玉)」は世俗の安っぽさを象徴しているかもしれないし、「月」は狂気、「六ペンス」は日常を象徴しているかもしれない>とありました。
「月」は日本でも、ずっと昔から身近でありながら、未知の世界で幻想的なものでした。「かぐや姫」は「月」の世界の人だし、「枕草子」にも、「夏は夜、月のころはさらなり」とあります。アポロ11号が月に着陸して、月の石を持ち帰り、月には生命の痕跡がないことがわかりましたが、現実の夜空に浮かぶ星と共に肉眼で見る月は美しく感じます。
夜空に輝く月がこの小説の余韻を広げていっているようにさえ感じました。
さて、今回はサマセット・モームの「月と六ペンス」です。作者も小説の題名もずっと以前から知ってはいましたが、最後まで読んだのは今回が初めてです。読書家の友人の一人が以前からサマセット・モームは読んでみる価値があると言っていたのをふと思い出し、一番有名そうなこの小説を読んでみることにしました。ポール・ゴーギャンがモデルということにも興味が湧きました。
1919年に発表された小説だそうです。もう100年近く前ですが、全く時代を感じさせない、人間の本質的なものを感じさせます。
ロンドンの株式仲買人、チャールズ・ストリックランドはある日突然仕事も家も妻子も捨て、芸術家としての道を歩み始めます。当然、最初からその生活は周りから見たら理解に苦しむばかりで金銭的にも悲惨なものです。ストリックランドの行動は気違いじみています。駆け出しの若き作家「わたし」、ストリックランドの妻、凡庸でお人好しの画家ストルーヴェとその妻ブランチ・・・・・。ストリックランドがタヒチに渡ったあとは回想形式ですが、絶妙なタイミングで現れる登場人物たちに助けられ、彼らの暮らしを犠牲にして生き抜くストリックランドの逞しさと美を求める生への凝縮のようなものを感じます。彼のような生き方は平穏な日常からはかけ離れています。ストリックランドの死は壮絶です。
ストリックランドの死後、彼の絵が世間に認められ、生前は二束三文としか思われていなかったものが法外な値で取引されるようになります。彼と関わった人々の関心は絵の芸術的価値ではなく、お金に換算していくらになるかが中心です。
訳者あとがきに
<タイトルについてだが、「(満)月」は夜空に輝く美を、「六ペンス(玉)」は世俗の安っぽさを象徴しているかもしれないし、「月」は狂気、「六ペンス」は日常を象徴しているかもしれない>とありました。
「月」は日本でも、ずっと昔から身近でありながら、未知の世界で幻想的なものでした。「かぐや姫」は「月」の世界の人だし、「枕草子」にも、「夏は夜、月のころはさらなり」とあります。アポロ11号が月に着陸して、月の石を持ち帰り、月には生命の痕跡がないことがわかりましたが、現実の夜空に浮かぶ星と共に肉眼で見る月は美しく感じます。
夜空に輝く月がこの小説の余韻を広げていっているようにさえ感じました。