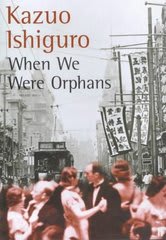
桜の便りが聞かれるようになった頃、積み重なった書籍の山を片づけていると、一冊の本が目にとまった。以前に読んだ本だが、なんとなくもう一度読みたくなり、仕事を放り出して読みふけってしまった。カズオ・イシグロの作品『わたしたちが孤児だったころ』When We Were Orphansである。いまや現代イギリス文学を代表する作家の一人であるイシグロの作品は好みでもあり、『女たちの遠い夏』、『日の名残り』、『充たされざる者』など、そのほとんどを読んできた。その名から推察されるように、この作家は日本人の血筋を受け継ぎながらも、生活の場であるイギリスの風土に溶けこんだ佳作を次々と生みだしてきた。
とりわけ、1989年のブッカー賞を受賞した『日の名残り』The Remains of The Dayは、イギリスらしい舞台装置と深い心理描写に大変感銘した。94年にケンブリッジに滞在していた時に、映画も見てしまい、さらにビデオまで買い込んだ。
イシグロの作品の中で、今回の小説『わたしたちが孤児だったころ』は、プロットにおいてもこれまでの作品とは、かなり趣きを異にし、この作家の非凡さをうかがわせる。広い意味では、イギリス伝統の探偵小説のジャンルに入るといえるが、きわめて特異な筋立てである。先ず『わたしたちが孤児だったころ』When we were orphans という意表をついたタイトルに驚かされる。しかし、読み進めるうちに、それが読者を含んだ現代に生きている「わたしたち」であることに気づかされる。
1930年代の上海
話は、ケンブリッジ大学を卒業した主人公クリストファー・バンクスの回想で始まる。バンクスは幼いころ上海に住んでいたが、10歳のころ、立て続けに両親が失踪し、一人自分はイギリスに送り返され、伯母の下で育てられ、名門ケンブリッジ大学を卒業する。両親失踪の原因は、1930年代当時問題となっていたアヘン貿易にからんでいたらしい。当時は、インドの阿片が中国に輸入され、中国の命運を左右するまでの大きな社会問題となっていた。バンクスが大学を卒業するまで両親の行方は確認できず、消息は深い霧の中に閉ざされていた。このことがトラウマとなって、バンクスは大学卒業後探偵となることを夢見る。そして、ロンドンを舞台に実際に探偵となり、大きな成功を収める。
横道にそれるが、イギリスでは探偵という職業は、社会的に高く評価されているようだ。シャロックホームズ、アガサ・クリスティなどの影響かもしれない。ケンブリッジ大学の卒業生が探偵 detectiveという職業を選択するについても、特に迷いはないようだ。事実、かつてカレッジ生活で親しくなったケンブリッジの学生から卒業したら、できれば探偵になりたいという話を聞いて、冗談ではないかと聞き直したことがあった。
さて、探偵となった主人公は、ロンドン社交界のパーティなどに出席して、上流社会の人々との交際を通して、職業上の情報を集めるとともに、有能な探偵としての社会的評判を獲得する。そして、舞台は1937年の上海に戻り、バンクスはすでに20年前に起きた両親の事件の解決に自らあたるという設定である。時は日中戦争が勃発し、騒然とした最中である。バンクスは探偵として、子供の頃の時代を求め、これまでの彼の人生を形づくり、そして歪めてきた過程を辿ろうとする。
わたしたちがたどった道
失われた過去への旅事件発生から20年も経ったというのに、両親がどこかに幽閉されているかもしれないと考え、戦乱で騒然、殺伐とした上海の世界へ戻ってゆく主人公はいかにも現実離れしている。イシグロはそれをわれわれが皆持っている「壊れてしまったものをもとに戻したいという欲求」に基づくものだという。これは、ある意味で、現代人、とりわけ若い世代が持っている「リセット」願望、あるいは既視感déjà-vuともいうべきものに近いのかもしれない。
バブルがはじけた90年代以降、日本のみならず、世界も激変を経験した。とりわけ、産業の盛衰は顕著で、それに伴い労働市場も大きく変わった。最近の日本では、大学卒業後3年間に、約3分の1が転職するという。1990年代以降、日本の労働市場は顕著な変貌を見せている。企業の盛衰の激しさも目を見張るばかりである。企業のみならず、個人間の競争も厳しさを増した。こうした実態を反映してか、自信を喪失したり、これからの人生をどう過ごすか戸惑っている若者が増えているようだ。
職業生活をスタートしたばかりと思われるのに、もう一度人生をやり直したいという感想を述べる人もいる。彼(女)らはできるなら、人生を「リセット」したいという。だが、リセットできるのは、小説の中だけなのだ。小説の根底に流れる思いは、探偵クリストファーが直面した過酷な体験から回避しようと、明るい未来を心に描くことに似ている。それは、現代という先の見えない不安な社会に生きている人間の思いなのだ。現代人は日々の現実がもたらす苦悩や疲れから逃れるために、幻想を抱く。いつかその幻想も現実の前にもろくも壊れるのだが。そのためにも、クリストファと同様に、わたくしたちも仮想の世界を必要としている。
イシグロは、現代人が持つ名状しがたい不安感を、一人の人間の失われた過去と記憶の旅を通して、見事に描き出している。表題が「わたしたち」とあるように、現代に生きているわたしたちは、過ぎ去った人生において精神的に取り戻したいなにかを抱えていることを、この佳作は絶妙なプロットを通して暗示している(2005年4月11日記)。
Kazuo Ishiguro. When We Were Orphans.London:Faber and Faber, 2000. (カズオ・イシグロ『わたしたちが孤児だったころ』 入江真佐子訳、早川書房、2001年)

























