『僕はなぜ小屋で暮らすようになったか』を読む (2/2)
―中世の西行を思い浮かべつつ
2
本書は、著者が現代の出家とも見なせる小屋暮らしをするようになったいきさつや著者の内面的な体験などが語られている。西行の時代に対応させれば、その出家の動機や出家後の生活を西行の場合とちがって外面からではなく内面から割と事細かに語ってくれていることになる。あるいはさらに普遍化させれば、わたしたちが他者(身近な人であれ、社会に浮上する事件の当事者であれ)の行動を推し量ろうとする場合のわたしたちが気掛けるべきことを暗示している。つまり、どんな他者の世界も、ということは自分の世界も、そんなに単純な道筋を経て現在の姿に到っているのではないということ。さらに一見そのことと矛盾するように見えるかもしれないが、この世界を日々生きているわたしたちは、それぞれ固有の色合いや性格を携えながらも誕生から生い育って死へという過程を誰もが一様にたどってゆくのだろうということである。
しかも、一般的には人は、内省することはあったとしてもそのような過程自体をごく自然なものとしてたどっていく。しかし、この著者の場合はその大多数が生活している「自然さ」に異和感を抱いている。また、誰もが何らかの形で持つのと同様であるが、著者によって事細かに内省的に語られても、著者が容易には触れ得ない無意識的な領域も存在する。著者の場合、それは日常性を振り切るような威力を持つ、〈死〉というものに過剰に引き寄せられ、引き回されることである。下の②に引用するように、そのことの起点としての小学生頃のイメージのようなものは描写されているが、おそらくその〈死〉への囚われは、もっと根深いもののように見える。そしてこのことは、西行の絶えず現世と出家後の仏教的な世界との間に引き裂かれ思い悩み、現世へ執着する心と似ている。
西行の歌を①と②に分けて引用したのと対応させて、本書の著者の言葉から取りだして、以下①と②に分類的に抽出する。
①
僕は遠い昔、むしろまったく逆の人間だった。人を真似したり、信じたりすることによって、無数の人々が構築してきた文明や文化の恩恵を享受する術を知っていた。しかし今や、自分の性格や思考様式はすっかり変貌してしまった。
それでも、なんとかやっている。僕は僕のままでちゃんと生きている。
小屋暮らしにはどの季節にもそれぞれのよさがあるが、あえて季節を一つ選ぶとするなら僕は冬を選ぶ。小屋を留守にしてどこかを彷徨っていることもしばしばだが、小屋を建ててから今まで、冬に小屋にいなかったことは一度もない。
朝、ロフトの寝床で目を開ける前に、雑木林ごと綿で包んだかのような静けさとほんのりとした暖かさに気づき、今日は特別な日だと感じることがある。目を開けて、ロフトの天窓が雪で覆われているのを確認し、「やはり」と思う。屋根に積もった雪が断熱材として機能しているのだ。かまくらの原理である。
顔を洗って外に出て、薪棚の前で今日はどれにしようかなと目をキョロキョロさせる。積まれている薪はあちこちからかき集めてきたもので千差万別てある。太いのもあれば細いのもあり、樹種も乾き具合も、表皮の厚さなんかも全然違う。なるべく相異なった太めの薪を三本ほど、たいがいサクラを一本、焚き付け用の細い小枝と一緒に抱えて小屋の中に戻る。
ストーブが稼働したら、パンを二枚焼く。薪ストーブの上で焼き網に乗せて焼くと輻射熱で中まで熱が通り、絶妙に焼ける。バターを塗って、こんがり焼いたベーコンを乗せて、塩胡椒を多めに振り、コーヒーと合わせて朝食とする。これは僕が冬の間中ずっと繰り返していたメニューである。
(『僕はなぜ小屋で暮らすようになったか』P144-P146 高村友也)
小屋は、舗装された道路からでこぼこの林道を数百メートルほど入ったところにある。……中略……
都会にいながら、「一人の時間」を確保するのは、そんなに難しいことではないかもしれない。喫緊の用事を済ませ、携帯電話の電源を切って、部屋の扉にカタリと鍵をかければ、何か思案に耽るにはとりあえず事足りる。
山小屋の「一人の時間」はそれとは少し異なる。部屋に鍵をかけ、外界を遮断して一人になるのではなく、外界と繋がったままにして一人なのだ。雑事を締め出し、雑念を追い払い、ようやく作り上げるかりそめの一人の時間ではなく、全体性を持った本物の一人の時間である。
この全体性こそ、わざわざ実際に土地を買って小屋を建てて、自分の生活そのものを捧げてまで欲しかったものである。
(『同上』P146-P147)
小屋には誰も呼んだことがない。
僕は一人でいるのが好きだ。何か趣味に没頭しているわけではない。何もすることがなくても、何ヶ月でも延々と一人でいられる。「一人」というのは、本当に心が安らぐ。
自分の中の最深部へ降りていったとき、そこに他人がいるか否か。そこに他人がいるという人は、安全地帯にも信頼できる他人が必要なのだと思う。僕の場合、そこには自分以外には誰もいない。
(『同上』P146-P147)
②
しかし、あえて一言で言うならば、「自由に生きる」ために僕はこの生活を選んだし、選ばざるをえなかった。
自由に生きるとはどういうことか。
それは、自分の中にあるものすべて投じて、自分自身に忠実に、全身全霊で生きるということである。もしも、自分の中のごく一部の能力、ごく一部の思考、ごく一部の人格のみによって、上っ面を撫でるような毎日しか送れないとしたら、それ以上の悲劇はない。 ことさらに自由を求める人が往々にしてそうであるように、そもそも僕は本来、自由とは正反対の性質を宿した人間である。とりわけ小屋を建てようと思っていた頃は、数多の抑圧を抱えて身動きが取れなくなっていた。
その抑圧の根底には、物心ついた頃からずっと考え続けてきた「自分の死」のイメージがある。いつか死んで永遠の無に溶け込むことを知っている自分と、今まさにこの瞬間に日常を生きつつある自分とが乖離していって、なんだか毎日に全人格を投じて生きられていないと感じるようになった。
自由に生きる。自分自身として生きる。そのためには、生と死のどちらをごまかすこともできない。自由に生きるとは、すなわち僕にとって、「死」というものまで包含しながら生きてゆくということだった。
(『同上』「はじめに」)
小学校の一年か二年か、そのくらいだっただろうか。はっきりとした年齢は覚えていない。
実家の二階の少し広い和室に布団を敷いて、いつものように一人で寝るところだった。橙色をした豆電球の明かりをぼんやりと眺めるともなしに眺めていて、いやもしかしたら目を瞑っていたような気もするが、突如、「僕はいつか死ぬんだ」と思った。次の瞬間、「そして永遠に戻って来ないんだ」と思った。
たった二秒か三秒のできごとだった。
そのとき、現実の存在物とまったく同等なリアリティを持って僕の脳裏に浮かんでいたのは、僕がいなくなった後の暗黒の宇宙と、百年、千年、一億年、……永遠に終わらない無限の時間だった。
僕は動悸を起こし、発汗し、震えていた。上半身を起こし、そのまましばらく掛け布団の青い花柄を見つめていた。
僕は消えてしまう。永遠に消えてしまう。怖い。絶対に嫌だ。
時間の感覚が消失し、僕を突き動かしていた「人生」という物語が消えた。自分の人生が、点のように小さくなってしまった。
この二秒か三秒足らずの経験によって、僕は、外界にまったく原因を持たない、日常生活という文脈から完全に切り離されたところからやって来る、純粋に内的な経験があることを知った。僕にとって決定的な経験であったにもかかわらず、時間的に前後の出来事と結びついておらず、何歳のことであったか定かでないのは、文脈がないからである。
その内的経験は、何か現実の存在物の抽象化といった過程を経て得られるのではない自立した「観念」と出会うこと、あるいは自身の中に最初から存在していたその観念に気づくことを意味した。
そして、その純粋に内的な存在であるはずの観念が、肉体に影響を及ぼしうるのだということを知った。
(『同上』P20-P22)
僕はひたすら、自分ばかりを見ていた。
―中略―
しかし、特定の誰かの視線ではない、誰の視線でもない視線があった。死の観念がもたらす、死の世界から見る視線だった。
(『同上』P58)
病気ではないことははっきりしているし、医者に症状を言えば病気と言われるであろうこともはっきりしているし、医者には治せないであろうこともはっきりしているし、症状が治ればいいという問題ではないこともはっきりしている。
(『同上』P171)
著者が、過去を振り返り、自らを内省し、「随所にその動機となった思いや経験をちりばめた」言葉の中から、わたしが大事と思うそのいくつかを抽出してみた。わたしは心の専門家でもない普通の平均的な世界を主に潜り抜けて来た者に過ぎないし、どこまでそれが可能かわからないけれど、できるだけ著者の心の在所に近づこうとしている。
抽出した①の群は、著者の小屋暮らしの描写の中から、わたしが特にいいなと思った部分である。たとえ不安の影が背に張り付いていたとしても、そこには万人が持つであろう、日々の細々とした生活の中で、穏やかに流れる時間があり、柔らかな眼差しや憩いや心安らぎがある。ここでは、人と人との関わり合いが希薄な、中世の「隠者」たちのような静けさがあるとしても、である。
②の群は、著者がなぜこのような小屋暮らしをするようになったかの動機の連鎖に当たっている。人は誰もが気づいたときには物心ついていて、誰々の家の子であり、どんな性格であり、という風になっている。どうして自分は感じ方や考え方や性格がこんななのだろうと嫌になったり、疑問に思うことは誰しも多少はあっても、それをたどる術がない。現在では、胎内の胎児の振る舞いが画像としてある程度わかるようになってきているとしても、その謎をたどる術がないように見えるのは変わりがない。ただ、わたしたち人の性格の核の部分の形成は、胎内から始まっていると言えそうである。そして吉本さんが明らかにした太宰治や三島由紀夫の乳児期の有り様から見れば、人の性格などの核の形成時期に相当する胎児期や乳児期という、人が絶対的な受動性であるほかない時期の生活の有り様が、無意識的な核として後々を大きく左右するほどとても大事であるということも言えると思う。
著者が、〈死〉というものに過剰に引き寄せられたり、占領されたりすることの起点として小学生頃のイメージを置いて描写している。著者に思い当たるのは、そのような唐突に訪れた体験であったのだろう。しかし、人の生まれ育ちの観点からすれば、誰もが通り過ぎてきたのに「そこに思い出せない記憶があるということはわかっている」(P37)とあるような漠然とした靄のような心の領域がある。わたしたちの性格の核の部分は、容易に気づくことのない、無意識的な領域に沈んでいるのだと思う。したがって、それは性格の核の部分が発した現象の一つなのかもしれない。付け加えれば、生まれて言葉をしゃべれるようになったまだ小さい頃なら、胎内の記憶を持っていてそれを語り出す子もいるらしい。
生きようとする意識にどこからともなく寄せてくる(ように見えたり感じられたりする)死の想念の波によって、著者の生存の感覚や意識は、今・ここに・生きているという現存性と、「世界をどこか遠くの上の方から眺める人格」(P95)とに二重化する。したがって、引き裂かれた分裂感(乖離感)を味わい続けることになる。
ところで、ここで個としての心や魂の場所から視線を引いて見る。
鎌倉期に多くの新仏教が起こり活動的になったということは、当然ながらそれ以前からの胎動があったということになる。平安末から鎌倉期にかけて、飢饉や病や戦さなど世の中のどうしようもないほどの惨状を目の当たりにして、また時代の激動と流行思想に押されるようにして、現世から出家遁世する者たちがいた。彼らは仏教の修行をしながら、西行のように文学(歌)に力を入れた人々もいた。これらの後に隠者と呼ばれる人々が、どの位の規模で存在していたのかは分からないけれども、この一群の人々が鎌倉期の新仏教への流れに大きく関係しているはずだから、社会的に無視し得ないような規模としてあったと思われる。例えば、西行の絶えず自らの生存の有り様を問い続ける歌のように、この一群の人々は、流行や流行思想に乗りながら、この世界から外れるようにしてその存在自体によって、この世界やそこでの人の生の有り様を照らし出していたはずである。
同様に、現在の著者のような生活する人々や「ニート」と呼ばれる人々まで含めると、この社会から一歩退いて生きる人々は、割合から見ても無視できない規模だと思われる。かれらを共通の地平で捉えれば、個々人の動機の違いは様々でも、自分の存在に対する何らかの否定性が普通以上に強いのかもしれない。これを社会との接触の面で見れば、本人たちの自覚としては希薄でも生き難い社会として否定性として見なされているはずである。このような動向や、例えば社会の現状に対応して社会で進行している葬式の有り様の変貌(家族葬の増加や葬式の簡素化)などが、徐々にこの社会を突き動かし変貌させていくのだろうと思う。もちろん、それらの大本には、わたしたちが関わり呼吸するこの社会の産業的な構成の更新があり、それに促されて変貌が現象してくる。
最後に、著者の場所に戻る。
普通、人々は、人間関係でひどい目に遭ったとか大きな難題に出くわしたときとかはあり得るとしても、学者や研究者や表現や思想などに入りこみすぎた者でなければ、日々生きていること自体を意識的に、継続的に問うたり、追い詰めていたりはしない。著者の場合は、生きていく上で大きな難題に魅入られてしまったから、避けられない形で小屋住まいという生活の形の有り様や本書の言葉として結んできたのだろう。
著者が力こぶを入れている(入れざるを得ない)ように見える哲学的な言葉は、ほんとうは彼の生存の条件から強いられたものにすぎないのではないかと思う。つまり、彼の生存の固有の条件が、哲学的な言葉を引き寄せ、哲学への関心へと押し出した。著者がどこかで哲学自体にそんなに関心があるわけではない、と記していたように思うが、ほんとうは、自らの魂の在所にわずかでも光が差し込んで、その心から精神に渡る乖離やこわばりがほどけていけばいいのだろう。それが第一に願われていることだろうと思う。
このように、思い悩むのは人であれば例外はないけれども、著者のように重たい課題を抱えてしまった人々も居るのだろう。その背負ってしまった重たい課題は簡単には解けてしまわないと思われるが、日々の生活の具体性を生きくり返す中から、いい小径ができて、心穏やかな時間が十分に持てるようになったらいいねと願うばかりである。お節介ではあるが、わたしから見ると著者は潔癖すぎる印象だ、もっと生活過程でのいいかげんさも大切にされたらと思う。
引用②の最後に、「病気」についての捉え方が記されている。坂口恭平『家族の哲学』の中の、作者が深く流れ込んでいると思える躁鬱を抱えた〈私〉もまた、この著者と同様な病の捉え方をしていた。この捉え方には、外からはいかにささやかにみえようと日々積極的に自由に生きようとする著者たちの、悪戦苦闘と生存の意志が込められている。
最新の画像[もっと見る]
-
 画像・詩シリーズ #15 田んぼの現在から
4日前
画像・詩シリーズ #15 田んぼの現在から
4日前
-
 水詩(みずし) #6
7日前
水詩(みずし) #6
7日前
-
 水詩(みずし) #5
1ヶ月前
水詩(みずし) #5
1ヶ月前
-
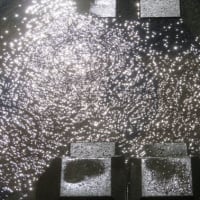 画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
1ヶ月前
画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
1ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
2ヶ月前
-
 水詩(みずし) #4
2ヶ月前
水詩(みずし) #4
2ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます