新庄の特別な朝、そんな気にもなろうというもの、絶妙な量の朝霧が陽の光に輝いています。
裏庭と裏の畑越しの新庄の野山、何と贅沢なことでしょう。

量子論と尺八と倍音
今読んでいる中村明一著の「倍音」、とても興味深いことがつづられています。
著者は、大学では量子化学を専攻しながら、尺八奏者として世界で活躍している変わり種。
でも、量子論と尺八、“倍音”という言葉でつながるかも、などと思ったり。 倍音には整数次倍音と非整数次倍音とがあるそうですが、日本人と日本以外の人はその感じ方、捉え方が違うというのです。
倍音には整数次倍音と非整数次倍音とがあるそうですが、日本人と日本以外の人はその感じ方、捉え方が違うというのです。
かつて、東京医科歯科大学教授の角田忠信氏は、日本語を母語とする人は言語を左脳で理解するが、日本語を母語としない大半の人は右脳で理解するという研究を発表し、右脳、左脳論が世論を賑わしましたが、倍音の感じ方も全く違う。
“密息”と感性
この本を読み進んで、“密息”という言葉に出会ったのですが、日本人が持っていた“密息”という呼吸法は、日本の風土や生活様式と深くリンクし、日本人の深い精神性や身体性を育んできていたんですね。
母音を基本とする日本語も、日本の高い湿度による豊かな自然に育まれて形成され、その環境故の豊かな整数次倍音と非整数次倍音の奥深で豊かな音楽が生まれ、愛されてきた。
美空ひばりや森進一、都はるみ、八代亜紀、浜崎あゆみ、宇多田ヒカルなども、当然にして日本人が好む歌声だとか。
急峻な地形風土と和服という文化故に持っていた複式でもなく胸式でもない“密息”という呼吸法は、身体性を高め、身体の受信感度を高め、「間」の感覚を生み出して来たと。
私たちの祖先が育んできた日本という国の持つ素晴らしさ、それ故に獲得してきた日本人の素晴らしい感性や身体性を、今どんどん捨ててきているのではないでしょうか?
私たちは、そんな大切なものをもう一度見直していきたいものだと思いました。
よく知らなかった“倍音”という言葉に、なぜだか反射的に反応して衝動買いしてしまったこの本ですが、きっと、僕の持つ受信機が感応した結果だったのでしょうね。










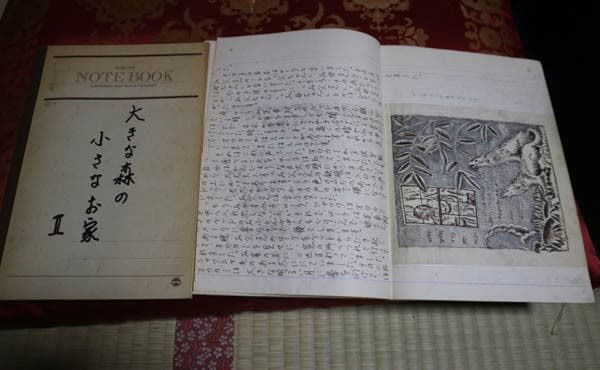




 話は変わって、今朝の新聞を見て、え~~!!なにこれ、でもきっとそうだろうなあ。
話は変わって、今朝の新聞を見て、え~~!!なにこれ、でもきっとそうだろうなあ。