今回は、音楽記事です。
このカテゴリーでは、リトル・リチャード、チャック・ベリーと、50年代アメリカンロックのレジェンドについて書いてきました。
その流れで、満を持してエルヴィス・プレスリーについて書きましょう。
エルヴィス・プレスリー。
それこそ、もう誰でも知っているアーティストでしょう。ラブ・ミー・テンダーなんかは、誰しも一度は聴いたことがあるはずです。
ラブ・ミー・テンダーが実は“カバー曲”だというのは以前一度書きましたが……エルヴィスさんは他のアーティストのカバーを結構やっていて、たとえばサイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」や、CCRのProud Mary なんかをやっています。チャック・ベリーの Johnny B Goode もやってました。
チャック・ベリーの
Roll Over Beethoven
から、“ロックとは新陳代謝である”と前回の音楽記事で論じましたが……エルヴィス・プレスリーという人は、その新陳代謝としてのロックを象徴する存在でもあります。
今でこそエルヴィスは「古き良きアメリカ」みたいなイメージでみられていると思いますが、出てきた当初は“良識ある大人”たちから猛烈なバッシングを受けていました。
その一つの原因は、黒人音楽と白人音楽を融合させたことといわれます。
デビュー前のエルヴィスはトラック運転手をやっていて、アメリカの広範囲を走り回っていました。車中でラジオを聴いていると、北のほうを走れば白人音楽、南の方を走れば黒人音楽が耳に入ってきます。それらを混淆して、エルヴィスの音楽が生まれたわけですが、それを気に食わない人もたくさんいました。なにしろ公民権運動よりも前の時代ので、白人と黒人はバスの座席も別々というのが普通だったころ。そんな時代に、白人と黒人の音楽を融合するなどというのはけしからんという人がいたのです。
そして、あのダンス。
あの動きは、一説にストリッパーのダンスをモチーフにしているともいいます。それがやはり、当時の良識ある大人たちからはけしからんとみられました。マーティー・フリードマンさんがいうには、エルヴィスは、当時のアメリカ社会にとって、後の時代のマリリン・マンソン以上に過激なものと受け取られていたのだそうです。
トレードマークのリーゼントも、やはりバッシングの対象となりました。
大学の学生がエルヴィスの髪形を真似したりすると、体育会系の学生がやってきてバリカンで丸刈りにするなんてことが行われていたといいます。
そんな具合で、エルヴィスの人形を燃やすとか、レコードを広場に集めて踏みつぶすとか、そんなことが全米各地であったのだとか。
フランク・シナトラはエルヴィスを酷評し、エド・サリヴァンは、あんなやつ絶対に自分のショーには出さないといっていました。
今から考えると、エルヴィス・プレスリーがそんな扱いを受けていたというのはちょっと想像しがたいでしょう。
それこそまさに、私が以前ベートーベンの記事で書いたことなんです。
エルヴィスは、新たな地平を切り拓いた。そしてそれが、新しいスタンダードとなった。ゆえに、後の時代からみると、そんなバッシングを受けてたなんてことが信じられなくなるわけです。
そして、さらに時代が進むと、チャック・ベリーがベートーベンをぶっ飛ばせと歌ったように、新たなスタンダードを覆そうという動きが出てきます。
それはすなわち、私がいう第三世代ロック――パンクです。
クラッシュが、1977という歌を歌っています。
1977年には、エルヴィスもビートルズもローリング・ストーンズもいらない
と歌うこの歌は、それ以前の世代を否定して新たな地平を切り開こうとする、まさに新陳代謝です。
1977年というのは、まさにエルヴィスがこの世を去った年ですが、こういうかたちで世代の交代を表明しているということでしょう。
これは、クラッシュのサード・アルバム、LONDON CALLINGの有名なジャケット写真。
ポール・シムノンがベースを破壊するこのジャケットは、エルヴィス・プレスリーのデビュー・アルバムのジャケットのパロディになっています。
ここに、新陳代謝の意味合いが現れているのではないかと思います。
ただしそこには、単純にエルヴィスを旧世代の存在として否定しているわけではないという複雑な関係もあるかもしれません。
この点について、『監獄ロック』という映画が非常に示唆に富んでいます。
「監獄ロック」は、エルヴィスの代表曲の一つですが、それをタイトルにした映画。エルヴィス自身が、刑務所上がりのミュージシャン、ヴィンス・エヴァレットという役で主演しています。
この映画を観ていると、出所したヴィンスが酒場で歌を歌っている場面で、騒がしい客の態度に切れて、ギターをテーブルにたたきつけて破壊するというシーンが出てきます。
そのシーンをみて、私ははっとさせられたわけです。
ギター破壊といったら、これはパンクスたちのお家芸ではないか――と。
以前フーの記事を書いたときに、ギター破壊のパフォーマンスを最初にやったのはピート・タウンゼントではないかと書きましたが、実は、1957年の映画のなかで、エルヴィスがすでにそれをやっている。
もっというと、同じ『監獄ロック』のなかで、ヴィンス・エヴァレットは、みずから音楽会社を設立します。デモ音源をもって大手レコード会社をまわるも色よい返事をもらえず、自分で音楽会社「ローレル」を設立し、そこからレコードを発表するのです。
自分でレコード会社を作る……そう、これもまた、パンク的DIY精神の発露にほかなりません。
このブログで何度か書いてきましたが、パンク/ハードコア系のバンドは、みずからレコード会社を作るということをよくやります。それは、既存の権威に対して反旗を翻すことであり、旧世代が規定する価値観に従わないということなのです。そのパンクスたちにといって否定する対象であるはずのエルヴィスが、映画のなかとはいえ、パンクスたちと同じことをやっているのです。
そんなふうに考えると、LONDON CALLING のジャケットもちょっと違った見え方が出てきます。
エルヴィスのアルバムジャケットをパロったジャケットで、エルヴィスが映画の中でやったギター破壊をやる。
これはすなわち、エルヴィスを否定することが、すなわちエルヴィスを継承することになるんじゃないか……そんなことを表現しているとも思えてきました。
せっかくなんで、曲のほうの「監獄ロック」の動画を公式YouTubeチャンネルから貼り付けておきましょう。
Elvis Presley - Jailhouse Rock (From '68 Comeback Special)
思えば、ここで監獄を題材にしているのは、プリズンソングの残響でしょう。
囚人をモチーフにしたプリズンソングは、ブルース、ロックの源流の一つです。そうすると、クラッシュがソニー・カーティスの曲をカバーした
I Fought the Law
なんかともつながってくるように思えます。
既存の価値体系のなかでは、新しく出てくる表現は異端扱いされます。それを“囚人”という姿に仮託しているのではないか……だとするならば、エルヴィスとクラッシュは、じつはまったく同じ立ち位置にいるともいえます。クラッシュの1977を聴いたジョニー・ロットンが「クラッシュの連中はエルヴィスのパート2じゃねえか」といったそうですが、それは――ジョニーの意図とは違った意味で――正しいのかもしれません。
以前の音楽記事で私は「ベートーベンもチャック・ベリーもロックだ」といいましたが……それと同じように、エルヴィスもクラッシュもロックなのです。











![ELVIS PRESLEY [12 inch Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/510ZVhBoL5L._SL160_.jpg)


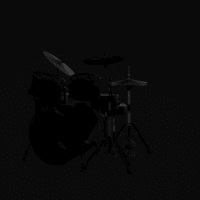








にしても監獄ロックって曲のヴォーカルはいつ聴いてもパンクだなあと思います。ギターにディストーションがかかる前は、みんな歌声の破壊力で勝負していたような気がしますね。
ギターにディストーションが架かる前は歌声の破壊力で勝負していた……たしかに、そういう側面はあるかもしれませんね。
パンクと呼びうるような音楽は、さかのぼっていけばロックが誕生したのとほぼ同時に生まれていたんじゃないかとも私は思っていて……このあたりは掘り下げていくと面白いかもしれません。