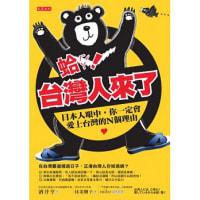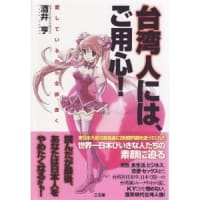中東紀行関連でついでにk.m.p.『エジプトがすきだから』(角川文庫、2003年)を読んだ。これがオモロイ!最近読んだ本で、これほど「うんうん、そうだよなあ」と声に出して、笑いこけながら読んでものはない。もとは1996年にJTBから出た単行本だが、安い文庫のほうを買った。ただ字を縮小しているから読みにくいが。
著者は女性漫画家?「なかがわ みどり」と「ムラマツ エリコ」の二人組だ。
エジプトで安宿に泊まり、庶民にもみくちゃにされて、よく怒鳴ったり切れたりしながら、それでもエジプトの面白さと魅力を漫画付きで描いている。
ところで、「そうだよなあ」と書いたが、私自身はまだエジプトに行ったことはない。だが、ここに描かれているエジプトの、日本人から見ての不条理さ、のんびり、むかつく部分は、台湾にも(今はずいぶん少なくなったといえ)、レバノンにも、その他いわゆる「先進国ではないが、飢餓でもない」世界の多くの地域に共通しているものだといえるからである。
たとえば24ページに「人をひきそういになって大爆笑する家族」が漫画とともに描かれている。25ページには「全然知り合いでもなんでもないのに乗ったとたんポケットの豆をあげる。そのあとは、おりるまでずーっと旧知の友のようにおしゃべり」するタクシードライバーと客。26ページ、街を歩く人の服の観察では、「カラフルな人、まっ黒な人、顔隠してる人、キマってる人、やぶけてる人、寝間着みたいな人」。
アザーンではある日、「でも今日のアザーンは、何だか変だ。おじさん、のどの調子が悪いのか、途中で咳き込んではゼーゼーしてる。タンを吐く音がスピーカーを通して町中に響く」(33ページ)。
アレキサンドリアの水族館(52ページ)では4コマ漫画で最初は「水がのごってみえない」、2コマ目「あ、死んでる」。3コマ目に「死んでる。苦しんでる。くさってる」。4コマ目の解説で「どう見ても何もいない水槽。苦しそうにあえぐ魚たち。水流でぐるぐる回りつづける死がい。こんな悲しい気持ちになる水族館ははじめて。魚が苦しんで死んでいく様子を観察するには、オススメの水族館です」。
同じページに道端で野糞する女性が、「あっ、ヤバーニー、ハロー、ハロー」と挨拶してくる場面。
60-61ページで「しつこいこども」に、「子供がまとわりついて、まともに歩けない・・・・ムシすると石投げたり、ずーっとやってる。胸ぐらつかんでブンブンふり回したら逃げていったが、子供にこんなことをしたのは、はじめてだ」とあって、悪がきに切れるのは25ページや112-113ページにも出てくる。確かにあれじゃむかつくだろうな。
63ページでは「両替するだけなのに40分」として、窓口の職員が冗談をいって同僚を笑って仕事を進めない場面。
114ぺージで、いろんなペテン師の話で「登場の基本」として、「日本語で話しかけてくるやつは99%あやしい」として「あやしいもんじゃないよ」とのせりふに「あやしいもんがよく使うセリフ」と突っ込みを入れている。
140ページ。エジプトで「おしん」が人気があったころ、日本人と見ると、みんなで取り囲んで指をさして「おしーん」。「ある日数えてみたら、1日107回」。
ほかにも、「うん、うん、これはあるね」みたいな爆笑話が盛りだくさん。
まあ、日本が特殊というかあまりにも近代化しすぎて、こうした「怒ったり笑ったりが激しくて、今何考えてるのかすぐわかっちゃう、人間臭い人たち」(25ページ)を失っただけなのだろう。それを著者たちも伝えようとしている。
そういう点で、これは「エジプト」だけを描いたものではない。近代化が進む以前の都市文化、人間関係を普遍的に描いたものだといえる。だからこそ面白いのだ。
著者は女性漫画家?「なかがわ みどり」と「ムラマツ エリコ」の二人組だ。
エジプトで安宿に泊まり、庶民にもみくちゃにされて、よく怒鳴ったり切れたりしながら、それでもエジプトの面白さと魅力を漫画付きで描いている。
ところで、「そうだよなあ」と書いたが、私自身はまだエジプトに行ったことはない。だが、ここに描かれているエジプトの、日本人から見ての不条理さ、のんびり、むかつく部分は、台湾にも(今はずいぶん少なくなったといえ)、レバノンにも、その他いわゆる「先進国ではないが、飢餓でもない」世界の多くの地域に共通しているものだといえるからである。
たとえば24ページに「人をひきそういになって大爆笑する家族」が漫画とともに描かれている。25ページには「全然知り合いでもなんでもないのに乗ったとたんポケットの豆をあげる。そのあとは、おりるまでずーっと旧知の友のようにおしゃべり」するタクシードライバーと客。26ページ、街を歩く人の服の観察では、「カラフルな人、まっ黒な人、顔隠してる人、キマってる人、やぶけてる人、寝間着みたいな人」。
アザーンではある日、「でも今日のアザーンは、何だか変だ。おじさん、のどの調子が悪いのか、途中で咳き込んではゼーゼーしてる。タンを吐く音がスピーカーを通して町中に響く」(33ページ)。
アレキサンドリアの水族館(52ページ)では4コマ漫画で最初は「水がのごってみえない」、2コマ目「あ、死んでる」。3コマ目に「死んでる。苦しんでる。くさってる」。4コマ目の解説で「どう見ても何もいない水槽。苦しそうにあえぐ魚たち。水流でぐるぐる回りつづける死がい。こんな悲しい気持ちになる水族館ははじめて。魚が苦しんで死んでいく様子を観察するには、オススメの水族館です」。
同じページに道端で野糞する女性が、「あっ、ヤバーニー、ハロー、ハロー」と挨拶してくる場面。
60-61ページで「しつこいこども」に、「子供がまとわりついて、まともに歩けない・・・・ムシすると石投げたり、ずーっとやってる。胸ぐらつかんでブンブンふり回したら逃げていったが、子供にこんなことをしたのは、はじめてだ」とあって、悪がきに切れるのは25ページや112-113ページにも出てくる。確かにあれじゃむかつくだろうな。
63ページでは「両替するだけなのに40分」として、窓口の職員が冗談をいって同僚を笑って仕事を進めない場面。
114ぺージで、いろんなペテン師の話で「登場の基本」として、「日本語で話しかけてくるやつは99%あやしい」として「あやしいもんじゃないよ」とのせりふに「あやしいもんがよく使うセリフ」と突っ込みを入れている。
140ページ。エジプトで「おしん」が人気があったころ、日本人と見ると、みんなで取り囲んで指をさして「おしーん」。「ある日数えてみたら、1日107回」。
ほかにも、「うん、うん、これはあるね」みたいな爆笑話が盛りだくさん。
まあ、日本が特殊というかあまりにも近代化しすぎて、こうした「怒ったり笑ったりが激しくて、今何考えてるのかすぐわかっちゃう、人間臭い人たち」(25ページ)を失っただけなのだろう。それを著者たちも伝えようとしている。
そういう点で、これは「エジプト」だけを描いたものではない。近代化が進む以前の都市文化、人間関係を普遍的に描いたものだといえる。だからこそ面白いのだ。