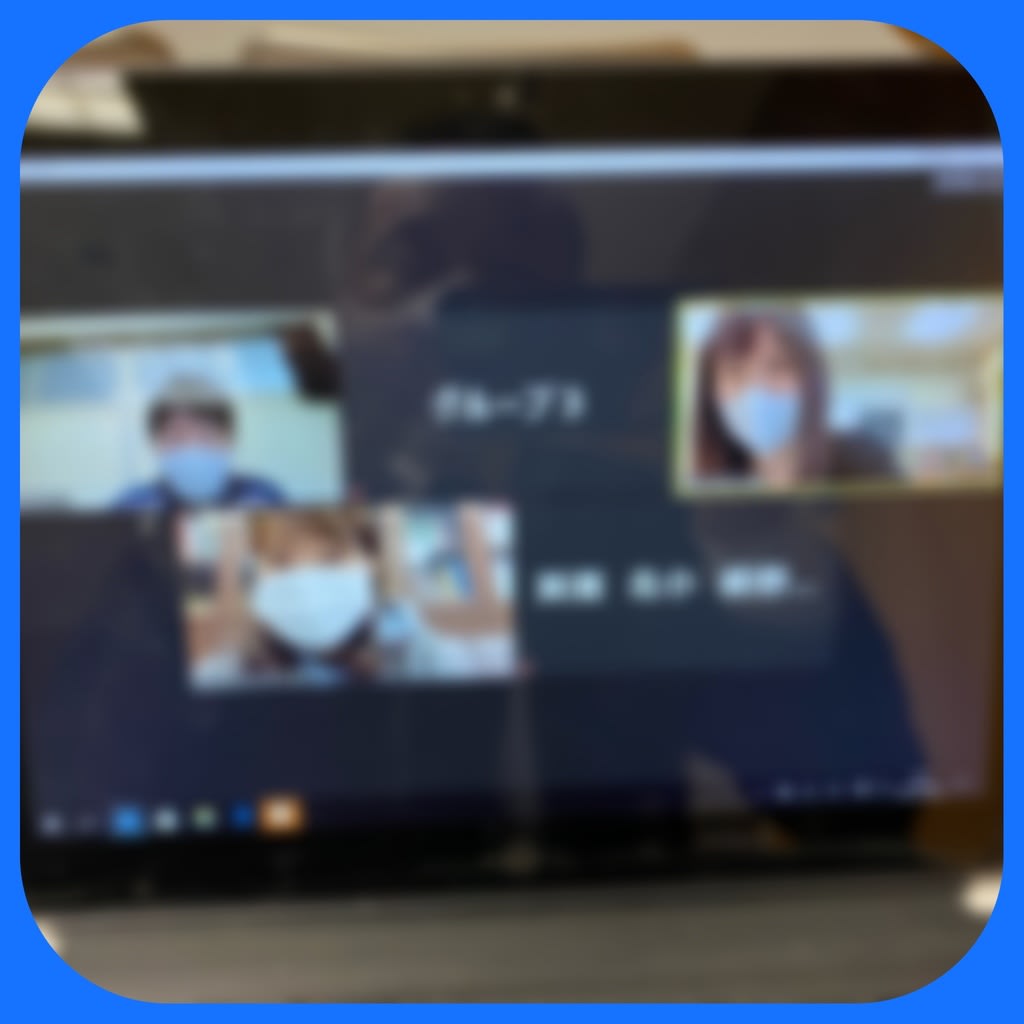コロナ渦により、学校教育の領域にも、オンラインが普及しました。
もちろん、教育ではオンラインが万能というわけではなく、教師と児童生徒、児童生徒同士の対面した活動が必要なのは言うまでもありません。
ただ、不登校の子どもたちにはオンラインの教育的かかわりが有効なこともあるようです。
不登校の子は通常学校に来るのが難しい状況にあります。学校に来れれば、教室に入れなくても、別室で学習課題に取り組むことで、学習活動が実現できます。
しかし、学校に来れない子の場合、学校で学習課題に取り組むことができません。
そんなとき、家庭にいながら、学校の教師と家庭にいる児童生徒がオンラインでつながれ、教材に取り組むことができますし、わからないところを教師に聞くことができます。
教師も、支援したり、教えたりすることができます。
じっさい、オンラインを使い、学校に来られず家庭にいる子が、オンラインで学習できている例も増えました。
ただし、不登校の児童生徒の支援には、子どもが安心できる居場所の提供と、何でも話すことができる人間関係が欠かせません。
不登校の子どもの支援は、おとなが子どもとの信頼関係を築くことが始まりになります。
そのための家庭訪問は必要です。
そこから信頼関係を広げ、オンラインでコミュニケーションをはかり、それからオンライン学習へ移行していきます。
個に応じた支援や学びを、オンラインが開くことになります。
オンラインを使うと、学校の教師は定期的に継続して子どもに声かけができます。
それは子どもにとって、教師という家族以外の人と話ができることになります。
その積み重ねにより、学習へと導いていくことができます。
ただし、オンラインは過渡的な支援であり、その先にはリアルに人とつながり、学校に来られるようになることを、学校はねらいにすべきでしょう。