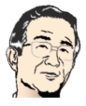14日、立命館大阪キャンパスで、立命館プロムナードセミナー「木津川 計/優しさとしての大阪文化」第5回「たおやかで一筋な道-森南海子と岡部伊都子のこころ-」を受講しました。内容は以下の通りです。
1、社会化された大阪の女像-”大阪のおばちゃん”の原型
文芸の中やテレビの中の大阪の女性のイメージが良くなく、それが大阪の女のイメージとなっている。
1)文芸の中の女
①小田作之助『夫婦善哉』の蝶子は知恵も才覚もあるが、インテリジェンスがない。
②山崎豊子『花のれん』は吉本興業創始者の吉本せいがモデル。直木賞受賞の時に「船場商人のど根性を描きたかった」と述べた。これが大阪の”ど根性”の始まり。
③菊田一夫『がめつい奴』のお鹿ばあさんはがめついことで評判。舞台や映画、テレビによって「がめつい」が全国に知られた。
2)テレビの中の女
①役者・タレント-浪花千栄子は賢い女性、大屋政子はド派手で有名、和田アキ子は芸能界の女帝、上沼恵美子は西の女帝と呼ばれ奔放な物言い。
②歌手-天童よしみ「道頓堀人情」、中村美津子「河内おとこ節」にはど根性の坂田三吉が出てくる。
2、岡部伊都子-日常の機微から大きなものへ
「おむすびの味」で認められ、日常生活のなかの伝統美をこまやかな感性でとらえた作品で人気を得た。戦争や差別にするどい視線を向けた著作もある。
1)『おむすびの味』と女人歳時記『暮しのこころ』
2)美なるものへの憧れ-『観光バスのいかない・・・・』から出発
3)『あこがれの原初』と差別への開眼
4)沖縄-鎮魂と反戦への祈り
3、森南実子-流行に背を向け、小さきものへ
リフォームのデザイナーとなり手縫いやリフォームを推奨し、手縫いの伝統をたずねて全国各地を歩く。身障者のためのデザインや点字の洋裁手引き書なども手がける。『千人針』の著作がある。
1)「リフォーム」の編み出しと「もたいない」の先駆け
2)少数派への視座と千人針への痛恨
3)沖縄-再生と平和への願い
1、社会化された大阪の女像-”大阪のおばちゃん”の原型
文芸の中やテレビの中の大阪の女性のイメージが良くなく、それが大阪の女のイメージとなっている。
1)文芸の中の女
①小田作之助『夫婦善哉』の蝶子は知恵も才覚もあるが、インテリジェンスがない。
②山崎豊子『花のれん』は吉本興業創始者の吉本せいがモデル。直木賞受賞の時に「船場商人のど根性を描きたかった」と述べた。これが大阪の”ど根性”の始まり。
③菊田一夫『がめつい奴』のお鹿ばあさんはがめついことで評判。舞台や映画、テレビによって「がめつい」が全国に知られた。
2)テレビの中の女
①役者・タレント-浪花千栄子は賢い女性、大屋政子はド派手で有名、和田アキ子は芸能界の女帝、上沼恵美子は西の女帝と呼ばれ奔放な物言い。
②歌手-天童よしみ「道頓堀人情」、中村美津子「河内おとこ節」にはど根性の坂田三吉が出てくる。
2、岡部伊都子-日常の機微から大きなものへ
「おむすびの味」で認められ、日常生活のなかの伝統美をこまやかな感性でとらえた作品で人気を得た。戦争や差別にするどい視線を向けた著作もある。
1)『おむすびの味』と女人歳時記『暮しのこころ』
2)美なるものへの憧れ-『観光バスのいかない・・・・』から出発
3)『あこがれの原初』と差別への開眼
4)沖縄-鎮魂と反戦への祈り
3、森南実子-流行に背を向け、小さきものへ
リフォームのデザイナーとなり手縫いやリフォームを推奨し、手縫いの伝統をたずねて全国各地を歩く。身障者のためのデザインや点字の洋裁手引き書なども手がける。『千人針』の著作がある。
1)「リフォーム」の編み出しと「もたいない」の先駆け
2)少数派への視座と千人針への痛恨
3)沖縄-再生と平和への願い