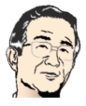新現役ネット【関西】のイベントで産經新聞社大阪本社を見学しました。24名が参加しました。
 11時15分、地下鉄御堂筋線「なんば駅」出口で待ち合わせました。先ず、行列のできる店「魚匠 銀平」道頓堀店で定番外特製昼食を食べました。昼食後に産經新聞大阪本社まで20分ほど歩き、13時に到着しました。
11時15分、地下鉄御堂筋線「なんば駅」出口で待ち合わせました。先ず、行列のできる店「魚匠 銀平」道頓堀店で定番外特製昼食を食べました。昼食後に産經新聞大阪本社まで20分ほど歩き、13時に到着しました。
大阪本社新社屋の玄関で記念写真を撮影しました。会議室で、産經新聞社の歩みと産經新聞のできるまでの簡単な説明を受けた後に、「産經新聞のできるまで」のビデオを鑑賞しました。そして、編集局、写真報道局そして制作局のフロアを順次見学しました。各フロア見学後に会議室に戻り質疑応答を行い16時に解散しました。
「新現役ネット会員24人 大阪産経新聞社を見学」と題した記事と写真(玄関で撮影したもの)を掲載した本日付夕刊の1面(もちろん市販はしません)を頂きました。ちなみに、1面のトップは北朝鮮党代表者会での「ジョンウン氏、指導部入り」です。
 11時15分、地下鉄御堂筋線「なんば駅」出口で待ち合わせました。先ず、行列のできる店「魚匠 銀平」道頓堀店で定番外特製昼食を食べました。昼食後に産經新聞大阪本社まで20分ほど歩き、13時に到着しました。
11時15分、地下鉄御堂筋線「なんば駅」出口で待ち合わせました。先ず、行列のできる店「魚匠 銀平」道頓堀店で定番外特製昼食を食べました。昼食後に産經新聞大阪本社まで20分ほど歩き、13時に到着しました。大阪本社新社屋の玄関で記念写真を撮影しました。会議室で、産經新聞社の歩みと産經新聞のできるまでの簡単な説明を受けた後に、「産經新聞のできるまで」のビデオを鑑賞しました。そして、編集局、写真報道局そして制作局のフロアを順次見学しました。各フロア見学後に会議室に戻り質疑応答を行い16時に解散しました。
「新現役ネット会員24人 大阪産経新聞社を見学」と題した記事と写真(玄関で撮影したもの)を掲載した本日付夕刊の1面(もちろん市販はしません)を頂きました。ちなみに、1面のトップは北朝鮮党代表者会での「ジョンウン氏、指導部入り」です。