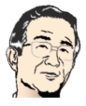15日、大阪市立大学文化交流センターで、「都市大阪のこれから」の第2回「下水の熱を使う」を受講しました。講師は大阪市立大学大学院 都市系専攻教授の中尾正喜さんです。
下水は水道水より温度が高い。都市内に張り巡らされた下水道管路で熱を汲み上げ、都市生活に必要なお湯を得るための方策について講義がありました。
1、都市におけるエネルギー・熱代謝
エネルギー(電気・ガス・石油)を供給し、都市域で都市活動を行うことで、人工排熱が環境(気圏・水圏・地圏)へ熱として排出される。化石燃料を減らし(⇒温暖化対策)、排出量を減らす。特に、大気(気圏)への排出を減らす(⇒ヒートアイランド対策)。
2、熱回収の方式
1)熱交換機による熱回収
2)ヒートポンプによる熱回収
3、ヒートポンプの活用
1)ヒートポンプの仕組み
2)家庭用ヒートポンプ給湯システム(エコキュート)
4、下水熱利用の現状(国内)
1)下水処理場における処理水の熱利用
①大型プラント:幕張新都心、品川ソニーシティ
・処理場と需要地が近い
②小型プラント(処理水熱利用のほとんど):
東京都下水道局(11カ所)、名古屋市下水道局(6カ所)
・配管の費用がかかるので施設内のみで利用
2)未処理下水
・熱の需要地に比較的近いポンプ場での大型プラントが2カ所のみ
①後楽1丁目地区
・熱供給管(約400m)の建設費は熱源設備に匹敵
②盛岡西口地区
・需要のある所とポンプ場が近い
5、今後の展望
1)大阪地域での下水幹線における下水熱利用
・首都圏と比べて夏期の水温が高く、冬季はやや高い傾向
・北野抽水所の場合
首都圏と比べ季節による違いが少ない
深夜に落ち込み、明け方上昇して、昼ごろピーク
2)熱利用が普及すると下水熱が足りなくなる
3)排熱処理を併用する
4)より安価な熱交換器・きょう雑物分離機器
下水は水道水より温度が高い。都市内に張り巡らされた下水道管路で熱を汲み上げ、都市生活に必要なお湯を得るための方策について講義がありました。
1、都市におけるエネルギー・熱代謝
エネルギー(電気・ガス・石油)を供給し、都市域で都市活動を行うことで、人工排熱が環境(気圏・水圏・地圏)へ熱として排出される。化石燃料を減らし(⇒温暖化対策)、排出量を減らす。特に、大気(気圏)への排出を減らす(⇒ヒートアイランド対策)。
2、熱回収の方式
1)熱交換機による熱回収
2)ヒートポンプによる熱回収
3、ヒートポンプの活用
1)ヒートポンプの仕組み
2)家庭用ヒートポンプ給湯システム(エコキュート)
4、下水熱利用の現状(国内)
1)下水処理場における処理水の熱利用
①大型プラント:幕張新都心、品川ソニーシティ
・処理場と需要地が近い
②小型プラント(処理水熱利用のほとんど):
東京都下水道局(11カ所)、名古屋市下水道局(6カ所)
・配管の費用がかかるので施設内のみで利用
2)未処理下水
・熱の需要地に比較的近いポンプ場での大型プラントが2カ所のみ
①後楽1丁目地区
・熱供給管(約400m)の建設費は熱源設備に匹敵
②盛岡西口地区
・需要のある所とポンプ場が近い
5、今後の展望
1)大阪地域での下水幹線における下水熱利用
・首都圏と比べて夏期の水温が高く、冬季はやや高い傾向
・北野抽水所の場合
首都圏と比べ季節による違いが少ない
深夜に落ち込み、明け方上昇して、昼ごろピーク
2)熱利用が普及すると下水熱が足りなくなる
3)排熱処理を併用する
4)より安価な熱交換器・きょう雑物分離機器