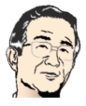28日、立命館大阪キャンパスで、立命館大阪プロムナードセミナー「木津川 計/大阪学講座」4回目の「<大阪城天守閣>はなぜ再建されたのか-陸軍の制圧から大阪城址を奪回した関一 ―」を受講しました。内容は以下の通りです。
大坂城は、大坂冬の陣・夏の陣、鳥羽伏見の戦いで二度焼失した。その跡地へ、明治新政府は大阪鎮台を置く(1871年)。1888年に大阪鎮台は第四師団司令部になった。かっての城内へ市民は立入れなかった。
1928年(昭和3)7月、関一は御大典記念事業として大阪城再建議案を市会に提案した。再建事業の内容は、工費約70万円で大阪城跡地に大阪城公園を設け、鉄骨鉄筋コンクリート造の天守閣を築造し、公園道跡を設け、工費80万円で鉄筋コンクリート造の第四師団司令部庁舎を移転改築するものであった。
議案は同年7月議会で可決された。事業費150万円、そのすべてを関は「広く一般市民の篤志に待つ」といった。一銭の負担も大阪市はしない。各区役所に設置された推進委員会に前例のない規模の寄付申込者が相次ぎ、半年足らずの間に法人・個人を合わせて78250余件の寄附申込がなされ、目標の150万円に達した。
天守閣復興で一番問題になったのは、大阪城内が明治以降軍用地として使用され、特に本丸はその中心部であったこと。しかし、御大典記念事業という錦の御旗があり、軍部も応じざるを得なかった。陸軍と関との間のやり取り(なぜ陸軍から市民の手に取り戻したのか)を関は語っていない。
市長としての関は、市営公園や公営住宅の整備、御堂筋の拡福、地下鉄の建設(現大阪市営地下鉄御堂筋線)、大阪城天守閣の再建、大阪商科大学(現大阪市立大学)の開設など都市政策を実行した。関は大阪の近代化を推進した名市長で、大大阪を実現した。
大坂城は、大坂冬の陣・夏の陣、鳥羽伏見の戦いで二度焼失した。その跡地へ、明治新政府は大阪鎮台を置く(1871年)。1888年に大阪鎮台は第四師団司令部になった。かっての城内へ市民は立入れなかった。
1928年(昭和3)7月、関一は御大典記念事業として大阪城再建議案を市会に提案した。再建事業の内容は、工費約70万円で大阪城跡地に大阪城公園を設け、鉄骨鉄筋コンクリート造の天守閣を築造し、公園道跡を設け、工費80万円で鉄筋コンクリート造の第四師団司令部庁舎を移転改築するものであった。
議案は同年7月議会で可決された。事業費150万円、そのすべてを関は「広く一般市民の篤志に待つ」といった。一銭の負担も大阪市はしない。各区役所に設置された推進委員会に前例のない規模の寄付申込者が相次ぎ、半年足らずの間に法人・個人を合わせて78250余件の寄附申込がなされ、目標の150万円に達した。
天守閣復興で一番問題になったのは、大阪城内が明治以降軍用地として使用され、特に本丸はその中心部であったこと。しかし、御大典記念事業という錦の御旗があり、軍部も応じざるを得なかった。陸軍と関との間のやり取り(なぜ陸軍から市民の手に取り戻したのか)を関は語っていない。
市長としての関は、市営公園や公営住宅の整備、御堂筋の拡福、地下鉄の建設(現大阪市営地下鉄御堂筋線)、大阪城天守閣の再建、大阪商科大学(現大阪市立大学)の開設など都市政策を実行した。関は大阪の近代化を推進した名市長で、大大阪を実現した。