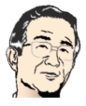2日(金)、大阪市立大学文化交流センターの専門家講座3月「生活科学コース《町家にみる庶民の暮らしと住文化》」の1回目「京の町屋、大阪の町屋」を受講しました。講師は、大阪市立住いのミュージアム副館長の新谷昭夫さんです。
庶民の伝統的な住居である町家について、建築的特色や空間構成のあり方、京都と大阪の違いなどを建物の写真や絵画資料などを用いて講義しました。内容は以下の通りです。
1、年中行事絵巻に描かれた町家
1)やすらい花の場面-『日本の絵巻8 年中行事絵巻』中央公論社
2)馬長行列の場面-同上
3)正月毬杖の場面-同上
(参考)町家と農家の比較
町家(住吉)、農家(千年家)
2、間取りからみた町家の種類
1)通りにわ形式-寛延3年(1750)うろこ形や五兵衛家指図(田中家文書)
2)通りにわ形式-宝暦10年(1760)山さき屋作兵衛家指図(田中家文書)
3)表屋造り形式-加賀屋清左衛門家指図(田中家文書)
4)大塀造り形式-林家住宅外観、林家住宅表座敷
5)大塀造り形式-仲屋住宅1階現況平面図
3、町家の空間構成
1)ケの空間ー長江家住宅間取り絵図(明治末期)
2)ハレの空間-『在京日記』宝暦7年(1757)7月25日条(聖護院宮の御峰入の行列に関する箇所)
3)ハレの空間-祇園祭礼図屏風(部分)
4)ハレの空間-『在京日記』宝暦6年(1756)6月6日条(祇園祭の宵山に関する箇所)
5)まとめ
4、町家の地域性
1)上方の町家-大坂建
2)大坂の町家-綴屋根:京都の町家(三上家)、大阪の町家(北垣家)
3)大坂の町家-壁塗込:京都の町家(秦家)、大阪の町家(北垣家)
4)大坂の町家-屋根材:桟瓦葺(京都)、本瓦葺(大阪)、鬼瓦(大阪)
5)その他
庶民の伝統的な住居である町家について、建築的特色や空間構成のあり方、京都と大阪の違いなどを建物の写真や絵画資料などを用いて講義しました。内容は以下の通りです。
1、年中行事絵巻に描かれた町家
1)やすらい花の場面-『日本の絵巻8 年中行事絵巻』中央公論社
2)馬長行列の場面-同上
3)正月毬杖の場面-同上
(参考)町家と農家の比較
町家(住吉)、農家(千年家)
2、間取りからみた町家の種類
1)通りにわ形式-寛延3年(1750)うろこ形や五兵衛家指図(田中家文書)
2)通りにわ形式-宝暦10年(1760)山さき屋作兵衛家指図(田中家文書)
3)表屋造り形式-加賀屋清左衛門家指図(田中家文書)
4)大塀造り形式-林家住宅外観、林家住宅表座敷
5)大塀造り形式-仲屋住宅1階現況平面図
3、町家の空間構成
1)ケの空間ー長江家住宅間取り絵図(明治末期)
2)ハレの空間-『在京日記』宝暦7年(1757)7月25日条(聖護院宮の御峰入の行列に関する箇所)
3)ハレの空間-祇園祭礼図屏風(部分)
4)ハレの空間-『在京日記』宝暦6年(1756)6月6日条(祇園祭の宵山に関する箇所)
5)まとめ
4、町家の地域性
1)上方の町家-大坂建
2)大坂の町家-綴屋根:京都の町家(三上家)、大阪の町家(北垣家)
3)大坂の町家-壁塗込:京都の町家(秦家)、大阪の町家(北垣家)
4)大坂の町家-屋根材:桟瓦葺(京都)、本瓦葺(大阪)、鬼瓦(大阪)
5)その他