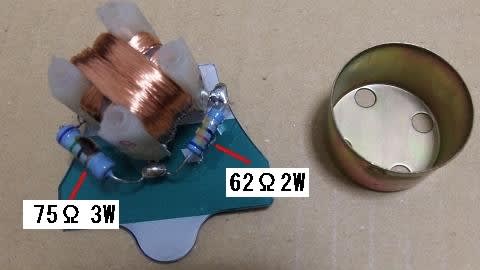わがYBR125のフロントタイヤがいよいよ終わりに近づいてるので、ビードブレーカの威力を借りて
交換作業に入り、あっという間にビードを落せたのでさっさとホイールからタイヤを外す。
ビードプロテクターは“自転車の古タイヤを切った物”を愛用中。
市販の樹脂製プロテクターより薄くて使いやすいので、チューブタイプのオフローダーのパンク修理携行用
にも勧められる。
交換用に購入しておいたのは今回初体験になるIRC GP-1 3.00-18 。
ミシュラン MT62 に比べて山が高くてブロックもゴツゴツしてるけれど、一応メーカーはON/OFF両用の
デュアルパーパスモデルとして発売してるタイヤなので、M62と変わらない分野である。
M62と比べてビード幅が広くてそのままでもホイールへの密着がよさそうだから、空気入れのきっか
けがつかみやすそうだ。
GP-1はWT、つまりチューブ仕様のタイヤであるが、そのままチューブレスで装着した。
もちろんビードクリームを丁寧に塗ってビード上がりを促進させる。
幅広ビードのおかげで自転車用空気入れでも
なんの苦労もなく、そのまま膨らんでビードが出た。
ここまでの作業時間30分、道具と条件が揃うと早いなあ。
GP-1を装着したYBRの勇姿w
YBR125GやYBR125KGの雰囲気になったね。w これでしばらく近所の河原やあぜ道で遊べそうだ。
空気漏れの問題も起きず、IRC GP-1 に関してはミシュラン M62 と同様にチューブレス状態で装着
運用は可能という実例になったので満足。
GやKGオーナーにとっては朗報なんじゃないかな?
ビード上げのしやすさからGP-1なら手組み交換でも楽な部類だと思う。
ついでにチューブレスホイールの特徴を撮影しておいたので掲載しておく。
断面で内側に凸があるのがチューブレス用ホイールの特徴で、ここにタイヤのビードを乗り越えさせるの
が一番苦労する工程だ。
凸部が無いのがチューブ式ホイールの断面形状でタイヤの付け外しはこれよりはるかに楽だ。
チューブ式ホイールだったら携行工具でも問題ないし、何度もパンク修理の経験をしてる。
俺がチューブレス状態にこだわる理由は、出先でパンク修理するにしてもチューブレスホイールにチューブ
を入れてチューブタイヤを装着した場合、携行工具じゃタイヤの付け外しに対応しきれない場合がほとんど
だからだ。
チューブレス装着ならタイヤを外すこと無く、携行修理キットで対応できる。
だが、このパターンの他にチューブホイールにクランプインバルブを装着してタイヤをそのままチューブ
レスで装着した方がもっと楽だろう。
手組みでもタイヤの入れ替えが楽で、しかもパンク時の修理も楽な条件はなかなかない。
YB125Z、YB125SP、YBR125の05~06式なんか出来そうだよね。
他車種の実例(右クリック・別窓で開くといいだろう)
GN125H チューブレス化
CBF125 CBF125タイヤ交換 サイズアップ チューブレス化
両者共に空気圧管理を十分する条件下での自己責任の改造なので、管理が苦手な人、自分で
手組みできない人には向かない方法でもある。
また、オフロード車のように空気圧を下げてダートでのグリップ特性を上げるような技に関しては不安があり、
せいぜい規定値175kpaくらいでトコトコとのんびりフラットダートを走るなど、YBRの車体限界を超えなけれ
ばビード落ちの心配は無いだろう。
GやKGの設定でもYBRは飛んだり跳ねたりする本格的オフロード車ではなく、悪路の多い国でもそれなりに
走れるスクランブラー的な位置付けだと思う。
さて、今回も無事チューブレス状態での装着が完了したけれど、山の方はまだ残雪で走りにくそうだから
大人しく近所で我慢しますよ。