技術者のための発想法に「トゥリーズ」というものがあります。「トゥリーズ」って"TREES"?樹形図にしてアイデアを整理するの?と思いきや、スペルは"TRIZ"。1946年に旧ソ連で生まれた発明的問題解決理論とのことで(その後研究が進められ、1990年初頭以降は西側諸国で発展)、ロシア語の Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch(英語では Theory of solving inventive problems または Theory of inventive problems solving)の略語です。
(以下引用)
TRIZ(トゥリーズ)は「発明的問題解決の理論」と訳される。ロシアで作られ、欧米に広まり、近年はアジアで認知度が上がってきた。TRIZを作った人物たちは膨大な特許を分析し、特許の中に繰り返し現れる問題解決の構造を「技術的ブレークスルーの40パターン」にまとめた(筆者注:そのほかにも複数のコンテンツがある)。その40パターンは「発明原理」と名付けられている。
(引用終わり)
出所:IT Media「TRIZ――10分以内に「それ、どうやって実現するか」を思いつく方法」(http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0804/22/news064.html)
日本でもこのTRIZは技術者の方々の間でかなり浸透しているようで、日本TRIZ協会という団体も設立されていますし、「日経ものづくり」でも紹介されていたように記憶しています。果たしてどの程度、我が国のものづくりやソフトウェア開発にこのTRIZが貢献しているのかはわかりませんが、基礎研究はともかく民生部門の技術開発はダメだった(軍需も実は西側に比べてお粗末だった)ロシアで生まれた発想法が現代の技術者に注目され続けていることが興味深いと思います。
(以下引用)
TRIZ(トゥリーズ)は「発明的問題解決の理論」と訳される。ロシアで作られ、欧米に広まり、近年はアジアで認知度が上がってきた。TRIZを作った人物たちは膨大な特許を分析し、特許の中に繰り返し現れる問題解決の構造を「技術的ブレークスルーの40パターン」にまとめた(筆者注:そのほかにも複数のコンテンツがある)。その40パターンは「発明原理」と名付けられている。
(引用終わり)
出所:IT Media「TRIZ――10分以内に「それ、どうやって実現するか」を思いつく方法」(http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0804/22/news064.html)
日本でもこのTRIZは技術者の方々の間でかなり浸透しているようで、日本TRIZ協会という団体も設立されていますし、「日経ものづくり」でも紹介されていたように記憶しています。果たしてどの程度、我が国のものづくりやソフトウェア開発にこのTRIZが貢献しているのかはわかりませんが、基礎研究はともかく民生部門の技術開発はダメだった(軍需も実は西側に比べてお粗末だった)ロシアで生まれた発想法が現代の技術者に注目され続けていることが興味深いと思います。












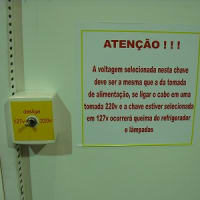







一応専門家の端くれです。1995年当時に企業内での活用研究をしていました。日経ものづくりの創刊当時に誤解を持って受け取られたため、そのあとの失望も早かったのです。
最近は特許データベース分析事例として唯一具体的に成功したものとして用いられていますが、データベースの分類法が古典手法(クラシカルTRIZ)では膨大な時間になってしまうことから、第二次の勃興時期はITなどでの検索が合理的に実施されるようになった1990年以降(コンテンポラリーTRIZ)と考えらえます。このため日本より韓国の企業のほうが活用事例が多いんですね。
シミュレーションとは少し違って情報ツールとしての見方のほうがいいでしょうか。(大学などで設計工学を論議するときはこの事項は必須になってきているようで、大概のMOTコースではこれを論ずる講座がありますし、そのためのテキストの執筆もしたことがあります)
なお、TRIZを開発したアウトシュラー自身軍の特許技術者でしたが、不遇をかこっていた時期もあり、1970年から1980年の間は教育活動はされたもの軍内部でさえ実用普及事例は極めて少なかったことも言えます。
かなりメジャーな手法なんですね。
ロシアで開発されたものの、母国では発展せず日本などで花開いた技術にはほかにもあるようですね。鉄鋼の連続鋳造技術もその1つだということです。