工作機械業界の方々とお付き合いしていると、国の「輸出管理」に対する不平不満のお話をよく聞きます。大量破壊兵器の生産技術の流出につながりかねない、ということで工作機械の輸出は厳しく管理されています。輸出管理の手順が明文化されておらず役所の担当者によって話が異なる、意味の無いような書類の作成を求められる、ドイツやスイスの役所はもっと柔軟に制度を運用している、などなど、関係者の方々は誠に憤懣やるかたない様子です。この工作機械の輸出管理の問題については以前このブログでも触れましたが(こちら)、いろいろと話をうかがってみると我が国の役所による輸出管理はやはりやり過ぎであるように思いました。
例えば、某社が某国の航空機部品メーカーに工作機械を輸出しようとしたところ、役所から待ったがかかりました。このメーカーは軍需産業にも関わっており、輸出はまかりならん、というのです。しかしこの航空機部品メーカーは、アメリカのボーイング社の下請メーカーであり、ボーイング社向けの仕事のためにこの某社の工作機械を購入しようとしていたのです。安保条約を締結している友好国のための輸出なのに、なぜNGなのか誠に理解に苦しむ、というのが某社の言い分です。
また、輸出先で工作機械が故障した場合、工作機械メーカーが修理のためにエンジニアを派遣することも難しいそうです。エンジニアを派遣することで技術が流出し、軍需に流用されかねない、と役所から待ったがかかるというのです。じゃあどうやってメンテナンスのサービスをするんですか、と聞いたところ、部品を送って交換することであればオッケーなのだとのことでした。確かに賃金コストの高い日本人エンジニアを現地に送るよりも、部品を丸ごと交換するほうがコストが安くなるでしょう。しかし、現地のローカルスタッフをエンジニアとして育てればメンテナンスコストはもっと安くなり、現地のユーザーの満足度も上がるのではないかと思うのですが、それは技術流出だからNGなのだとのことでした。
こうも工作機械業界が役所から厳しく規制されるのはなぜなのか。背景にはかつての某社のココム違反事件があることは明らかですが、それだけではない、とある関係者氏はおっしゃいます。
日本は軍需に転用できるハイテク技術をたくさん保有しています。例えばデジタルカメラなどの民生用IT機器。これらの技術はミサイルの誘導装置などに転用することは大いに可能でしょうけれども、工作機械のように、どこに販売されるのか、販売先での用途は何かなど、役所からうるさく問われることはありません。そして金型などの素形材。これもまた軍需と深い関係があるはずなのですが、役所がうるさく輸出を規制することはありません。ノウハウの塊である金型の図面が外国に流出してコピーを作られてしまった場合、役所は金型メーカーに対して同情的な立場を取りますが、もし同じように工作機械の設計図面が外国に流出した場合、工作機械メーカーは役所から同情されるどころか「管理がなっとらん」と厳しい制裁が課されてしまうと思います。
なぜ工作機械業界の場合は役所の対応が異なるのかというと、この関係者氏は業界構造の違いにあると言います。民生用IT機器の場合、生産しているメーカーがいずれも大企業であり、役所としてはあまり手を出したくない相手です。そして素形材の場合、生産しているメーカーは圧倒的に中小企業が多く、政策的に保護すべき対象であり、こちらも役所としては厳しい態度で臨みにくい相手です。一方、工作機械業界はというと、中小企業が中心とはいえ、企業の規模としては素形材ほどは小さくはありません。民生用IT機器や素形材は量が膨大で、とても工作機械のように販売先を個別にトレースできないという問題もありますが、工作機械は業界を構成する企業のサイズが役所がいじめるのにちょうどよいからだ、というのが関係者氏の主張です。
この関係者氏の主張が正しいかどうかは私には判断できませんが、過度な技術流主防止政策は適切な技術移転や国際分業、そして業界の発展を阻害するだけであることは確かであるように思います。
例えば、某社が某国の航空機部品メーカーに工作機械を輸出しようとしたところ、役所から待ったがかかりました。このメーカーは軍需産業にも関わっており、輸出はまかりならん、というのです。しかしこの航空機部品メーカーは、アメリカのボーイング社の下請メーカーであり、ボーイング社向けの仕事のためにこの某社の工作機械を購入しようとしていたのです。安保条約を締結している友好国のための輸出なのに、なぜNGなのか誠に理解に苦しむ、というのが某社の言い分です。
また、輸出先で工作機械が故障した場合、工作機械メーカーが修理のためにエンジニアを派遣することも難しいそうです。エンジニアを派遣することで技術が流出し、軍需に流用されかねない、と役所から待ったがかかるというのです。じゃあどうやってメンテナンスのサービスをするんですか、と聞いたところ、部品を送って交換することであればオッケーなのだとのことでした。確かに賃金コストの高い日本人エンジニアを現地に送るよりも、部品を丸ごと交換するほうがコストが安くなるでしょう。しかし、現地のローカルスタッフをエンジニアとして育てればメンテナンスコストはもっと安くなり、現地のユーザーの満足度も上がるのではないかと思うのですが、それは技術流出だからNGなのだとのことでした。
こうも工作機械業界が役所から厳しく規制されるのはなぜなのか。背景にはかつての某社のココム違反事件があることは明らかですが、それだけではない、とある関係者氏はおっしゃいます。
日本は軍需に転用できるハイテク技術をたくさん保有しています。例えばデジタルカメラなどの民生用IT機器。これらの技術はミサイルの誘導装置などに転用することは大いに可能でしょうけれども、工作機械のように、どこに販売されるのか、販売先での用途は何かなど、役所からうるさく問われることはありません。そして金型などの素形材。これもまた軍需と深い関係があるはずなのですが、役所がうるさく輸出を規制することはありません。ノウハウの塊である金型の図面が外国に流出してコピーを作られてしまった場合、役所は金型メーカーに対して同情的な立場を取りますが、もし同じように工作機械の設計図面が外国に流出した場合、工作機械メーカーは役所から同情されるどころか「管理がなっとらん」と厳しい制裁が課されてしまうと思います。
なぜ工作機械業界の場合は役所の対応が異なるのかというと、この関係者氏は業界構造の違いにあると言います。民生用IT機器の場合、生産しているメーカーがいずれも大企業であり、役所としてはあまり手を出したくない相手です。そして素形材の場合、生産しているメーカーは圧倒的に中小企業が多く、政策的に保護すべき対象であり、こちらも役所としては厳しい態度で臨みにくい相手です。一方、工作機械業界はというと、中小企業が中心とはいえ、企業の規模としては素形材ほどは小さくはありません。民生用IT機器や素形材は量が膨大で、とても工作機械のように販売先を個別にトレースできないという問題もありますが、工作機械は業界を構成する企業のサイズが役所がいじめるのにちょうどよいからだ、というのが関係者氏の主張です。
この関係者氏の主張が正しいかどうかは私には判断できませんが、過度な技術流主防止政策は適切な技術移転や国際分業、そして業界の発展を阻害するだけであることは確かであるように思います。












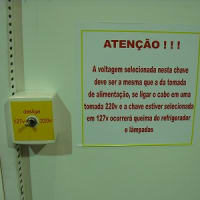







情報ありがとうございます。工作機械業界からはいろいろと他にも興味深い話を聞いています。いつかまた紹介しようと思います。
今日、杉本泰治さんという企業倫理・技術者倫理の専門家の講演会にいってきたのですが、この話にどんぴしゃの話が出てきました。
-------------------
東芝機械ココム違反事件で、親会社の東芝製品まで輸出規制をかけられた日本政府は、これにこりて規制を厳しくしてほかの企業に類が及ばないようにした。しかし逆に日本が輸出規制を他国にかけることは政策上できなかったため、旧共産圏には米独の高級機械がたくさん入ることになった。
一時緩んだ規制は9・11で元に戻る以上に厳しくなり、輸出管理をさらに高くしなければ米国への出荷停止を求められることになり、事実何社かが勧告をだされてしまい、萎縮してしまった。(当時の通産省はグレーゾーンを全部危険サイドに判断してしまい、日本企業もそれに従うしかなかったという元豊田工機専務の言)最近はきわどいものはアメリカの合弁会社からの出荷にすることでクリアしている。
------------------
なんか、最近のT自動車の一件にもすこしにてるのかもしれません。
参考:http://www.amazon.co.jp/%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E2%80%95%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95%E4%BB%A4%E3%81%A8%E5%80%AB%E7%90%86%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E6%9D%89%E6%9C%AC-%E6%B3%B0%E6%B2%BB/dp/4621081039
技術とコンプライアンス P48 コンプライアンスの経営判断
>何を作られるかわからない
それはいえますね。
>つまりEUクローズの世界でやっていけるので、
欧州の強みですね。日本はどうしてもアメリカの目を気にせざるを得ませんから。
ドイツもスイスもいざとなったら、これらの輸出規制枠から逃げ出せますよね。つまりEUクローズの世界でやっていけるので、文句をつければその国が離脱するだけということになってしまう。日本は輸入による中間加工が多いが顧客が偏ってるため、制御が格段に効く。
そのあたりが、とかくけちをつけやすい相手と思われているという見方もあるようです。
---------------
民生用IT機器でも同じように言われている側面がある(いくつか事例はありますね)のですが、そもそも捕捉が難しく、結果的に諸外国から見ても見えないし、全体的な意味でいちゃもんをつけてもパフォーマンスが悪いだけということであって、もし露呈した場合は、同じ問題になるということは認識していると思います。
---------------
では金型はどうか。公知の技術と、海外に技術指導を行っている人を規制するしかないためすでに手遅れとも言えるようです。
何を作られるかわからない
そーいう不安を感じているだけだと思いますが。