司法試験合格者は、いくつかの資格の試験が免除されるようです。
弁理士について調べたのですが、よくわかりませんww。
ただ、弁護士法3条2項は
「2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」
とあるので、税理士、弁理士については、できるという意味だと思うのですが、違うのでしょうか?
気になるのは、「弁護士は、」とあり、他の試験の免除項目などに記載されている「弁護士となる資格を有する者は、」と書いていない以上、司法修習終了後、弁護士登録をして弁護士として活動していなければならないのでしょうね。
弁理士業務や税理士業務だけを行いたいという場合には、弁理士試験を受けないとダメなんでしょう。
つまり、弁護士登録をせず、企業内サラリーマンで弁理士として活躍したい場合も、別途弁理士試験に合格しないとダメなんでしょうね。
弁理士について調べたのですが、よくわかりませんww。
ただ、弁護士法3条2項は
「2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」
とあるので、税理士、弁理士については、できるという意味だと思うのですが、違うのでしょうか?
気になるのは、「弁護士は、」とあり、他の試験の免除項目などに記載されている「弁護士となる資格を有する者は、」と書いていない以上、司法修習終了後、弁護士登録をして弁護士として活動していなければならないのでしょうね。
弁理士業務や税理士業務だけを行いたいという場合には、弁理士試験を受けないとダメなんでしょう。
つまり、弁護士登録をせず、企業内サラリーマンで弁理士として活躍したい場合も、別途弁理士試験に合格しないとダメなんでしょうね。












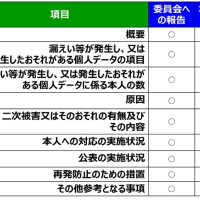
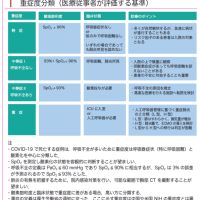
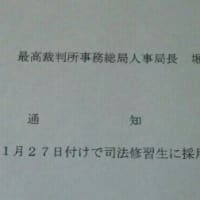






私も予備試験経由の社会人合格者ではあるものの、長期の専業の時代を経ているので、ずっと社会人として働きながら勉強されて合格されたのは、本当にすごいと思います。
試験免除の件ですが、税理士法3条1項4号と弁理士法7条2号によって、それぞれ「弁護士となる資格を有する者」であれば登録できるみたいです。
なお、登録しなくても弁護士として税理士業務と弁理士業務ができるようです。
税理士の場合は、税理士法51条1項により、国税局長に通知をする必要があるようですが、弁理士の場合は通知不要(?)みたいですね。
情報、ありがとうございます。
そちら側からの法律に書いてありましたか!!
ということは、弁護士として登録しなくても、弁理士としてのみ登録も可能なんですね!
良い情報をありがとうございます。
実際に登録する場合は、きっちり確認しますが、とりあえず、弁理士の勉強も税理士の勉強もする必要がなくなってほっとしています。