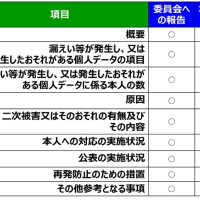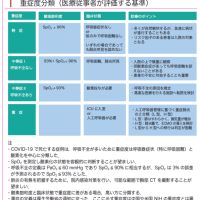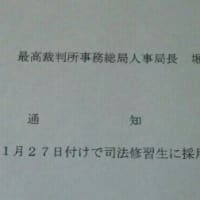代理名義の冒用には、作成者は誰かという問題と名義人は誰かという問題がある
ということをよく理解していなかったために、勘違いが生じました。
Xには、Aの代理権限がないのにA代理人Xとする文書を作成した場合。
偽造罪について
偽造罪の保護法益は、文書に対する社会一般の信用である。
そして、これは、名義人が責任を負うかどうかが重要であるため、
偽造とは、文書の名義人と作成者の人格的同一性を偽ることである。
ここで、疑問だったのが、代理名義の冒用なのです。
上記問題で、XがAの代理権限を有する正当な代理人の場合、
形式的に把握すると、作成者はX、名義人はAとなります。
とすると、作成者はX≠名義人はAとなってしまい、偽造の形式的
定義に該当することになります。
これに対して、択一で有名な承諾を与えたから違法性が阻却されると
いう反論もありますが、文書に社会的信頼を保護する公共的犯罪に個人の意思で違法性が
阻却されるのは妥当でないと再度批判されます。
そのため、代理名義の冒用については、作成者は誰かという問題と、
名義人は誰かという問題があるのです。
形式的に作成者はXとすると上記疑問があります。
そこで、判例は、
作成者は、文書の意思の主体と解します。
とすると、正当な代理権を有するのであるから、Xが作成した
文書の意思の主体はAであるため、法律的意味の作成者は、Aである。
そこで、
作成者はA=名義人はAとなり、偽造ではなくなる。
ここで、以前のブログでは、文書の意思の主体ではなく、効果帰属する者と
いう説を取った場合、
「作成者は、現に作成した者をいうのではなく、文書の効果が帰属する者」
と記述しています。
この場合、択一で有名な、公序良俗違反で効果が名義人に帰属しない場合、
自己が作成した自己名義文書でも有形偽造になるとの批判があります。
そして、代理権限がない者が作成した文書については、
文書の意思の主体は、冒用者の意思によって作成されたので、
文書の作成者はXとなります。
さて、次に問題となるのが、名義人ですが、名義人は、
文書上認識される者というべきことから、上記問題では
本人Aとなります。
代理名義の冒用の択一的まとめ
作成者
1.文書を形式的に作成した人
×社長秘書が作成しても偽造になる。
2.文書の意思の主体となる人
×代理権を濫用した場合も偽造になる
3.文書の効果が帰属する人
×自己作成文書で公序良俗違反の文書の場合も偽造になる。
名義人
1.無権代理人X
×無形偽造になる
2.本人A
3.A代理人X
×肩書きの冒用も偽造になる
ということで、まとめてみますと、
代理名義の冒用には作成者と名義人の問題がある。
作成者が文書の意思・観念の主体とした場合、その者が
作成した文書上認識される名義人と異なる場合に
有形偽造となる
ということがいえると思います。
ということをよく理解していなかったために、勘違いが生じました。
Xには、Aの代理権限がないのにA代理人Xとする文書を作成した場合。
偽造罪について
偽造罪の保護法益は、文書に対する社会一般の信用である。
そして、これは、名義人が責任を負うかどうかが重要であるため、
偽造とは、文書の名義人と作成者の人格的同一性を偽ることである。
ここで、疑問だったのが、代理名義の冒用なのです。
上記問題で、XがAの代理権限を有する正当な代理人の場合、
形式的に把握すると、作成者はX、名義人はAとなります。
とすると、作成者はX≠名義人はAとなってしまい、偽造の形式的
定義に該当することになります。
これに対して、択一で有名な承諾を与えたから違法性が阻却されると
いう反論もありますが、文書に社会的信頼を保護する公共的犯罪に個人の意思で違法性が
阻却されるのは妥当でないと再度批判されます。
そのため、代理名義の冒用については、作成者は誰かという問題と、
名義人は誰かという問題があるのです。
形式的に作成者はXとすると上記疑問があります。
そこで、判例は、
作成者は、文書の意思の主体と解します。
とすると、正当な代理権を有するのであるから、Xが作成した
文書の意思の主体はAであるため、法律的意味の作成者は、Aである。
そこで、
作成者はA=名義人はAとなり、偽造ではなくなる。
ここで、以前のブログでは、文書の意思の主体ではなく、効果帰属する者と
いう説を取った場合、
「作成者は、現に作成した者をいうのではなく、文書の効果が帰属する者」
と記述しています。
この場合、択一で有名な、公序良俗違反で効果が名義人に帰属しない場合、
自己が作成した自己名義文書でも有形偽造になるとの批判があります。
そして、代理権限がない者が作成した文書については、
文書の意思の主体は、冒用者の意思によって作成されたので、
文書の作成者はXとなります。
さて、次に問題となるのが、名義人ですが、名義人は、
文書上認識される者というべきことから、上記問題では
本人Aとなります。
代理名義の冒用の択一的まとめ
作成者
1.文書を形式的に作成した人
×社長秘書が作成しても偽造になる。
2.文書の意思の主体となる人
×代理権を濫用した場合も偽造になる
3.文書の効果が帰属する人
×自己作成文書で公序良俗違反の文書の場合も偽造になる。
名義人
1.無権代理人X
×無形偽造になる
2.本人A
3.A代理人X
×肩書きの冒用も偽造になる
ということで、まとめてみますと、
代理名義の冒用には作成者と名義人の問題がある。
作成者が文書の意思・観念の主体とした場合、その者が
作成した文書上認識される名義人と異なる場合に
有形偽造となる
ということがいえると思います。