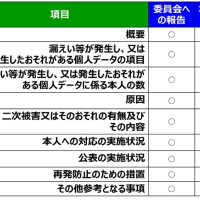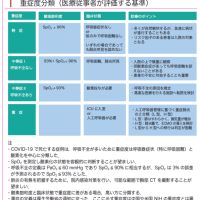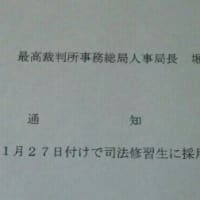まとめていったのを書いていきます。
民事訴訟法の訴訟要件について
訴訟要件は、本案判決を得るために具備しておかなければならない要件です。
訴訟要件を要求する趣旨は、無駄な訴訟を排除し、効率的訴訟運営を行うという、国家の利益、国民の利益と、当事者の利益のためです。
重要なのは、国家、国民の利益であるため、原則として公益的目的のために訴訟要件は要求されているので、それが具備されているかの調査の開始は裁判所とする職権調査事項です。
ただ、私的事項に関することは、当事者が調査を開始する抗弁事項です。
そして、公益的目的であるため、その資料の収集、提出は、裁判所が行うのが原則です。
しかし、資料が訴訟の帰趨を左右、本案に密接に関連する場合もあるため、そのような訴訟要件については当事者が収集、提出を行う弁論主義が妥当します。
本案に密接に関連する者を裁判所が収集、提出したならば、弁論主義(訴訟資料の収集、提出は、当事者の責任と権能とする建前)に反するからです。
私的自治が妥当する範囲に公権力が介入することによって、当事者の意思の尊重が無視され、被告の不意打ちにつながる恐れがあるからです。
どのようなものが訴訟要件か。
分類としては、
・裁判所に関すること…裁判権、専属管轄
・当事者に関すること…当事者能力、当事者適格、訴えの提起や訴状の送達の有効性、代理権の存在、訴訟費用
・請求に関すること…二重訴訟の禁止、再訴禁止、併合の訴えの要件、訴えの利益、不起訴の合意
裁判所が調査を開始すべき訴訟要件として、公益的目的のためであるため、当事者能力、当事者適格、訴訟能力、裁判権、専属管轄
当事者が調査を開始すべき訴訟要件として、不起訴の合意
また、職権調査事項でも訴訟の帰趨を左右しないものならば、裁判所が行う職権探知主義が妥当するものは、当事者能力、訴訟能力、裁判権
弁論主義が妥当するのは、本案に密接に関連する事項であるから、訴えの利益、当事者適格
本案判決が訴訟要件の調査よりも先に決定した場合
このような場合、被告の利益となる訴訟要件では、具備されていなくても本案判決をしてもよいとする。
∵被告は請求棄却判決によって、訴訟から解放され、強力な既判力を手に入れられる。
∵本案判決は出ているのにもかかわらず訴訟要件の調査のため、さらに時間、金銭を費やすことは、被告の負担となる。
∵当事者適格、訴えの利益などは、被告の利益のため。
ただし、第三者に判決効が及ぶ場合の当事者適格は、被告以外の者の利益を図るという公益的目的もあるため、訴訟判決により却下すべきである。
時期
調査は随時
具備は、訴訟要件は原則、口頭弁論終結時にあれば良い。
訴訟要件が本案判決をするために必要な要件であるから。
もっとも、裁判権、専属管轄などは、訴訟開始時に必要である。
訴訟要件が口頭弁論終結後に消滅した場合、上告審で原判決を破棄して訴え却下の自判の判例あり(大判昭16年5月3日)。
また、訴訟要件が口頭弁論終結後に具備した場合、訴訟要件の欠缺を看過してなされた原判決を維持した判例あり(最判昭55年2月22日)。
さらに、訴訟要件の欠缺を理由とする訴え却下判決に対する上告審で、口頭弁論終結後に訴訟要件が具備されていても、却下判決を維持した判例あり(最判昭42年6月30日、最判昭46年6月22日)。
民事訴訟法の訴訟要件について
訴訟要件は、本案判決を得るために具備しておかなければならない要件です。
訴訟要件を要求する趣旨は、無駄な訴訟を排除し、効率的訴訟運営を行うという、国家の利益、国民の利益と、当事者の利益のためです。
重要なのは、国家、国民の利益であるため、原則として公益的目的のために訴訟要件は要求されているので、それが具備されているかの調査の開始は裁判所とする職権調査事項です。
ただ、私的事項に関することは、当事者が調査を開始する抗弁事項です。
そして、公益的目的であるため、その資料の収集、提出は、裁判所が行うのが原則です。
しかし、資料が訴訟の帰趨を左右、本案に密接に関連する場合もあるため、そのような訴訟要件については当事者が収集、提出を行う弁論主義が妥当します。
本案に密接に関連する者を裁判所が収集、提出したならば、弁論主義(訴訟資料の収集、提出は、当事者の責任と権能とする建前)に反するからです。
私的自治が妥当する範囲に公権力が介入することによって、当事者の意思の尊重が無視され、被告の不意打ちにつながる恐れがあるからです。
どのようなものが訴訟要件か。
分類としては、
・裁判所に関すること…裁判権、専属管轄
・当事者に関すること…当事者能力、当事者適格、訴えの提起や訴状の送達の有効性、代理権の存在、訴訟費用
・請求に関すること…二重訴訟の禁止、再訴禁止、併合の訴えの要件、訴えの利益、不起訴の合意
裁判所が調査を開始すべき訴訟要件として、公益的目的のためであるため、当事者能力、当事者適格、訴訟能力、裁判権、専属管轄
当事者が調査を開始すべき訴訟要件として、不起訴の合意
また、職権調査事項でも訴訟の帰趨を左右しないものならば、裁判所が行う職権探知主義が妥当するものは、当事者能力、訴訟能力、裁判権
弁論主義が妥当するのは、本案に密接に関連する事項であるから、訴えの利益、当事者適格
本案判決が訴訟要件の調査よりも先に決定した場合
このような場合、被告の利益となる訴訟要件では、具備されていなくても本案判決をしてもよいとする。
∵被告は請求棄却判決によって、訴訟から解放され、強力な既判力を手に入れられる。
∵本案判決は出ているのにもかかわらず訴訟要件の調査のため、さらに時間、金銭を費やすことは、被告の負担となる。
∵当事者適格、訴えの利益などは、被告の利益のため。
ただし、第三者に判決効が及ぶ場合の当事者適格は、被告以外の者の利益を図るという公益的目的もあるため、訴訟判決により却下すべきである。
時期
調査は随時
具備は、訴訟要件は原則、口頭弁論終結時にあれば良い。
訴訟要件が本案判決をするために必要な要件であるから。
もっとも、裁判権、専属管轄などは、訴訟開始時に必要である。
訴訟要件が口頭弁論終結後に消滅した場合、上告審で原判決を破棄して訴え却下の自判の判例あり(大判昭16年5月3日)。
また、訴訟要件が口頭弁論終結後に具備した場合、訴訟要件の欠缺を看過してなされた原判決を維持した判例あり(最判昭55年2月22日)。
さらに、訴訟要件の欠缺を理由とする訴え却下判決に対する上告審で、口頭弁論終結後に訴訟要件が具備されていても、却下判決を維持した判例あり(最判昭42年6月30日、最判昭46年6月22日)。