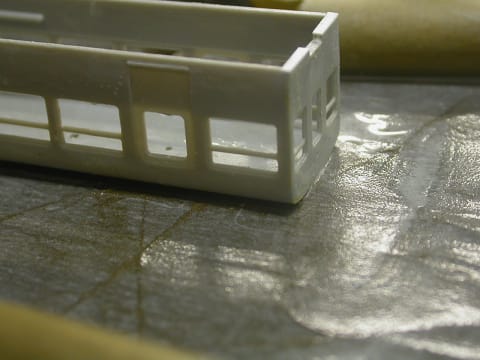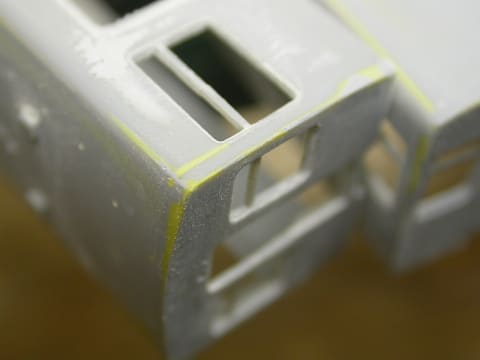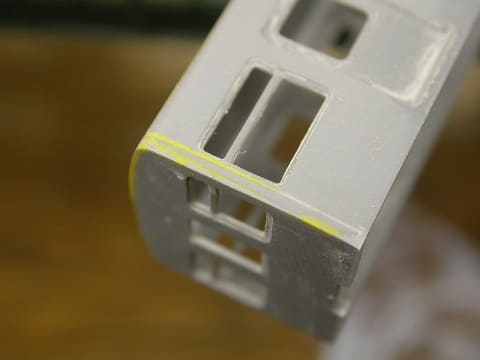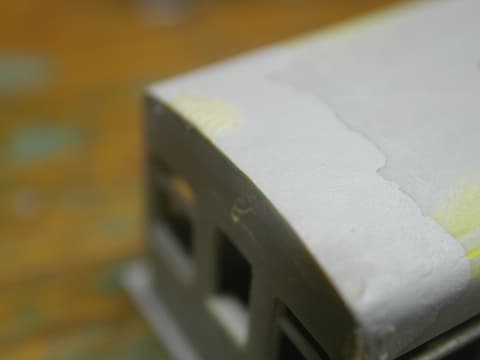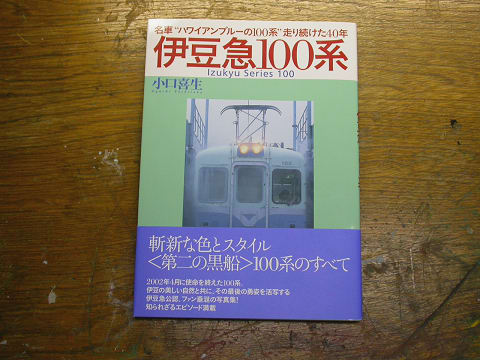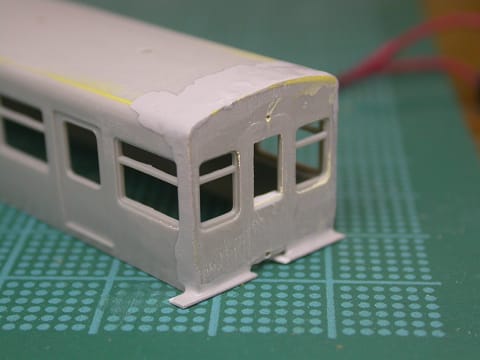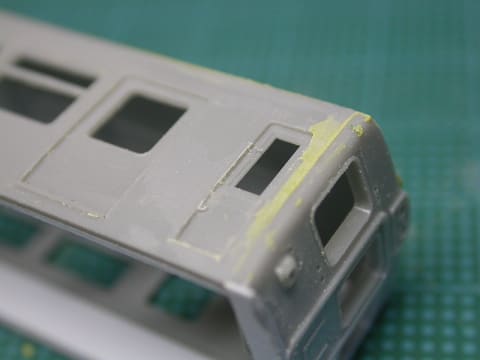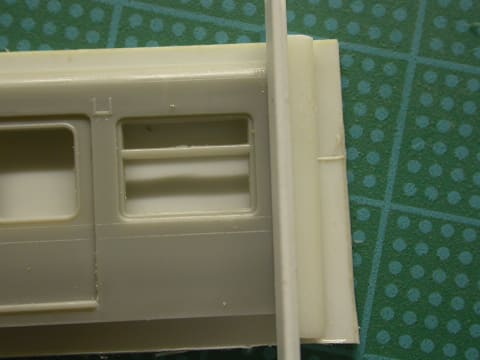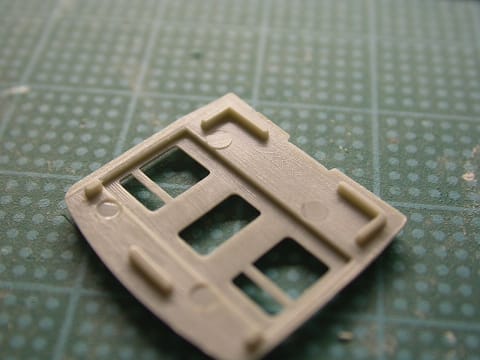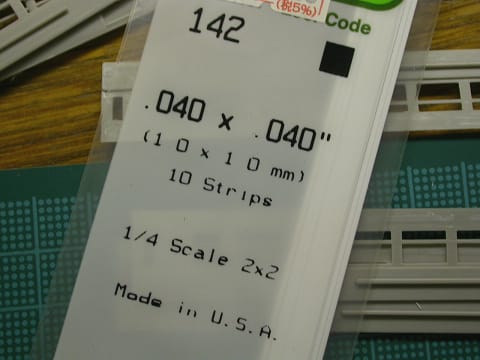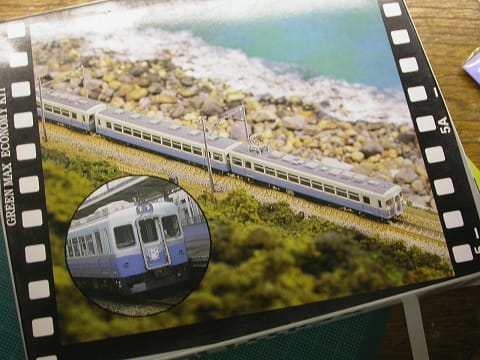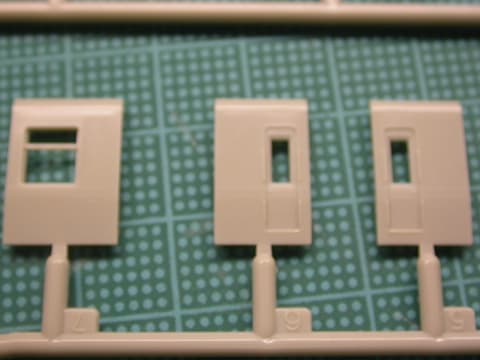車体鋼体をまずは仕上げていきます。

車体裾がめくれ上がっているのが見えると思います。
まるでアコモ改造で72系の台枠に115系の車体を乗せたがために、台枠が切り立ってしまったモハ62系Ⅱのような雰囲気です。

これを耐水パーパーをひいて、車体をか半回転させながら均一にこすり、滑らかな絞りにします。
もちろん、靴ずりは消えてしまいました。
と、
この上の写真。
つまり妻面を右にして後ろのドアを良く見ると

なんじゃこりゃ・・・・。
ドアが長方形ではないんです。
全部車体。
これは直せない。
少なくとも自分には直す術が解らない。
くりぬいて金属ドアに置き換えたりしても、どえらいことになります。
ノミで仕上げてもキット4枚全部綺麗にいかず乱れる。
しょうがないので、ココは目を瞑ります。
ドアは残念ですが

裾は仕上げきりました。
本当にディテールといえば、窓とドアの窪み、パンタ台(何で残しているんだというくらい簡単なものですが・・・。)、代替部品が思いつかない避雷器ぐらいです。
避雷器、別部品にしたい筆頭なんですけど・・・。
連結面角・隅柱の角を落とします。

耐水ペーパーに宛がって・・・
ゆるい角度から、

ゴリっと角度付けて滑らせます。


こんな感じで繰り返し。
自分は7回繰り返すことにして角度を安定させようと試みました。

下が施工前
上が施工後
これを絞り部分や屋根Rも全部行います。
屋根R部は耐水ペーパーのほうを持って撫でていきました。

施工前の妻板を接させるとこのように隙間は殆どありませんが

施工後はRが突きあってくぼみが出来る程度に角が落ちました。

こんなイメージ。
いい感じでしょ?
きっとRは結構デタラメなんだろうけど。

隅柱の細さもマァマァいい感じ。

この形式、本当に芸が細かいというか、シンプルな美しさが凄い電車です。
さすが五島会長の秘蔵鉄道の電車です。
惜しむらくは、偉い苦労しないと、この電車の本当の美しさが再現できないことです。
東急車輛電車市場からトミックスあたりに作らせた模型がNで出たら、ココまでの苦労は水泡に帰すわけですから、悲鳴が上がるとともに、とことん再現するでしょうから買っちゃいますね・・・。

今になって思えば、なんで一組は切りついでサハとクモハ両運にしなかったのかと。
最低でも、更にその2台を作らないと、格好が付かないじゃないですか。
いや、こんなに徹底的にやるとは思わなかったからなんですけどね。
今なら、切りついで短くなりそうな部分、プラ板挟んでも全く支障ないくらい削り込んで磨いています。
切りついではいませんが、ある意味切りつぎよりへビーなことしていますもんね。

洗浄しました。
少し全車にカスが見えますから、小筆で除去をします。

つくづく、惜しい窓です。
何でこんなにきついRなんでしょうね。

ヘッドライトはいつシールドビームになったのでしょう?
白熱灯時代のやや大きいヘッドライト別部品も用意していますが、改造時期の確証がなく困っています。

綺麗になりましたね。

先がまだまだ長い・・・。
サフェーサーを吹きますが、傷が深いと思われる部分がありますので、厚く塗りたいと思っていました。
そのままでは窓などが埋まりますので

マスキングテープで

残したいディテール部分を隠します。
前面は吹き付けをゆるくして、ほかはタップリ吹いていこうという算段です。

金属部品にはコレを小筆で塗りました。

吹いた状態。

屋根、屋根肩、車体裾にはコッテリと吹きました。
案の定、雨樋を落とすときに金ヤスリで当てたので、深い傷が結構見られました。
コレを磨いて埋めていきます。
今日はココまで。
良質なキットならば、30分でL字に組んで箱にする作業を何工程使ってやっているんでしょうね。

↑どんなヘビーな工作も、淡々とコツコツつづけることが飽きないポイントかなぁ?

車体裾がめくれ上がっているのが見えると思います。
まるでアコモ改造で72系の台枠に115系の車体を乗せたがために、台枠が切り立ってしまったモハ62系Ⅱのような雰囲気です。

これを耐水パーパーをひいて、車体をか半回転させながら均一にこすり、滑らかな絞りにします。
もちろん、靴ずりは消えてしまいました。
と、
この上の写真。
つまり妻面を右にして後ろのドアを良く見ると

なんじゃこりゃ・・・・。
ドアが長方形ではないんです。
全部車体。
これは直せない。
少なくとも自分には直す術が解らない。
くりぬいて金属ドアに置き換えたりしても、どえらいことになります。
ノミで仕上げてもキット4枚全部綺麗にいかず乱れる。
しょうがないので、ココは目を瞑ります。
ドアは残念ですが

裾は仕上げきりました。
本当にディテールといえば、窓とドアの窪み、パンタ台(何で残しているんだというくらい簡単なものですが・・・。)、代替部品が思いつかない避雷器ぐらいです。
避雷器、別部品にしたい筆頭なんですけど・・・。
連結面角・隅柱の角を落とします。

耐水ペーパーに宛がって・・・
ゆるい角度から、

ゴリっと角度付けて滑らせます。


こんな感じで繰り返し。
自分は7回繰り返すことにして角度を安定させようと試みました。

下が施工前
上が施工後
これを絞り部分や屋根Rも全部行います。
屋根R部は耐水ペーパーのほうを持って撫でていきました。

施工前の妻板を接させるとこのように隙間は殆どありませんが

施工後はRが突きあってくぼみが出来る程度に角が落ちました。

こんなイメージ。
いい感じでしょ?
きっとRは結構デタラメなんだろうけど。

隅柱の細さもマァマァいい感じ。

この形式、本当に芸が細かいというか、シンプルな美しさが凄い電車です。
さすが五島会長の秘蔵鉄道の電車です。
惜しむらくは、偉い苦労しないと、この電車の本当の美しさが再現できないことです。
東急車輛電車市場からトミックスあたりに作らせた模型がNで出たら、ココまでの苦労は水泡に帰すわけですから、悲鳴が上がるとともに、とことん再現するでしょうから買っちゃいますね・・・。

今になって思えば、なんで一組は切りついでサハとクモハ両運にしなかったのかと。
最低でも、更にその2台を作らないと、格好が付かないじゃないですか。
いや、こんなに徹底的にやるとは思わなかったからなんですけどね。
今なら、切りついで短くなりそうな部分、プラ板挟んでも全く支障ないくらい削り込んで磨いています。
切りついではいませんが、ある意味切りつぎよりへビーなことしていますもんね。

洗浄しました。
少し全車にカスが見えますから、小筆で除去をします。

つくづく、惜しい窓です。
何でこんなにきついRなんでしょうね。

ヘッドライトはいつシールドビームになったのでしょう?
白熱灯時代のやや大きいヘッドライト別部品も用意していますが、改造時期の確証がなく困っています。

綺麗になりましたね。

先がまだまだ長い・・・。
サフェーサーを吹きますが、傷が深いと思われる部分がありますので、厚く塗りたいと思っていました。
そのままでは窓などが埋まりますので

マスキングテープで

残したいディテール部分を隠します。
前面は吹き付けをゆるくして、ほかはタップリ吹いていこうという算段です。

金属部品にはコレを小筆で塗りました。

吹いた状態。

屋根、屋根肩、車体裾にはコッテリと吹きました。
案の定、雨樋を落とすときに金ヤスリで当てたので、深い傷が結構見られました。
コレを磨いて埋めていきます。
今日はココまで。
良質なキットならば、30分でL字に組んで箱にする作業を何工程使ってやっているんでしょうね。

↑どんなヘビーな工作も、淡々とコツコツつづけることが飽きないポイントかなぁ?