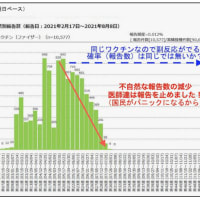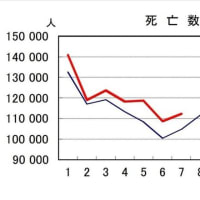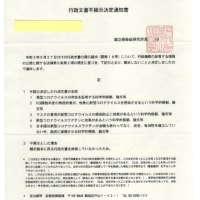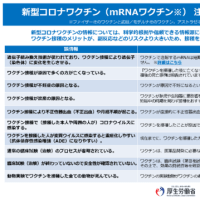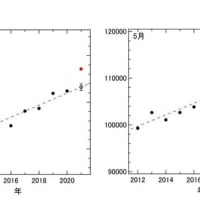私の憲法草案(その1)
いまだ書かれざる前文のための前文
去る4月26日、産経新聞が「国民の憲法」要綱を発表しました。
憲法改正気運が一定の盛り上がりを見せている中で、私はこれにたいへん刺激を受けました。この起草に当たった方たちの熱意と努力には労いの気持ちを表するのにやぶさかではありません。しかしいっぽうでは、一素人のまことに生意気な言い分ですが、この要綱は、基本的なところで「憲法」あるいは「近代法」というものが何であるかがまるでわかっていないなあ、という感想を持ちました。
折から、この要綱をもとにした、5月18日のチャンネル桜の番組「討論・倒論・闘論」で、起草者の方たちと法の専門家たちとの長時間にわたる議論を聴き、私の漠然とした感想が、まんざら間違ってもいないなという感を強くしました。
出席者は以下の方々です。
大塚拓(衆議院議員・自由民主党)
倉山満(憲政史家)
小堀桂一郎(東京大学名誉教授)
佐瀬昌盛(防衛大学名誉教授)
百地章(日本大学教授)
八木秀次(高崎経済大学教授)
山田宏(衆議院議員・日本維新の会)
司会・水島総
http://chsakuramatome.seesaa.net/article/361845646.html
このなかで、佐瀬さんと百地さんが起草者のメンバーです。これに対して小堀さん、倉山さんは、かなり対立的な立場から言論を張っていて、私はどちらかといえば後者のほうに共感を感じたのですが、起草する以上はなるべく現実的なものに仕上げようとする百地さんの配慮に敬服したのも事実です。
しかしここでは、この番組の出席者についての細かい論評は差し控えます。代わりに、全体を通じて私が感じたことを、その前に思っていたことと合わせて簡単にまとめてみます。
①憲法(統治のための基本的なきまり)は、時代を下るごとに条文の数と文章量が増えて、やたら細かくなってきています。じっさいに条文の内容を見ると、モノによってはほとんど実定法の領域にまで踏み込んでしまっています。これは、時代の多様化した要請に押し流されているために憲法というものの本質を見失っている証拠ではないでしょうか。
参考までに。十七条憲法は17条。御成敗式目は51条、武家諸法度および禁中ならびに公家諸法度は計36条、帝国憲法は76条、日本国憲法は103条、そして産経版「国民の憲法」は117条。
②産経版「国民の憲法」は、「独立自存の道義国家」という基本理念を打ち出していますが、人間の内面に踏み込んで方向づけを強いるような「道義」を主軸に置くことは、近代法の精神とまったく合いません。たとえば「家族の尊重」という項目を盛り込んでいますが、これは、いわば帝国憲法から見ても退歩であって、まして今の国民の普遍的な同意を得られるはずがありません。家族の解体を恐れる旧世代保守主義者たちの危機意識が露出したものでしょうが、もともとこういう問題は、必要と感じた者が日々のしつけや教育などを通じて保守していけばよい話です。
③チャンネル桜の番組での議論の「空気」は、現実主義と理想主義との対立という枠組みで進んでいました。つまり、佐瀬さんや百地さんのように、実際に起草にかかわった人たちは、理想はわかるが実用に耐えるものにするために、今の国民意識の平均的な部分をたえず気にかけなくてはならない、これはとりあえずの提案なので、自分たちもけっして完璧とは思っていないから、これから一歩一歩理想に近づけていけばよい、というのですね。 この③の論点がとても重要です。いかにも説得力のある主張のように思えますが、私は、これは違うと思います。理想と現実という対立項を、時間軸に転嫁して、「いつかは」と考えることは、まったくの幻想です。「一歩一歩」などという論理は永遠に実現しないでしょう。
そもそも「憲法」の言葉を新しく紡ぎだそうという動機には、二つの側面があります。一つは、現行憲法が解釈による運用では限界に達しているので、少しでも時代に合わせるために「改正」しようという現実的な動機です。もう一つは、GHQによるあんな一時的な押しつけ憲法は、日本の伝統的な国民性とはまったく乖離しているので、思想言語、哲学言語としての自主憲法を編み出さなくてはならないという思想的な動機です。
ところで、もし前者の動機にシフトしようと思うなら、産経版「国民の憲法」などを苦労して編み出す必要はほとんどないのです。いま一番問題になっているのは、主として日本の安全保障環境が危機状態にあるから何とかしなければという切迫感ですね。要するに9条です。
自衛隊が正規軍隊として認められていないために、他国の侵害を受けてもきちんと安全保障を確保できない状態が現に存在している。軍をもたないなどという規定は国際的に見て非常識以外のなにものでもない。そのためにはまず憲法を改正して、という話になるのですが、私は、この実践的な問題をクリアーするためにわざわざ憲法の大改革を目論む必要などない、と思っています。時々の政治問題は、なるべく早く解決すべきなのですから、最小の努力で迅速に所期の成果が得られるように行動するのが良い。
具体的に言うなら、9条2項(「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」)を削除するだけで済む話です。「国防」という新たな章を設けて「軍を保持する」などとわざわざ憲法で謳う必要はまったくありません。謳わないことによって、かえって軍の存在は自明なものとして承認されることになるわけです。また、これなら国民のコンセンサスを得やすいですし、同時に、自衛隊法の改正も根拠づけられます。別に憲法に根拠づけられなくても、実定法のレベルでどんどんやってしまえばいいのですが、まあ、「知らなうちに」とか騒ぎ出す連中がいますからね。一応、現憲法からの2項削除というかたちでのダメ押しは必要かな、と。
ここで産経版について感じることを言いますと、こういうことを一生懸命やる人たちは、いま、こういう問題があるからそれに対してできるだけポジティヴに発言しなくてはならない、という過剰な切迫感に駆り立てられているような気がします。気持ちはよくわかります。けれども、発言は必要最小限にしておいて、「うまく黙る」という方がいいこともあるのです。「削除」も立派な言語行為です。「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」を削るだけで、自衛隊はちゃんと「軍」としての根拠を与えられるではありませんか。
もし「国防」という章をわざわざ設けるなら、それと併行して「外交」とか「防災」とか「国民経済」とか「社会福祉」とか「教育」などという章も設けなくてはバランスを欠くでしょう。そうするとますます煩雑なものになっていきますね。
さて、後者の思想的な動機ですが、これは、「一歩一歩踏み固めていって」あとに延ばすというような悠長な問題ではありません。やるならいま、まさに日本の言葉で、日本国のアイデンティティをしっかり固めるという確固とした動機にもとづいて構築すべきです。これは、とりあえずのプラグマティックな必要とは別で、さしあたり使えなくてもかまわないのです。福澤諭吉が説いていたように、「政事」は応急手当、「学問」は百年の計としての日頃の養生、両者はその守備領域がもともと異なるというわけです。思想言語としての自主憲法案づくりは、法的・思想的な言語技術に優れた人たちがぜひ使命感と熱意をもって挑んでいただきたい課題です。これをやっておかないと、あとあと相当なツケが回ってきそうな気がします。
ですから、この二つの側面を同時に一つの言語で果たそうなどと欲張りなことを考えずに、政治的な対応としては、必要最小限の改正で済ませ、いっぽうで、思想言語としての「憲法」は、現行憲法とはまったく異なる新しい構成によるもの(帝国憲法の改正というかたちでもいいと思います)を、専門家、思想家がいま提示する。こうした同時進行が要請されているので、前者からだんだん後者へ、とか、後者をただちに実用可能なものとして構想するなどと考える必要はありません。
私もできればお役にたちたいのですが、法的な言語の創造には相当の専門的な力量が必要とされるため、はっきり言ってビビッています。さしあたり私にできることを試みます。ゼロからやれ、と言われると、正直かなり厳しい。たまたま産経版があるので、失礼ながらこれを踏み台にしつつ、「私の憲法草案」を提示します。とりあえず産経版の文言で利用できるところはそのまま踏襲しながら、構成としてはズタズタにしたものです。
産経版があることにはとても感謝しますが、これはしょせん現行憲法の「改正版」であり、妥協の産物です。そうではない仕方で、思想言語としての「憲法」を自分なりに示したいと思います。たった一晩で考えた代物ですので、いくらでもボロの可能性があります。まな板で存分にたたいていただければ本望です。
なお、「前文」については、産経版ではダメだと思っていますが、代案はまだ出せません。これをしっかり考えようとするととても大変です。私は「前文」ってなくてはならないのかなあ、と迷いますし(まあ、草案を提示する以上はあったほうがいいのでしょうね)、そもそも憲法って、必要なのかなとさえ思っています。皇室がしっかりしていて、実定法が整っており、国民の間に基本的な人倫の習慣が根付いていれば、別に絶対必要と考えることもないのじゃないか。ご承知のように、イギリスには憲法がありません。でも何とかやっています。「よき慣習」の力でしょうね。
さて、草案を提示する前に、「憲法」というものに対する私なりの基本的な考えを述べておきます。
①そもそも憲法とは何か。欧米語の「constitution」は、「構成」という意味ですが、この言葉にはまた、「体質」とか「気質」といったニュアンスがあります。この面から言えば、ある国の「国柄」を表現したものということになり、この点で産経版の基本の構えには同意します。
また日本語の「憲法」という言葉には、「公平であること、公正であること」という意味があります。両者を合わせ考えると、「国家共同体の国柄を、イデオロギー的な偏りを排して公正に表現したもの」となりましょうか。
②すでに述べたように、憲法は実定法ではなく、実定法を整備していくにあたっての基本的な指針ですから、なるべく簡素を旨とすべし、です。先ほどのテレビ番組でも、十七条の三倍くらいでよい、という意見が出ていましたが、私も賛成です。細かいところに踏み込むことをあえて避け、抽象性を担保しておくことによって、かえって、あらゆる社会問題を包括でき、しかも条文をタテにとった悪用・濫用を避けることができます。世の中には、私的な争い、公権力への身勝手な異議申し立てなどに、すぐ憲法を葵の印籠のように持ち出す向きが後を絶たないようですが、そういうことは法律のレベルでやるべきことです。憲法はルール細目ではないのです。
憲法が忙しく駆り出されることがないように、その条文は一定の抽象レベルを保つべきであって、またその方が時間に耐えるものができるはずです。細かく書き込めば書き込むほど、すぐに時代に合わなくなり、その権威が軽いものとなってしまいます。また、簡素にすることによって、重複や不整合を避けることができます。現行憲法は、特に権利規定の部分などにとても重複が多いですね。
③以上のことは、同時に、憲法起草に当たっての二つの禁じ手を要求することになります。ひとつは、多様な国民の諸欲望の実現のためにみだりに利用されてはならない。もう一つは、人間の内面を誘導するものとしての特定の「道徳」的な規範を盛り込んではならない。 ちなみに、産経版が「家族の尊重」を謳っているのと同じように、しかし逆の意味で、現行憲法が「個人の尊重」(13条)とか、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて」とか「両性の本質的平等」(いずれも24条)などと謳っているのも、人間の内面や私的生活への道徳的な介入であり、くだらない規定です。
④日本は立憲君主制国家ですが、この場合、「君主制」の部分は、歴史や伝統をいまに生かすもの、いま国民として生きている私たちの実存に過去からのつながりとしての自覚を与えるものです。しかし、近代社会はその構造を複雑多様に分化させており、残念ながら過去からのつながりを自覚しただけでは社会秩序そのものが立ちいきません。
そこで「立憲制」が必要とされるのですが、いわば立憲制は、君主制(代々の王の人格や意志や行為を国柄の中心と考える)の限界を補完するものにほかなりません。いつも一人の名君によってうまく治まる保証はどこにもありませんし、それは実際無理なことです。多くの政治的にすぐれた人々による統治機構がどうしても必要になります。王はただ国家の権威の象徴として存在し、実権をもってはならない。立憲君主国においては、「君臨すれども統治せず」の原則が貫かれなければならないゆえんです。事実、日本は近代に限らず、長い歴史の中で、「憲法」のない時代でもほとんどずっとそうしてきましたね。
ですから、「憲法をちゃんと決めなければならぬ!」という思いは、近代社会の複雑さ、多様さに対する国家の危機意識の表現なのであって、もし伝統的権威や慣習や、それにもとづく実定法に従うだけで国がやっていけるなら、それに越したことはないのです。それがそうもいかないので、補完物としての憲法が必要になる、ということでしょう。
⑤「憲法は国家権力への縛りである」という説がこれまでリベラリストを中心に幅を利かせてきましたが、この説は、憲法の一機能を説いたものにすぎません。これはマグナ・カルタに始まる西欧の憲政史上の事実を絶対視するところから出てきた説で、日本には日本独自の憲法観があってよいし、また欧米でさえ、こんな一方的な憲法観によって憲法が編まれているわけではありません。
憲法とは、国民に福利と安寧をもたらすための国家統治の基本的な構えを謳ったものですから、公共精神がその根幹にあります。そうである以上、国民の権利を最大限認めつつ、同時に国民に一定の義務と責任を自覚させるためのものでもあります。それは、国家機構の仕組みを明らかにするとともに、自分たちはどういう国の民であるか、何ができ、何はできないかという疑問に対して、基本的なイメージを与える機能を持ちます。
⑥現在、憲法を考えるとき、「主権」をどこ(誰)に置くかという点が真っ先に取り上げられるのが習いです。もちろん、帝国憲法の主権者は天皇、戦後憲法の主権者は国民ということになっています。当然、どの改正案でも、主権者を「国民」とすることは、最重要な規定であり、しかも自明のこととして通用しているようです。
しかし、私はこれを疑います。もともとこの「主権(sovereign)」という言葉は、ヨーロッパの国王が自らを統治者として正当づけるために用いた言葉で、それが近代になって王権の実質的な崩壊とともに、では誰が統治の主体なのかという問いが持ち上がり、とりあえず「国民」という茫洋たるフィクションにその役割を託したわけです。けれども国民が国民をみずから支配統治する、というのは、どう考えてもロジックとしておかしいですね。現実に平凡な国民の一人ひとりが国家体制の運営主体として自分たち自身を支配・統治するなどということがどこかで行われたためしがありますか。
日本には、こんな概念はもともとありませんでした。いまの人たちはほとんど、日本は民主主義国家なのだから主権在民は当たり前だ、と思って何の疑いも抱かないようですが、外来のこの言葉が、近代日本の国家機構の仕組みを説明するために本当に不可欠かどうか、少し疑ってみてはどうでしょうか。こんな言葉を用いなくても、現在の国家体制(選挙によって選ばれたメンバーによる代議政治、三権分立の仕組み、国民の諸権利の保障など)を少しも変えずに合理的に説明することは可能です。
第一、自民党案も産経版も、天皇を「元首」としながら、いっぽうで「主権は国民」と謳うのはおかしいではありませんか。「元首」もsovereignですよ。
「国民主権」を謳わないと、専制権力のほしいままを許すのではないかという過剰な恐れがあるようですが、そういう恐れを払拭するためにこんなアクロバティックな論理を用いる必要はまったくありません。二つのことを謳っておけば済む話です。
ひとつは、現実の統治権は国民によって選ばれた代表者が握り、代表者は常に国民の福利と安寧のために尽くす義務と責任があるということ。もう一つは、国民にはこれこれの権利があり、それは侵されてはならないということ。
よい国家とは、民に支持されたすぐれた統治者による、民のための政治が行われる国家であって、民はその恵沢を享受する権利があるのです。「国民」という抽象語に統治権、支配権を託すなどというわけのわからぬフィクションは、冗談としか思えません。
そこで、以下に提示する草案では、国政にかかわるかぎりでの「主権」という言葉をいっさい用いませんでした。ただし、国際関係の場では、一国はあたかも社会のなかの「個人」のような位置にありますから、個人が自分の生を自己管理しなくてはならないのと同じように、他者(他国)との関係において、「国家主権」という概念を用いる必要があるのは当然です。
⑦「国体」という言葉は、まさにその国の国柄、国家体制のあり方を表わす言葉ですが、戦前の国家体制に対するアレルギーから、すっかり使われなくなってしまいました。しかし、アレルギーから自由になってよく冷静に考えてみましょう。この言葉は、憲法のなかで、日本がどういう国なのかということを端的に説明するために、まことに簡潔で便利、しかも格調のあるふさわしい言葉ではないか。
これまで、「国柄」というソフトな言葉を用いてきましたが、じつはこの言葉は、外国の文化風習などについて話す時に「お国柄ですね」というように、気安く使われるところがあります。それだけ含むところが広すぎて概念として曖昧なので、憲法の用語としてはふさわしくないと思います。産経版でも反発を恐れて「国柄」としていますが、これは遠慮見え見えですね(まあ、それは仕方がないでしょう)。
しかし、すぐに実用性を顧慮する必要のない思想言語としての憲法を考えるかぎり、堂々と「国体」という言葉を用いるべきだと私は考えます。日本国の国家体制は何であるかということを何よりも先んじて明瞭に規定する必要があるからです。constitutionが「体質」を意味するという点にも合致しますね。このことは、これから先、誰が新憲法を構想する場合においても変わらないでしょう。ヘンな連想ゲームはもうやめましょう。
ちなみに、GHQ占領統治下の日本は、皇室は維持されたものの、実質的な統治権を喪失したのですから、国体はいったん壊れたのです。当時「国体は護持された」などと担ぎまわった人たちが権力の中枢部にいたようですが、負け惜しみであり、欺瞞です。
⑧産経版で新たに付け加えられた、衆議院に対する参議院の独自性、部分的な優越の規定は、とてもよいと思います。私案でもそのまま踏襲します。貴族院を復活させるわけにもいかず、さりとて今のままの参議院がいいとも言えず、一院制は衆愚政治への最短距離なのでとんでもない。これも頭の痛い問題なのですね。産経版は、そのあたりよく工夫されているようです。
ただし、参議院に行政監視院を新設するというアイデアに関しては、国会議員の国政調査権や、会計検査院の業務と相当かぶることが予想され、役割分担の調整が困難です。いまのところペンディングとしたいと思います。
⑨現行憲法は、あわただしく作られたせいもあってか、叙述の順序がおかしかったり、この章に収めるべきだと思われる条項が他のところに入っていたりする混乱が目立ちます。産経版は、この点に対する配慮を施した形跡がありません。自主憲法ではなく、現行憲法の「改正」という枠にこだわりすぎたのでしょう。おまけに法律で書けばいいものをやたら書き込んで、混乱をいっそう助長している印象があります。たとえば、「第十一章 緊急事態」の規定は、一一四条の一部を除いて、他はすべて法律(緊急事態法)で謳えばよい話で、しかもこの一部は、一章を設けずに、「内閣」の章に組み入れれば十分です。
⑩現行憲法96条の改正が話題となっていますが、これを提起した自民党は、反発が強いとみるや、7月の参院選を考えて引っ込み思案になっているようです。政党としてのその気持ちもわかりますが、もしこれを争点として打ち出すなら(私は打ち出すべきだと思いますが)、たとえば発議要件としての「総議員の三分の二以上」を「過半数」に緩和するという提案はそのまま通し、改正要件としては「国民投票において六割以上の賛成を要する」としてはどうでしょうか。これなら通りやすいのではありませんか。ほかにもいろいろアイデアは考えられるでしょう。
⑪小さなことですが、現行憲法およびこのたびの産経版には、「何々は、法律でこれを定める」という条文が多すぎます。そんなことは当たり前なので、ほとんどの場合、要らぬ贅語です。憲法の最高法規性を謳っておけば、それ以外に何も言う必要はありません。
最後に感想として、現行憲法が、その思想、文体、煩雑さ、記述順序の混乱、同一内容の重複、不整合など、いかにお粗末な代物であるかということを再確認しました。正直なところ、今回この試みをやってみるまでは、その事実を実感していませんでした。私個人にとっては、一つの収穫だったと思っています。
では次に、私の憲法草案を提示します。