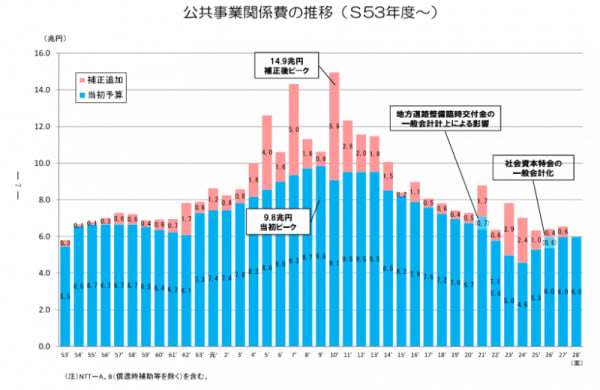所有者不明の土地は全国で410万ha、これは九州全域を超える面積です。
2040年には北海道本島に匹敵する720万haに及ぶと推計されています。
政府は、管理できない土地の所有権を所有者が放棄できる制度の検討に入りました。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31241990R00C18A6MM0000/
一方、参院本会議では、所有者不明の土地を公共目的に限って使える特別措置法を可決しました。
防災や都市計画の妨げになるというのが理由です。
この法律では最大10年、民間業者やNPOなどに土地の利用権を与えるのが柱とされています。
都道府県知事が公益性などを確認した上で利用権を定めることになります。
利用権は延長もできるそうです。
https://www.asahi.com/articles/ASL664HKLL66ULFA00S.html
この二つのニュースでまず驚くのは、所有権のない土地の面積の巨大さでしょう。
次に思うのは、こういう事態を放置していた行政機関の怠慢です。
しかしそれはとりあえず差し置き、所有権放棄の制度創設、所有者不明の土地の有効活用という法律の可決は、一見よい方向への一歩のように思えます。
しかし、次のような連想と疑念を抱くのは筆者だけでしょうか。
現在、中国が日本の土地を爆買いしています。
すでに北海道や沖縄を中心に、全国土の2%が中国人の所有になっています。
https://www.recordchina.co.jp/b190071-s0-c20-d0035.html
2%というと静岡県全県にほぼ匹敵します。
この話題は一年前にも取り上げたのですが、
https://38news.jp/economy/10151
このような事態を招いたのは、外国人が土地を取得することに対して法的な規制がないことが原因です。
WTOのGATSという協定が内国民待遇義務というのを定めているので、それをバカ正直に守っているのですが、インドやフィリピンなどは、GATSに加盟していながら、外国人の土地所有を原則不可としています。
政府各省庁もそれを知っていながら、中国人の土地爆買いに対して何らの法的な措置も講じようとはしません。
国会議員も昨年12月に自民党の鬼木議員が問題視した程度で、動きが非常に鈍い。
http://www.buzznews.jp/?p=2113292
また6月10日のTVタックルでも(ようやく)取り上げていましたが、国防の要地であるはずの対馬が韓国人の観光客であふれかえっているだけでなく、韓国人に不動産を爆買いされ、民宿、ホテル、釣り宿など、彼らの思いのままに建設、経営されています。
海上自衛隊対馬防備隊本部に隣接する土地に十年前リゾートホテルが建設され、その後、周辺地域に次々と韓国資本によるロッジが建てられました。
いたるところハングル文字だらけ、もはや対馬は日本ではないとぼやく地元の人たちもたくさんいます。
韓国のツアー客が大挙して対馬に来ると、ツアーガイドが開口一番、「対馬はもともと韓国の領土です」と説明するそうです。
こんな事態になっているのに、対馬市当局は何と、どれくらいの土地が韓国人の手にわたっているか、把握していません。
https://www.sankei.com/life/news/171030/lif1710300021-n1.html
こういう危機的状態は、政府がいち早く手を打たない限り、今後ますます加速するでしょう。
初めの二つの記事に書かれていたこと、
つまり、
九州全域に相当する土地が所有者不明という事実、
所有権放棄の制度の創設、
公共目的に限定して、民間業者やNPOに土地の利用権を与えるという趣旨。
これらは、中国や韓国の爆買い攻勢を想定しているでしょうか。
不動産の外資規制がまったくない状態で、民間業者やNPOに土地の利用権を与えるのは、
中国人や韓国人にも、どうぞ爆買いを進めてくださいと言うのと同じではないでしょうか。
公共目的など、何とでも名目を作れます。
途中で営利目的に変えちゃったっていいのです。
日本名義のダミー会社に買わせる手もあります。
彼らはきっとそうした巧妙な手を使うでしょう。
まして、外国人が利用を申請してきた時に、いまの都道府県にそれを抑える論理と力があるとは到底思えません。
考え方が根本的に甘いのです。
ここには、いまの日本の行政機関が、それぞれ問題別に解決策を追求するだけで、総合的に危機に対処する力を喪失している状態がいみじくも象徴されています。
やがて北海道本島にまで広がりかねない所有者不明の土地。
すぐにでも公有化を進めるべきです。
国や地方自治体が素晴らしい公共施設を作ればいいではありませんか。
財源をどうするか?
いいかげんに、財源の話はしないでください。
大いに建設国債でも発行すれば済む話です。
またまた日本が自分の首を絞めている事実を痛感しました。
【小浜逸郎からのお知らせ】
●新著『福沢諭吉 しなやかな日本精神』
(PHP新書)が発売になりました!

http://amzn.asia/dtn4VCr
●『日本語は哲学する言語である』(仮)
を脱稿しました。徳間書店より7月刊行予定。
●『表現者クライテリオン』第2号
「『非行』としての保守──西部邁氏追悼」
●月刊誌『Voice』6月号
「西部邁氏の自裁死は独善か」
●『表現者クライテリオン』9月号特集
「ポピュリズムの再評価」(仮)の座談会に
出席しました。(8月15日発売予定)