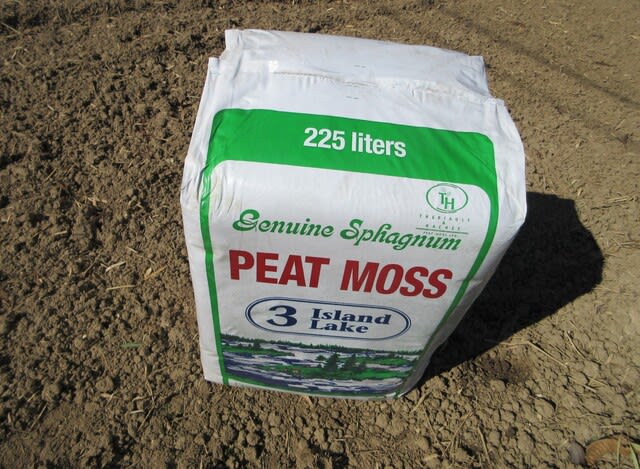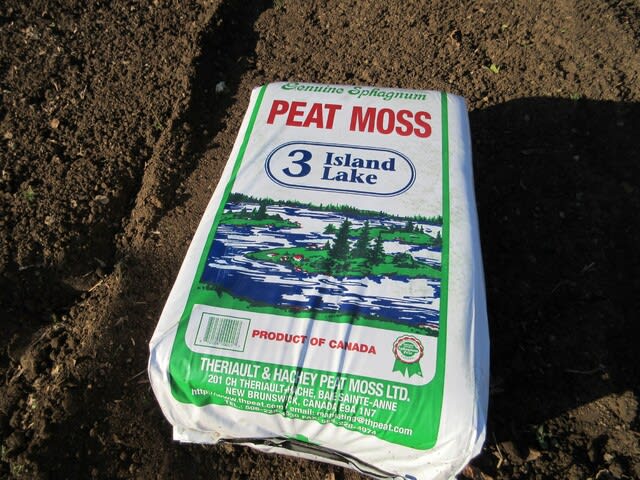ナバナ類の一つ「寒咲花菜」、今年は豊作です。

11月末から主枝の収穫を開始、年明けからはわき芽(側枝)を穫り始め最盛期となりました。
今はわき芽(1次側枝)とそのわき芽から出る孫茎(2次側枝)が混在しています。
今はわき芽(1次側枝)とそのわき芽から出る孫茎(2次側枝)が混在しています。

しかし、寒咲きの花菜とは言え当地で厳寒期を乗り切るのは容易ではないのです。
酷寒ともなれば凍害を受け、今頃は多くがギブアップしていてもおかしくありません。
昨年は連日最低気温-5℃以下まで下がり、今頃はかなり凍害を受けた株が目立ちました。
酷寒ともなれば凍害を受け、今頃は多くがギブアップしていてもおかしくありません。
昨年は連日最低気温-5℃以下まで下がり、今頃はかなり凍害を受けた株が目立ちました。
今年は一時的な寒さのぶり返しはあるものの総じて言えば暖冬、昨年と比べ明らかに株の姿が良い。

但し、外葉はすでにかなり老化し寿命に達しているとも言えます。
この時期になって株による優劣がはっきりしてきました。
言えることは、このように勢いが良いしっかりした株は耐寒性が付いて凍害にも強いと言うことです。
言えることは、このように勢いが良いしっかりした株は耐寒性が付いて凍害にも強いと言うことです。

発芽から追肥土寄せあたりまでの初期の管理が非常に大事だと分ります。
旺盛な株はわき芽(1次側枝)が10本くらい出ています。
勢いの悪い株は凍害で尽きるかに見えましたが、春のような陽気が数日続いたことで復活してきました。
旺盛な株はわき芽(1次側枝)が10本くらい出ています。
勢いの悪い株は凍害で尽きるかに見えましたが、春のような陽気が数日続いたことで復活してきました。

これは少し遅れ気味だったわき芽(1次側枝)。

わき芽(1次側枝)は花芽が大きくこの時期になると蕾が膨らみます。2、3芽残して切り取り収穫します。
早くに収穫したわき芽(1次側枝)からはさらにわき芽(2次側枝)が伸び収穫しています。
この孫にあたる茎から出る花芽はこのように一回り小さい。しかし、今年は良いものが穫れています。

大きな外葉が下がり枯れたものも出てきたため沢山の蕾が見えるようになり、収穫の盛りらしい姿です。
花の咲いているものを見つけました。

花菜は多少花が咲いても大丈夫ですが、やはり蕾のうち、花の咲く直前が一番美味しい。
花菜は皆から人気があり、穫り遅れることが殆どありません。
これは助っ人が穫って我が家の分と置いていったもの。

穫り始めの頃のわき芽と違って丈が短くなっていますが、花菜らしい姿といえます。
葉が短くなり蕾が目立っています。

蕾、茎、新葉と軟らかく風味があり、用途も広い。
小生の好物は卵とじ。自身でもよく作ります。

たかが卵とじ、されど卵とじ。